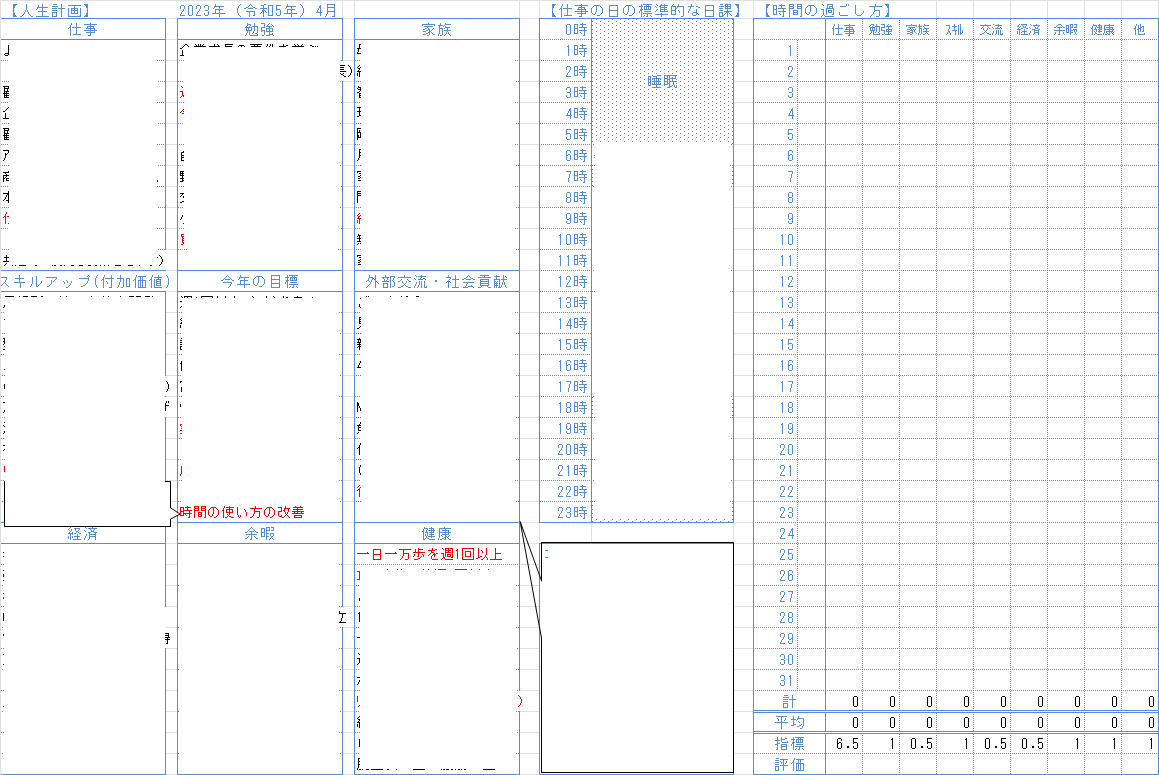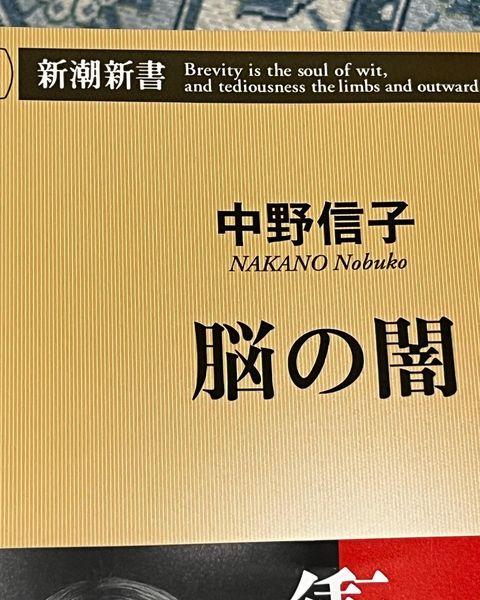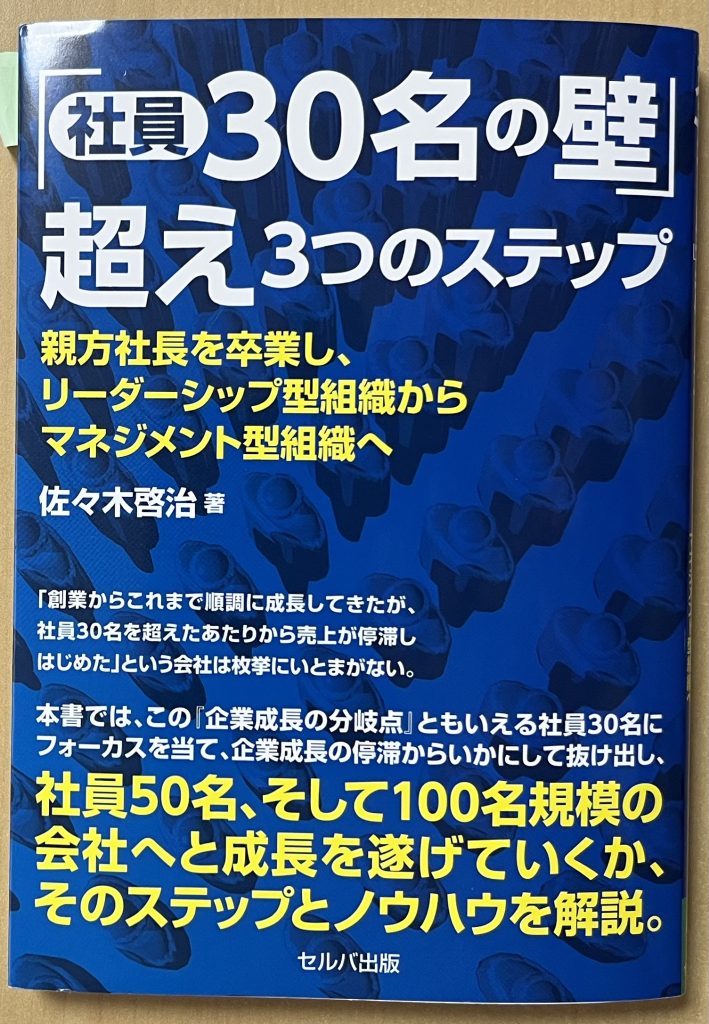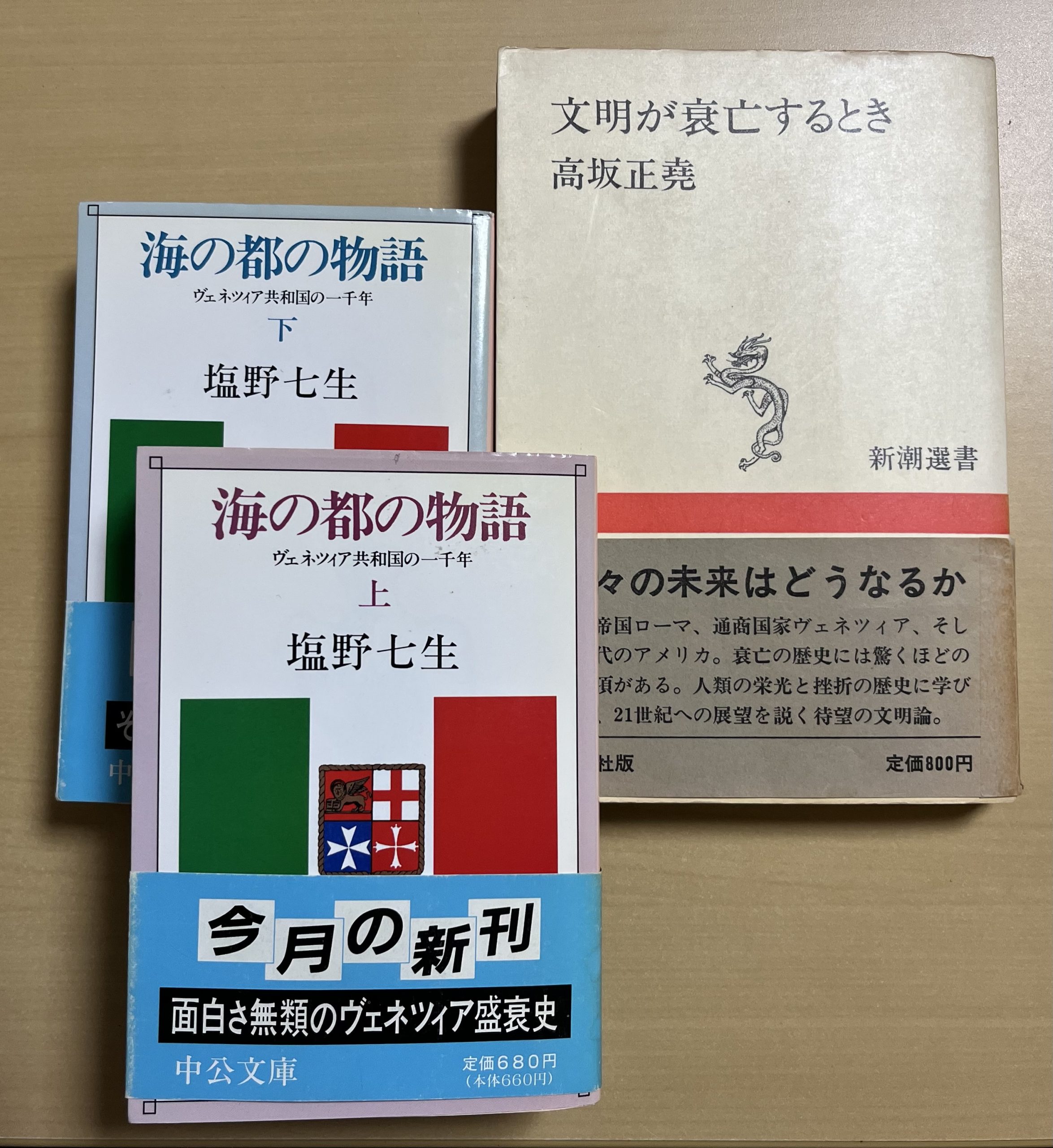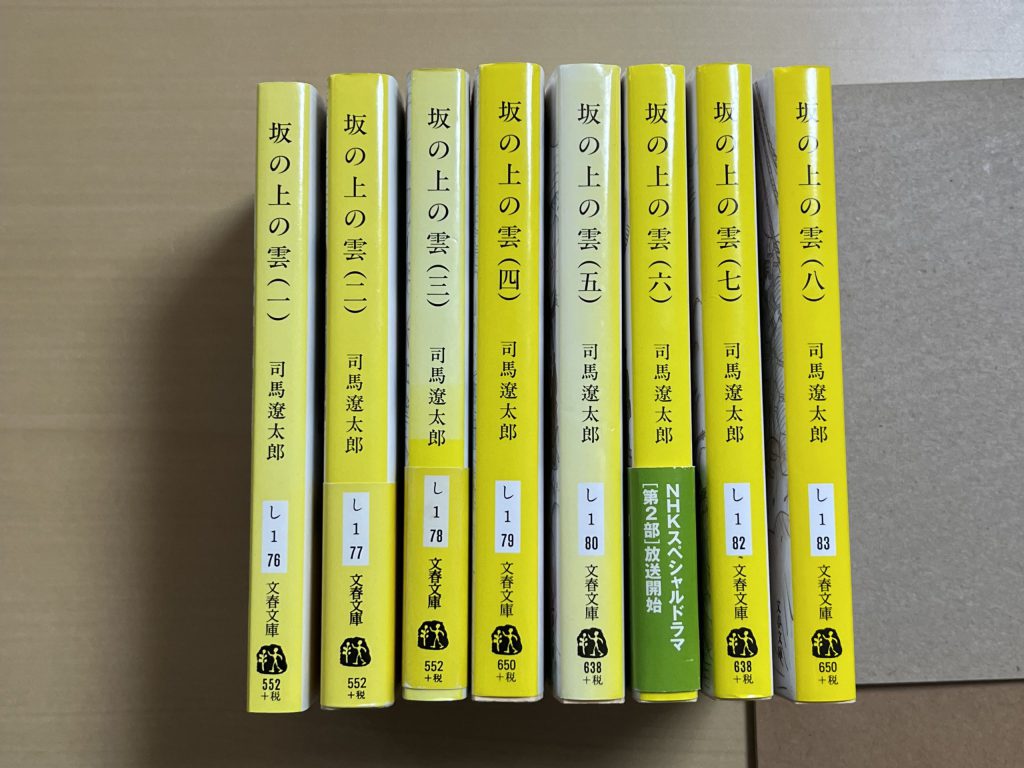ある仕事で、企業の経営者の相談相手として伴走的に関わるということをしています。「経営力再構築の支援」というような言い方がなされている業務です。「経営力再構築」とはどういう状態からどういう状態になることを指すのか、あまり明確な定義があるわけではないようですが、経営者がこれまで気づかなかった会社内の問題やなるべく考えないようにしていた問題などに、経営者が目を向け主体的に解決に取り組むことを目指しているようです。
その仕事を始めて約一年が経過しますが、いくつかの企業と取り組んでいる中で、「価値観教育」と「組織力強化」がとても大事であり、かつこれらの企業に共通した課題だなと最近感じています。そのうち「組織力強化」は組織の中間にいる人たちのマネジメント行動(もちろん「考え方」が前提として必要です)ができるようになることです。「価値観教育」については、社員が10名ぐらいの間は、大抵の場合は社長と社員がいつも同じ釜の飯を食べるといった、物理的にも心理的にも近い間柄のため、ことあらためて価値観を合わせるようなことは必要ないのですが、規模が大きくなって行ったり、中途入社の人が増えて行ったりすると、徐々に社長の思いや大事にしていることや行動基準のようなものが伝わりにくくなっていきます。そのうち組織の崩壊、なんてことにもなりかねません。
成長を志向し、組織力を強化していこうという企業にとっては、価値観をどうしていくかということが大きな課題になるようです。そんなことを感じながら、ハーバードビジネスレビューの2023年4月号「価値観」特集を読みました。
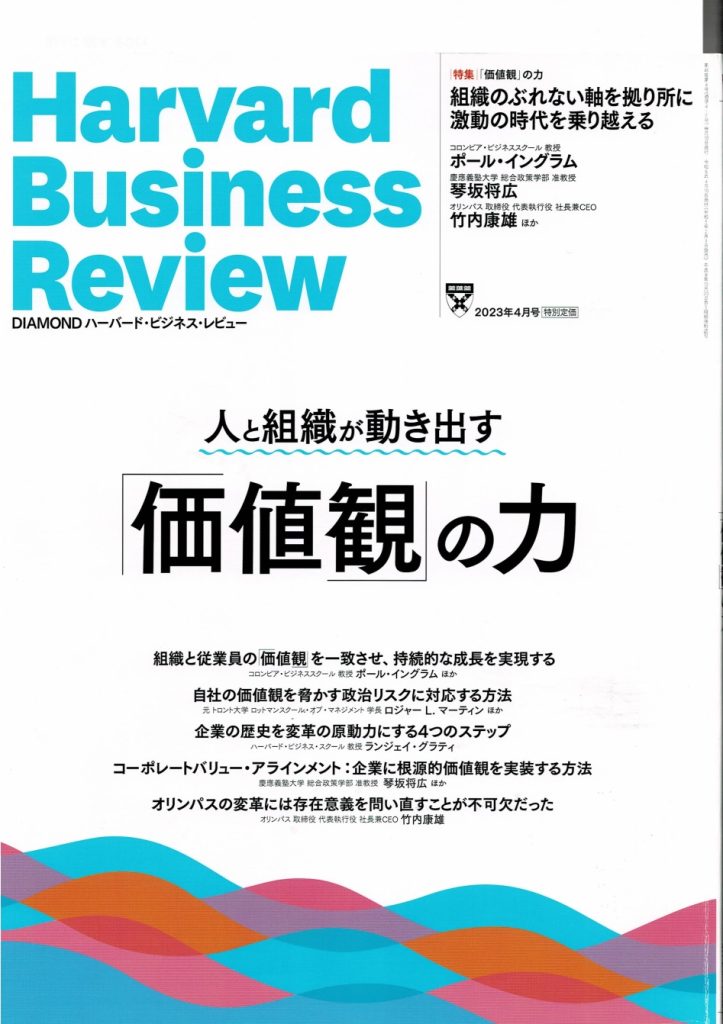
価値観という言葉の定義や、パーパス、企業理念、ミッション、ビジョン、バリュー、経営方針、行動指針など、企業の方針的なことを表す言葉は沢山あり、何が上位概念で何が下位概念かといったことも、言う人によって一様ではありません。この本では、コーポレートバリューという考え方を提唱しています。コーポレートバリューは、①企業が最終的な到達を目指す地点と、②企業および企業の構成員の心構え、の2つの要素で構成される、とのことです。①をパーパス或いはミッションと呼び、②をバリューと呼んでいます。パーパスは社会課題などを背景として自社が社会で果たすべき役割や社会に提供したい価値であり、企業が存続する限り追い求める高邁な理想、内発的に形成されるもの(但し、経営者の独りよがりの「やりたいこと」とは少し違う)であり、多様な人材が一つの組織に集まって協働する理由であり、バリューは、目指す地点(①)にどのように向かうかを規定するものであり、「心構え」だとあります。
目指す方向がずれている人、企業が望むような行動様式が取れない人、をどうするか、といった問題も発生しています。価値観の合わない人、というのが従来の言い方になるかも知れません。ここでは価値観=目標=ゴール(=パーパスやミッション+バリュー)という言い方なので、「目指す方向」というのがが近いように思いますが。そこを目指そうとせず、そのための「心構え」(お客様からの様々な刺激に対してどう反応・行動するかといった従業員に共通的に心得ておいてもらいたい行動の基準みたいなもの)が他の人と異なる場合は、どうするのか。価値観の合わない人は出て行ってもらう、というような簡単なわけにはいきにくい時代になっています。人手不足の問題もありますが、多様性がイノベーションを生む土壌であるということを考えると、そのような人をどうやって包摂していくのか、という難しい課題にも対応していくことがこれからは必要かも知れません。見ないふりをするのではなく、かといって退場してもらうのでもなく、しかし社内での他の従業員との軋轢を放置せず、いかに包摂して自社のパワーを高めていくか。難儀ですがこれからの企業にとって取り組む必要のある課題ではないかなと感じています。
さて、この冊子には、コーポレートバリューを組織内にうまく浸透させることがとても大事であるということや、そのための方法論なども書いてあり、ここでは省略しますが、実務の中でも参考にしていきたいと思っています。