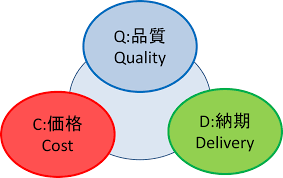塩野七生さんの『ローマ人の物語』、文庫版の第27巻、28巻を読んだのがもう4~5年前のことになります。
第29巻からはローマ帝国の晩年に入っていきます。サブタイトルが「終わりの始まり」。
物語は上を向いて進んでいく最中は書き手も楽しそうな言葉が躍っているし、それを読む私たち読み手もワクワク感があります(秀吉や信長などに関する書き物に対する個人的な印象です)。
この『ローマ人の物語」もカエサルやアウグストゥス辺りの筆致はとても明るい感じなのですが、ティベリウス以降はちょっと事実を丹念に記述することにエネルギーが費やされているような少し下り調子な印象を受けます。
そのためか前半とは著しく読書テンポが落ちてしまっています。
今回の主人公はマルクス・アウレリウスです。
この人は哲人皇帝と言われ『自省録』というストイックな哲学の本を書いており、第29巻においてもあちこちにその内容に触れられています。こりゃあ『自省録』を読まないと先に進みづらいなと感じてしまい、『自省録』を買うまでに数年かかってしまいました。先だって読み終え、ようやく第29巻再開となりました。
さて。
世界史では「ゲルマン民族の大移動」の時期を西暦375年( み な ご そっと移動)というふうに覚え、それが長期的なトリガーとなってローマ帝国が滅びた、と教わった記憶があります。
塩野さんのこの本にはこういう記述があります。
「番族の首長たちが首都を訪れ、彼らから皇帝に、帝国の支配下に入って他の属州民と同じ立場になりたいという申し出がなされた。しかし、皇帝は、ローマ帝国に何の効用ももたらさない人々を受け入れるわけにはいかない、と答えて、この人々の申し出を断った。」「これこそが、時代の変化の予兆であったのだ。紀元160年といえば、アントニス・ピウスの治世の最期の年で、この「慈悲深き人」は翌年に死去し、紀元161年からの皇帝はマルクス・アウレリウスに代わる。」「マルクス・アウレリウスも、この一事が時代の変化の予兆であったことに、気づかなかったということになってしまう。」(P197~198)
「紀元170年の春を期して、ローマ軍はドナウを渡りダキアを北上し、大規模な攻勢に打って出た。」(P215)
「ローマ軍の攻勢がダキアの北に集中しているスキを突いて、ちょうどその両脇にあたり地点からドナウ河を渡ったゲルマンの二部族が、実に大胆な行動に出ていたのだった。」「ウィーンの軍団基地を避けてそのはるか上流からドナウを越えたマルコマンニ族は、ローマ領内に入った後もひたすら南下してアクィレイアを襲撃した。」(P216)
「リメス(防壁)破らる!の報が、帝国の西方に波のように広がっていった。」(p218)
塩野さんがこの先どういうふうな話しの展開をなさるのかは読んでみないとわかりません。
私の推測では、これらの記述が次のようなことの伏線になっているのではないかと感じています。
カエサル以降、ローマは統制の取れた強い軍隊を持ちつつも、恭順してくる他部族に対しては、生存を認め、部族長にはカエサルという名前を与えることすら行い、農耕を進め定着を促し、闘う必要性をなくしてローマ化していったという平和維持のやり方を採っていたのに、このアントヌス・ピウス、そしてマルクス・アウレリウスは「ローマ帝国に何の効用ももたらさない」「撃退すればよい」という考え方で時代の変化にあった判断をせず、排外的で内向的な政策を取ってしまった・・・。
つまりこれまでローマを発展させ安定させてきた価値観の一つである「寛容」と反することを時の皇帝が行ってしまったことが、近隣諸国の態度を硬化させ、それがゲリラ戦を招き、長い国境線を維持することによる疲弊と国力の低下をもたらしたのがローマの崩壊の遠因だ。
少し遡ったところにこのような記述があります。これはアントニヌス・ピウス治世5年目に行われたアリスティデスという学者による演説からの引用です。
「ローマは、すべての人間に門戸を開放した。それゆえに、多民族、多文化、多宗教が共生するローマ世界は、そこに住む全員が、各々の分野での仕事に安心して専念できる社会をつくりあげたのである。・・・中略・・・ローマ人は、誰にでも通ずる法律を整備することで、人種や民族を別にし文化や宗教を共有しなくても、法を中心にしての共存と共栄は可能であることを教えた。・・・中略・・・かつての敗者に対しても数多くの権利の享受までも保証してきたのである。」(P25)
ピウスの晩年の判断は、果たしてこのローマの価値観からしてどうだったのだろうかと考えてしまします。
塩野さんはこの巻でもカエサルを高く評価しています。
「カエサルは天才だ。そして、天才とは、他の多くの人には見えないことまで見ることのできる人ではなく、見えていてもその重要性に気づかない人が多い中で、それに気づく人のことなのであった。」と。
このような記述によって、五賢帝最後の2人が国境線の向こう側で起きている変化に気づかなかったことを問題視しています。
彼らがカエサルのような天才ではなかったからだ、と言ってしまえばそれまでですが、この2人の皇帝はともに首都ローマからほとんど出ることなく過ごしていたようです。その前のハドリアヌスが皇帝時代の大半を前線の点検・対策・点検(PDCAで言うところのC⇒A⇒Cの繰り返し)に費やしていたのとは大違いです。
つまり、問題は現場で発生している、又は発生し得るということを感覚的に知っていてそれへの対応をしっかり行っていた前帝とは異なり、これら2人の皇帝は残念ながら現場を見ずに過ごしていたがために、現場の問題に気づけなかったのではないか、という仮説が考えられます。
「現場を見ず現場の問題に気づかなかったこと」そして「伝統的な寛容の精神と反する力技だけに頼ってしまったこと」これらがローマ帝国を崩壊に導く序曲となったということをこの先塩野さんが書いてくれていそうな気がします。・・・第30巻へ続く。
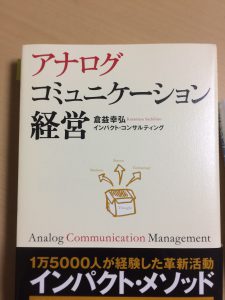
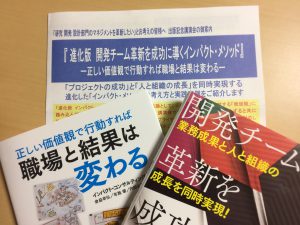 一気に事例本も2冊同時上梓です。大変エネルギッシュな取組事例の紹介があり、久しぶりにインパクト・コンサルティング社とそのノウハウを採り入れられた企業の情熱に触れることができ、自分自身改めて何をなすべきかの決意を新たにしたところです。
一気に事例本も2冊同時上梓です。大変エネルギッシュな取組事例の紹介があり、久しぶりにインパクト・コンサルティング社とそのノウハウを採り入れられた企業の情熱に触れることができ、自分自身改めて何をなすべきかの決意を新たにしたところです。 店員さんに「こういう所で働けるってとっても誇らしいですね」というキザな言葉が思わず口を突いて出てしまいました。
店員さんに「こういう所で働けるってとっても誇らしいですね」というキザな言葉が思わず口を突いて出てしまいました。