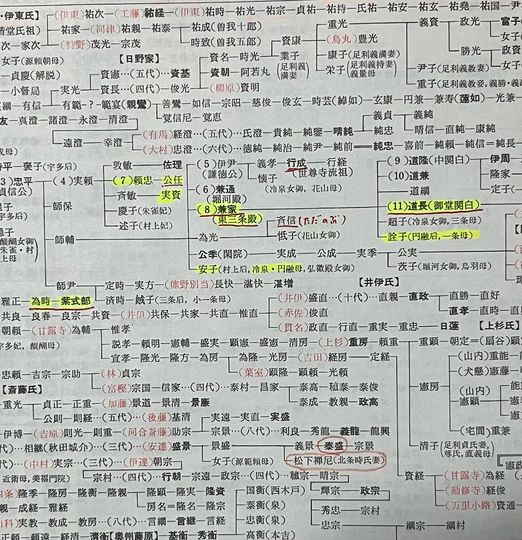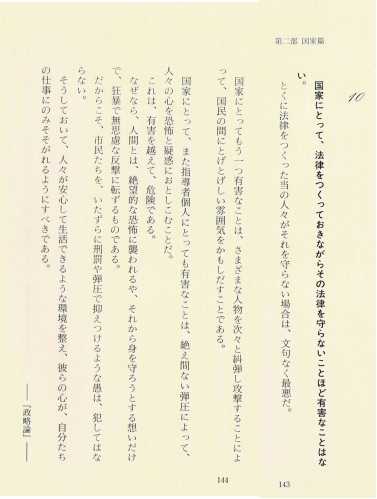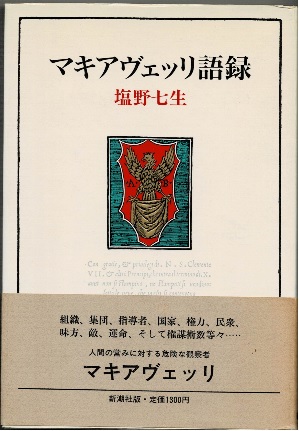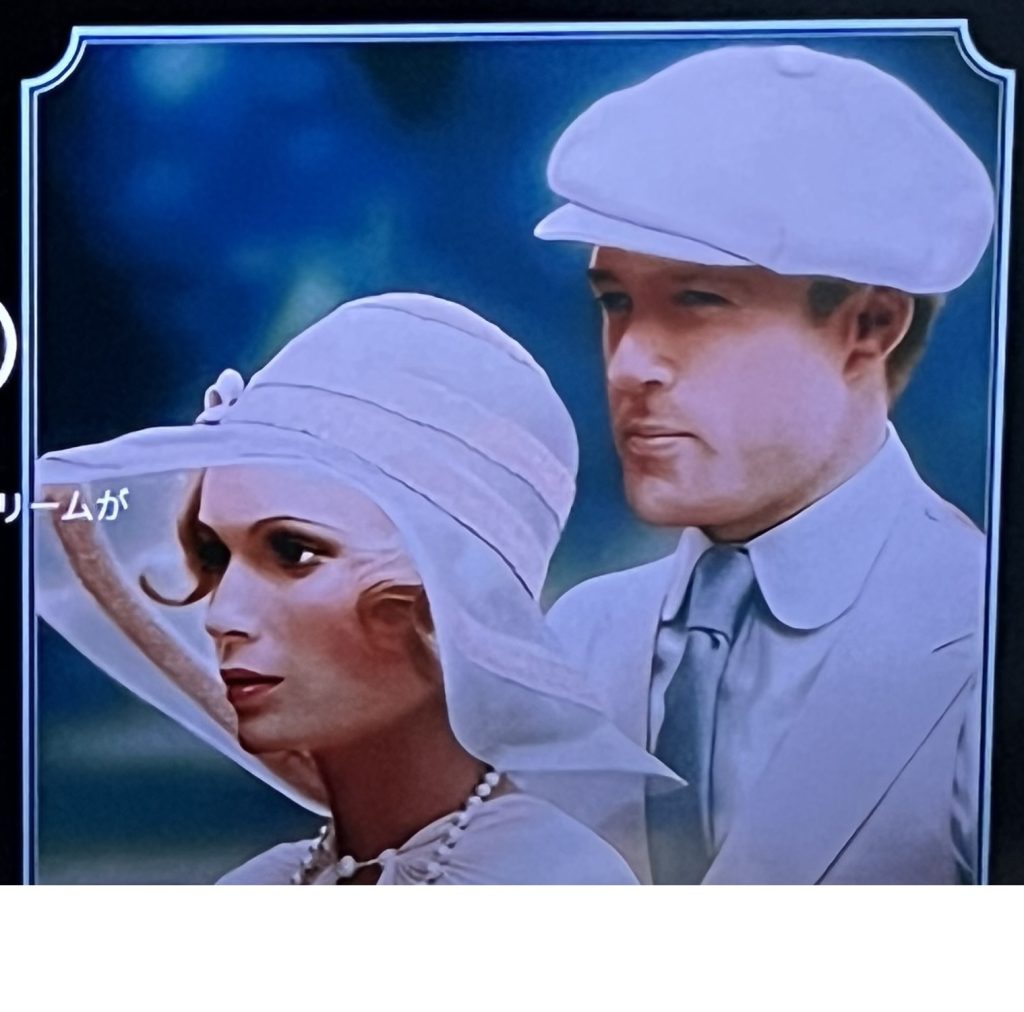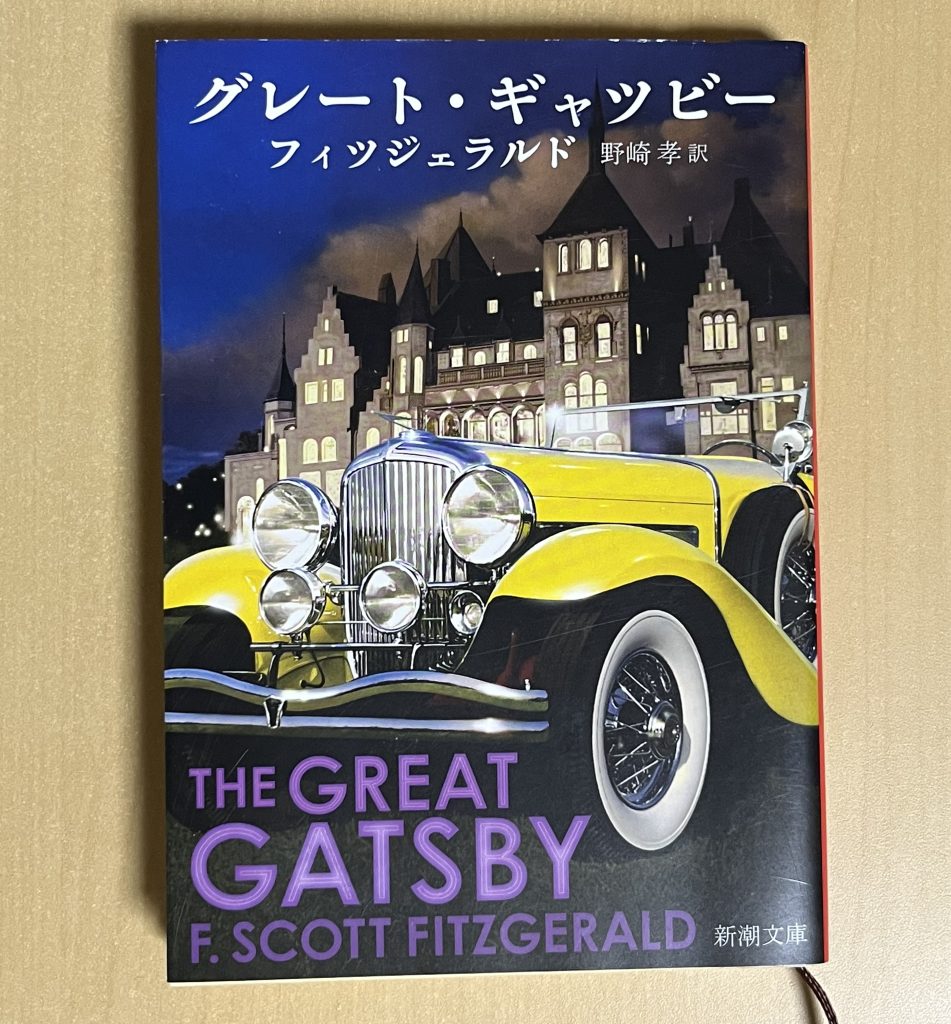先日、ある会合で「よろず支援拠点の伴走支援」について仲間と情報共有を行いました。「よろず支援拠点の伴走支援」とわざわざ断りを入れる理由は、現在国の勧めで色々な中小企業支援機関(商工会、商工会議所、信用保証協会、金融機関、認定支援機関、中小企業活性化協議会などなど)が「伴走支援(中小企業、小規模事業者、個人事業者に対して寄り添った形での支援)」をやっており、それぞれ微妙にやっていることが異なるためです。異なること自体は問題ではなく、色々な伴走の仕方があってしかるべし、とされているようです。
それはそれとして、私の所属する富山県よろず支援拠点(勤務は週2日ほどですが)では、令和3年からエドガー・シャイン教授の唱える「レベル2」の関係でのコンサルティングを志向してきました。これはコンサルティングが「答を教える」という従来のスタイルでは通用しないことが発生する時代になり、これまでとは異なるやり方をしていかなければならなくなったという研究結果から出てきた一つのあり方を提示したものです。もちろん「答を教える」ことで解決する課題も相変わらずありますので、これまでのコンサルティングを全否定するものではありません。
クライアントとコンサルタントの「レベル2の間柄」とは何か。シャイン教授はこんな感じの説明をしてくれています。曰く、「固有の存在として認知」「たまに会う友人」「次の3点で通常より深い・・・①交わした約束を互いに守る、②相手を傷つけたり相手が努力を傾けたりしていることをけなしたりしないと合意する、③嘘をついたり仕事に関わる情報を隠したりしないことに合意する」・・・令和4年の春によろず支援拠点の全国本部から提示された伴走支援のガイドラインにも、このシャイン教授の考え方に基づいて仕事をするように、とされていました。
さてそこで改めてふと思い出したことが『徒然草』でした。第百十七段に以下のようなことが書いてあります。以前も投稿したかも知れませんが・・・「友とするに悪き者、七つあり。一つには、高く、やんごとなき人。二つには、若き人。三つには、病なく、身強き人。四つには、酒を好む人。五つには、たけく、勇める兵、六つには、虚言する人。七つには、欲深き人。よき友、三つあり。一つには、物くるる友。二つには、医師。三つには、知恵ある友。」
と、これだけの文章ですが、まず、自分自身「友とするに悪き者」に該当する要素がいくつかあり、この時点で汗顔の至りではありますが、それを踏み越えて、「よき友」に進ませていただきます。私たちコンサルタントは、エドガー・シャインの警句を待つまでもなく、この「よき友」を目指していかなければならないのではないかと思うわけです。ま、その中でも「物くるる友」はシャインの区分では恐らく「レベル3」の親友などに当たるような気がします。コンサルタントがここまでやると、不特定多数の相談者への対応が困難になります。また「医師」は「レベル1」の技術的課題を回答する専門家になるのではないかと思います。もちろん「医師」も「レベル2」の関係を構築することが望ましいと思いますし、ある意味コンサルタントは経営の「専門医」たるべし、とも言われていますので。そうしたことに加え、私たちが目指すべきは「知恵ある友」になれるよう、人間的な面、知識や経験の面など、日々研鑽を続けていくことが大事ではないかなと、2年ぶりによろず支援拠点の通常支援担当に戻って、改めて感じている今日この頃です。