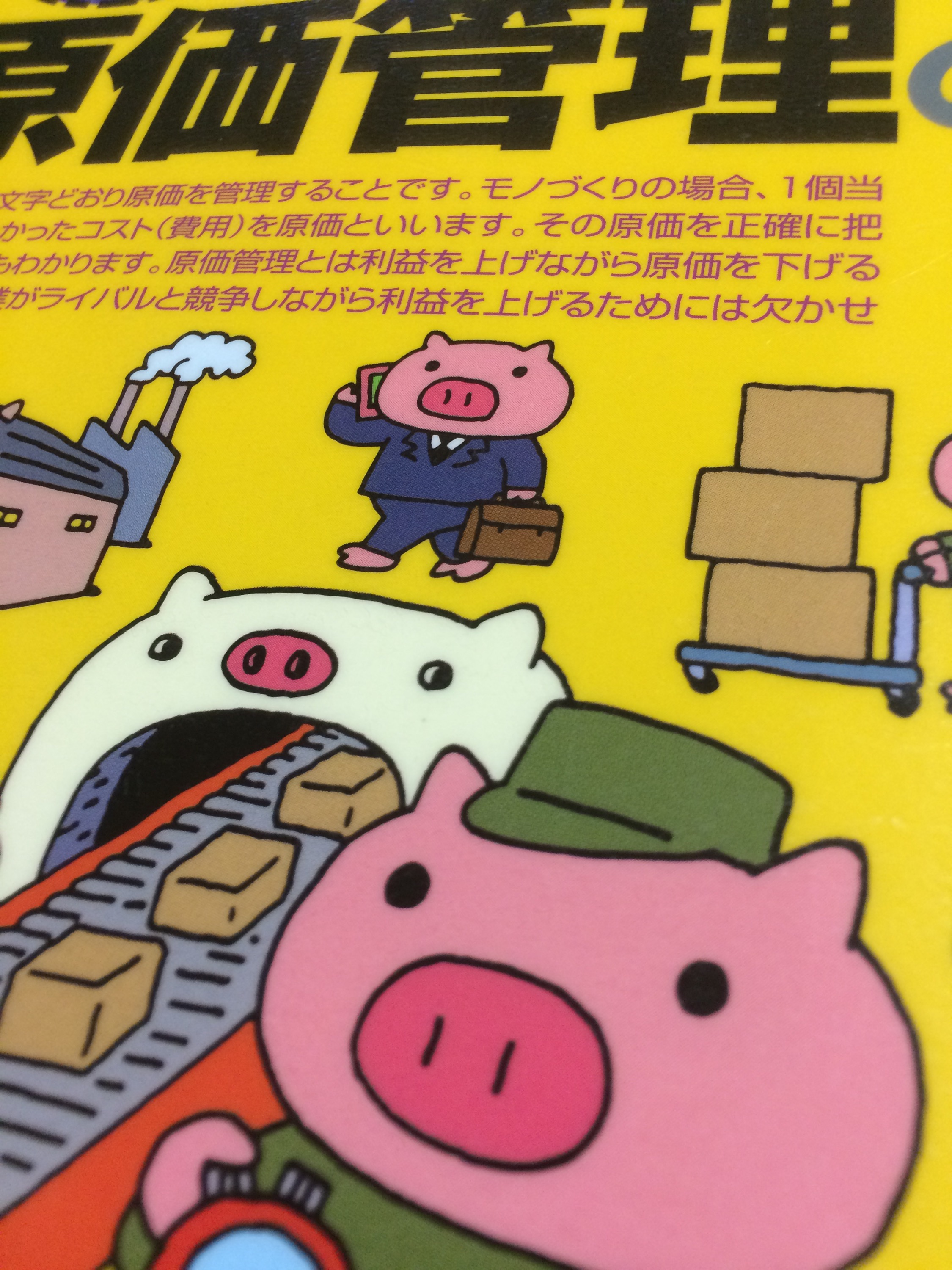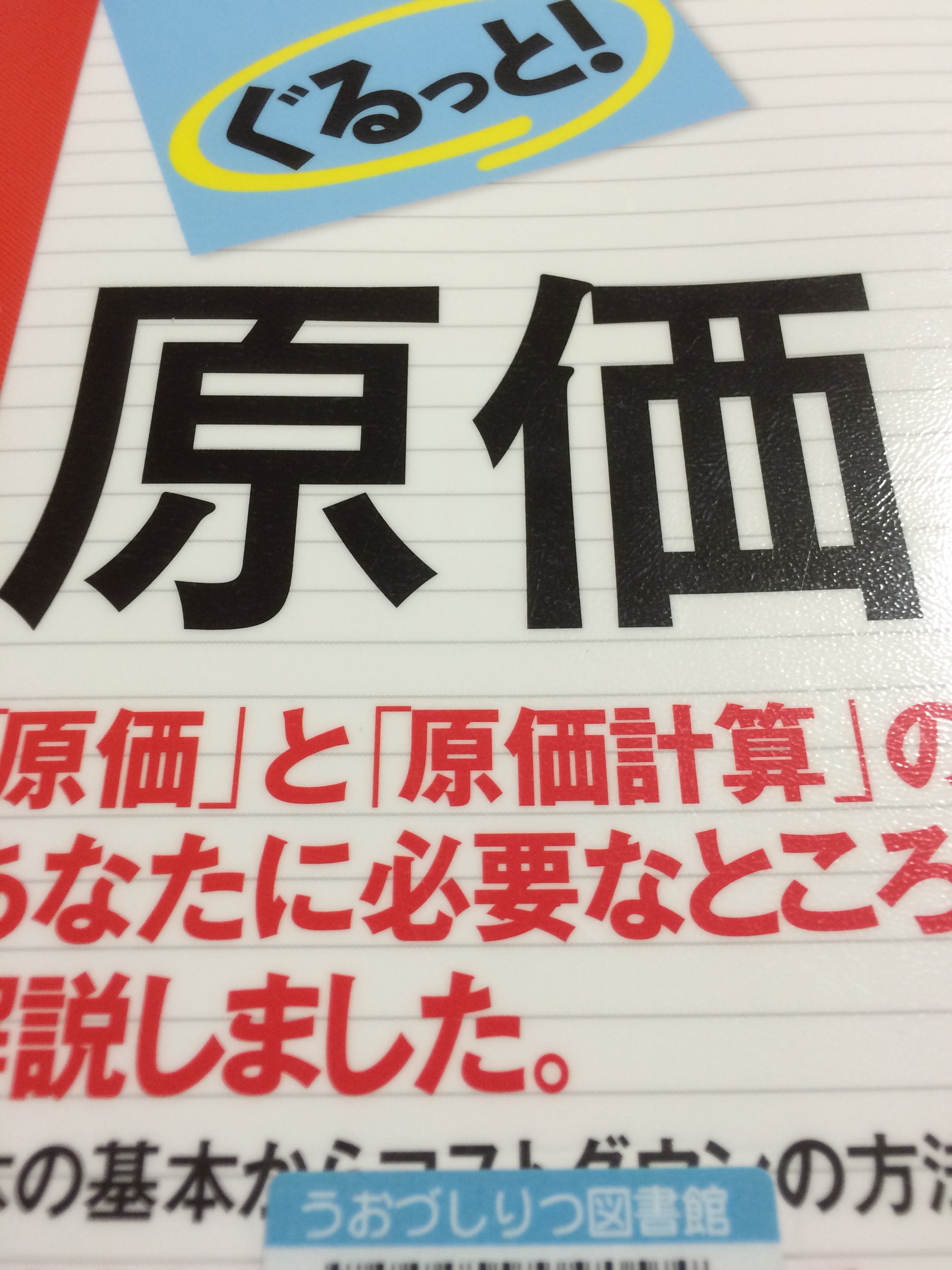「ヒヤリハット」という言葉はよく耳にされると思います。
1件の大きな事故や災害の背景には29件の軽微な事故や災害があり、さらにその背景には300件のヒヤリとしたことやハッとしたことがあるので、ヒヤリハットは重大事故の温床となるのでそういう細かなことも共有したり注意したりしましょう、というあのヒヤリハットです。世間では「ハインリッヒの法則」ということでも知られていますね。
そのためヒヤリハットは危険予知などに活用されるのですが、今回は似て非なる「ニヤリホット」という言葉です。
今日の日経新聞に載っていました。
介護現場での出来事。足元のおぼつかない高齢者が車いすから一人で立ち上がろうとすると、転倒の危険があり、これはヒヤリハット事例として介護現場では情報共有されるのが一般的だそうです。
しかしある職場では、一人で立ち上がろうとする、すなわち自立歩行への意思と努力の表れであり、喜ばしいことだ、と捉え、「ニッコリ」笑って(もちろん注意しつつ見守りながら、でしょうが)、今までよりも介護度が改善するので「ほっと」する事例という捉え方をしたそうです。
物事の負の側面だと思われていたことが、見方を変えれば正の側面になりうる、という好例だと思い紹介させていただきました。
他の仕事や人の見方でも応用できそうな気がします。
「ニヤリホット」・・・いい造語だなと思います。