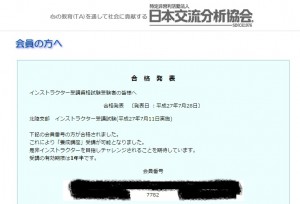魚津市にある認定支援機関のアシステム税理士法人さん。
3年前からこの税理士法人さんが主催する創業スクールで講師をさせていただいています。
この創業スクールは、中小企業庁が、全国各地で実施される創業支援講座で一定の要件を満たすカリキュラムを「認定創業スクール」として認定し、創業希望者の基本的知識の習得からビジネスプランの策定まで支援する、というものです。
平成27年に第1回を開催され、私は第2回の平成28年からお手伝いをさせていただいております。
昨年の第3回からは、通常の講義時間だけではなく、講義終了後に個別相談の時間を設け、受講者の方々の疑問点や相談への対応も柔軟に行っています。それによって、講義を聴くだけでは十分にわからなかった点をしっかり理解していただいたり、ご自分の構想している事業についての深掘りなどを一緒に考えたりしています。
この8月18日(土)に第4回が開講されますが、市町村の特定創業支援事業の対象地域が新川地域に留まらず、富山市も対象となったこともあり、「にいかわ創業スクール」から「とやま創業スクール」と名称が一新されました。新たな講師も加わり、パワーアップして創業希望者の方へのサポートをしていきたいと願っています。
「足取り」カテゴリーアーカイブ
独立から丸三年、日々新たに、これからも
経営コンサルタントとして独立開業して今日で丸三年を過ぎ、四年目に入りました。
この間、大変多くの方にお声をかけていただき、助けていただきました。
途中病院通いの時期や父の死などもありましたが、先輩や友人・知人・お客様・医師・薬師など多くの皆様の支えのおかげでなんとか生きてこられました。改めてここで感謝を申し上げます。ありがとうございます。
三年前の今日、独立したことをフェイスブックに投稿した時に、沢山の方から励ましの言葉をいただきました。
その中の一つに、高校時代の同級生から「一人では生きられないことを肝に銘じておけ」というのがありました。
慢心を戒める忠告として心に響きました。
振り返ってみると、本当にそうだなと心から感じ入っています。
四年目のスタートに際して、改めて自分の社会人スタートの時の社長であった真藤恒さんの著書をひもときました。
(思えば、ことあるごとにこの本を繰り返し開いていることに気がつきました)
200ページに満たない薄い本ですが、昭和50年代末から60年の電電公社民営化に至る期間、真藤さんがどのように私たち従業員の意識を変え、電電公社をたくましい民間会社に生まれ変わらせ、日本が高度情報社会へ進んでいけるように寄与しようとしておられたかが具体例とともにふんだんに記載されており、今日のNTTの基本的な行動指針がこの人によって埋め込まれているなあということを、何度読み返しても感じます。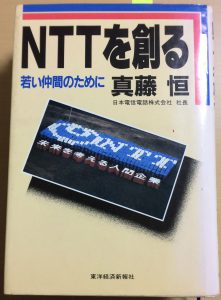
謙虚であれ、ということをこの本の中でも何か所かにわたり、真藤さんは書いています。
<人間というものは、一人で生きられるものではなく、お互い気心の合ったものの仲間の信頼感が基礎になって、助け合いながら、ともに成長することのできる動物だと思う。闘争心も使いようによってはよい面もあるが、その立場を押し通すと、世の中に安住の場所は狭くなるばかりである。>
今改めてこのことを肝に銘じて、これからも企業の経営者やそこで働く人たちのより良い今日・明日のため、伴走これ努めて参りたいと思います。
アセッサー養成研修を受講して
先週一週間に亘って、ヒューマンアセスメントのやり方を学ぶ「アセッサー養成研修」という研修を受講しました。
元々は諜報機関などで受験者の適否を見極める手法の一部として開発されたもののようですが、日本では任用や育成など人材開発系の方法論として導入されたようです。
一週間ぶっ通しの研修は随分久しぶりのことでかなり疲れました。
ヒューマンアセスメントは、個人の潜在能力・資質が、観察しやすい行動として外面に表れる状況を、心理学的に設計された数種類の演習課題を使って作り出し、一定の行動観察技法に基づいて、観察・記録・評定する職務適正の評価技法のことです。ある職務に登用する前などに、その人物がその職務に対する適性があるのか、不足する能力は何かなどを、演習(疑似体験)を通して、客観的に事前評価する手法です。職務への適性やその職務に必要な能力開発を目的としたものであり、人物を評価するものではありません。
ヒューマンアセスメントの対象規模としては、色んなことを全部やらなければならない個人事業者や中小企業の社員さんを対象とするより、少し大きめの組織で活用することが多いようで。人物評価ではないとは言え、アセスメントをする人が心しておかなければならないことは、そこで出した評定の結果が対象者の人生を左右することもあるということです。見る側も人間である以上、個人個人の経験や感覚はまちまちなので、同じ人の行動を観察しても、異なるバイアスがかかって対象者を見てしまいがちです。しかしプロはそのバイアスを極力少なくするように自分を無にして淡々と人の言動を見る訓練を積んでいるとのことで、一週間の研修を受けただけの私はその域にはすぐには達しませんが、今後修練を積んでいきたいと思っています。
人への関心が強く、組織の力を高めるためには構成員の目的認識の共有や一人ひとりの協働意識が大切だ、と思っている私は、これまでも人と人とのコミュニケーションをより良好にするための心理学である交流分析や、チームでの仕事を効果的に実施するアナログ・コミュニケーション(インパクト・コンサルティング㈱の手法)を学んできました。今回さらに新しい知見を得ることができましたので、これらを活用して、今後さらに企業などの組織力強化のお役に立てればと思っています。
独立後、NTT関連の初仕事
先日久しぶりに大阪に行ってきました。
10年以上前NTTラーニングシステムズという会社に出向していた際お世話になった、あるコンサルタントの方からお声をかけていただいたのがきっかけでした。
仕事の内容はNTTグループ企業の営業担当者向け研修において、サブ講師(サブサブ講師かな)を務めるもので、ロールプレイイングやグループディスカッションのお手伝いをするものです。
通信業界を離れて9年以上経ちますが、NTTグループが顧客企業に提供するサービスの根本は変わっておらず、受講者の方々が話しておられる言葉が理解できたのがまず嬉しかったです。もちろん事前にサービスメニューの知識をネットで調べて仕込んでは行ったものの、10年ひと昔と言いますから、話についていけない恐れも十分にありました。言葉が理解できるかどうかはその後の会話に入り込めるかどうかという極めて大事な入口でしたので、ここで一安心。
研修の詳しい中身は書けませんが、ある営業の技法を学んで、練習するというものです。この技法は20年ほど前に私も学んだもので、その後も折に触れ活用したり紹介したりしてきたので、違和感なく参加できました。
技法と並行して受講者の方々に深く学んでいただいたことは、お客様の課題をしっかり把握するということだったように思います。
お客様の話を聞いている際に、こちらが仮説を持って尋ねたことが必ずしもお客様が問題だと捉えているわけではなく、尋ねたことにはさらっと答えられて他の話題に移ったり、お客様自ら別の話題を出されたりすることも往々にしてあります。
その場合、お客様が自ら語っていることに焦点を当て(営業担当が立てた仮説にこだわらず)、仮にそれが真の問題でなかったとしても一旦はよく話を聴き、さらに表層的な話で終わらずに深堀することで課題をより具体化させること(できれば目で見て共有するのが理想)が大事だと思います。もちろんお客様が語っていることが真に危険な問題ではなく、他により重要な危険が迫っている(と営業担当が思う)場合は、例示などをして気付いてもらうよう示唆してみることも大切です。
課題は必ずしも一つではない。むしろ複数存在していることが結構あります。それらをなるべく具体的に(ビジュアルで)双方が認識できるようにして、それが自然体で進んだ場合の影響を、数値や従業員の心理面などを考えながら、着手すべきものの優先度や重要度をお客様と擦り合わせる。・・・とここまで書いてきて、これは営業だけではなく経営相談やコンサルでも同じだなあと、今自分がさせていただいている仕事との共通点があることに気付きました。
私には、24年間お世話になったNTTの社員さんたちに、人材育成やコミュニケーションレベル向上のお手伝いをしたいという夢があります。今回の仕事はその大切な第一歩であり自分の知見が通用するかどうかの試金石でもあると考えて参加させていただきました。プログラムやメイン講師が素晴らしかったこともあり、思った以上にすんなりと入り込めたような気がします。ありがとうございました。
2期にわたる大学での講義を終えて
先日も書きましたが、ご縁で富山国際大学という大学で「情報社会論」という科目を受け持たせていただきました。
平成27年度の後期と28年度の後期の2期、非常勤講師という立場での対応でした。
受講者は各年度約50名ずつ。
それぞれ15回の授業と期末試験の全16工程。
初年度は依頼をいただいてから開始まであまり時間がなく、前任の方の授業構成(シラバスっていうんだそうです)をなぞって取り組み、2回目の今回は前回のものを利活用しつつ最新の動向なども含め、構成を全体的に見直しました。
全15回のカリキュラムは次のとおりです。
第1回 オリエンテーション、情報社会論序論
第2回 人類の歴史と情報革命、コンピュータの登場
第3回 「情報システム」という考え方 ~OAからSISへ:企業情報システム、国家レベルの情報システム、EUCとパソコン~
第4回 情報と通信の融合的発展:ニューメディアからインターネットへ ~通信プロトコル、標準化、TCP/IP~
第5回 経済社会とIT その1 ~私たちの生活に直結しているIT、POS、カード、家庭や労働とIT~
第6回 経済社会とIT その2 ~IoT、ビッグデータ、知識労働者~
第7回 ネットワーク社会の光と影 その1 ユビキタスコンピューティング社会、Web2.0からWeb4.0へ~
第8回 ネットワーク社会の光と影 その2 ~監視社会、情報犯罪、情報セキュリティ~
第9回 メディアの変容、口コミとデマと流言飛語 ~瓦版からTwitterまで~
第10回 情報社会の倫理と情報リテラシー
第11回 情報社会を支える法、国の情報戦略、情報公開と情報保護
第12回 IT産業の発展と今日のIT業界における覇権争い ~Google、Apple、Amazon、Facebook、他~
第13回 諸外国のIT化動向
第14回 これからの情報社会を考えるためのキーテクノロジーズ ~電子商取引、電子マネー、クラウド、AIとロボット、そして人間はどこへ?~
第15回 まとめとふりかえり
作成したパワポの枚数は千枚以上。配布した分だけだと約600枚になります。
もしも次年度もあれば、これにまた最新情報を加えたり深堀すべきものを付加したり古いものを廃棄したりという更新をかけて臨むつもりでした。
が、次年度この授業は、本来の姿である大学の専任教員の方が対応されることになったので、私の役割は終了しました。
お話をいただいた時に相談した師(元・同大学の教授)から、「人に教えるテーマとは、実は自分が学ばなければならないことなのだよ」と言われ、豁然と理解させられた覚えがあります。
確かに、この2期間学生の皆さんに伝えるために、自分の中で一つの科目についての体系・骨格が形作られたような気がします。
もちろんこの分野はドッグイヤー、ラットイヤーなどと言われるように日々激しく変化し、主流になっていくもの・いつの間にか消えていくものなど目を見開いて世の中の動向を見ていなければならず、情報が体系化されたとしてもその瞬間から陳腐化していきますので、じきに使い物にはならなくなるネタも沢山あると思います。
ではありますが、昭和59年に電電公社に就職してから歩んできた自分の情報通信業界での社会人生活を振り返りつつ、最先端の情報社会の動向などを学んで90分一コマの授業を15回分に整理できたことは大変有意義な時間だったし、色々なことが体系的に整理できて、とても勉強になったことは間違いありません。
またNTTの研修センタで社内研修の講師をさせていただいた経験も、この大学の授業を行う上で大いに生かすことができました。
どこで何がどうつながるか、ほんとにわからないもので、私を育んでくれた会社、先輩・同僚・上司、この話を私に紹介して下さった中小企業診断士の大先輩、私でいいよと仰って下さった大学の教授の方々、などなど多くの人に感謝感謝です。
授業の日は大体晴れの日が多かったですが、最終日だけは雪が積もりました。
いい経験をさせていただき、本当にありがとうございました。
交流分析士インストラクターデビュー戦
本日、おかげさまで交流分析入門講座を開催することができました。
インストラクターの資格取得を目指して丸三年。
最初は色んなことがブツ切りに見えてなんだかよくわかりませんでしたが、諸先輩のお導きのおかげで、学習を進めるにつれ少しずつバラバラの知識が結びついて、実生活や実社会にも活用できるようになってきたような気がします。
今日は、魚津商工会議所さんでの初インストラクターを務めさせていただきました。
なにぶん駆け出しですので、これからさらに学習を進めて行かねばと思っています。
そんな私にとって、人様に交流分析のことをお伝えすることができるのは、何よりも自分自身の勉強になります。
今日一緒に登壇してもらった先輩インストラクターの話の内容、事前に準備する時の自身の学習、参加された方々からの質問、一つひとつが自分にとって新鮮な気づきになります。
将来的には若い方々に早い時期に学んでいただき、自分の人生のかじ取りを自信をもって行っていただけるよう貢献したいと思いますし、企業などの組織においても幹部と従業員の方々に学んでいただき、思いやりと正のエネルギーに満ちたチーム作りができるようお手伝いしていきたいと思っています。
コミュニケーション研修(交流分析入門講座)の開催
経営コンサルタントとして私が目指している「標榜科目」(お医者さんじゃありませんが)は、ITと財務とコミュニケーションの3つの分野です。
これまでの経験を活かそうと思うと、そういうことになります。
そのうちコミュニケーションについては、何か一つ体系的なものを学ばなくてはと考え、数年前から交流分析という心理学を学んできました。
その結果、今年の1月にインストラクター資格をいただくことができました。
交流分析は極めて実践的で日常生活に活用できるところが、学者さんたちだけに閉じた学問ではない特徴です。
そのため活用範囲はとても広く、私は企業経営の助言や組織内のコミュニケーション改善にも役立てて行きたいと考えています。
インストラクター資格をいただいたからには、人様の前でこの素晴らしい実践的な知恵と方法論をお伝えしていきたいと思います。
ということで、まずはこの5月22日(日)に先輩インストラクターと一緒に初回の入門講座を開催します。
・期 日:平成28年5月22日(日)午後1時半~4時
・場 所:魚津市釈迦堂1-12-18 魚津商工会議所5階研修室
・参加費:1,000円
・申 込:日本交流分析協会北陸支部のHP(http://www.ta-hokuriku.jp/kaiin.html)から申込書をダウンロードして必要事項記入の上、申込み。
富山県よろず支援拠点「にいかわサテライト」他開設のお知らせ
現在私が主な仕事場にさせていただいている「富山県よろず支援拠点」の新川地域の出張拠点「にいかわサテライト」が5月17日(火)午後、魚津商工会議所内に開設されることになりました。(6月以降は毎月第二火曜日の午後の開設です)
関係者の皆様、心から感謝申し上げます。
「よろず支援拠点」は、国が全国に設置した経営相談所です。中小企業・小規模事業者の経営者、創業予定者の方々からの、売上拡大、商品開発、後継者や人材育成、経営改善など経営上のあらゆるシーンで起きてくる様々な悩みごとのご相談に対応しています。必要に応じて、商工会・商工会議所、金融機関、その他の公的機関とも連携・連絡を取りながら、課題解決に向けて対応しています。よろず支援拠点へのご相談は何度ご利用されても無料です。
富山まではちょっと遠いなあとお思いの新川方面の方、お近くに参りますので是非ご利用下さい。
なお初回記念として、「よろず支援拠点」の原型を作り、今も静岡を拠点に企業支援活動を展開している<カリスマ経営支援家>小出宗昭氏の無料特別セミナーを5月17日(火)午後1時から開催します。
公的機関を利用して経営改善や売上増大や新製品開発などに取り組みたいとお考えの経営者の方々、独立起業をお考えの方々、経営支援のお仕事に関係されている支援機関や金融機関などの方々、一聴の価値ありです。
セミナーは定員80名・先着順です。ご関心のある方は、富山県よろず支援拠点へFAXにてお申し込み下さい。お問合せ先は下の写真のとおりです。私宛に電話やメールでご連絡いただいても結構です。よろずにいかわサテライト_セミナー申込書(↑「平成28年6月より開設」と書いてありますが、初回は上記のとおり5月17日(火)です。)
なお、にいかわサテライトに続いて、6月15日(水)には「なんとサテライト」(福野商工会内に)、6月21日(火)には「たかおかサテライト」(高岡商工会議所内に)がそれぞれ開設されますので、南砺地域・高岡地域の方はそれぞれお近くのサテライトも是非ご利用下さい。
インプットもしていかなければ、の日でした。
今日の午前中は富山県民会館で行われた「NTT WEST COLLECTION 2015」という展示会に参加。
大先輩のIさんからご案内をいただき参上つかまつりました。
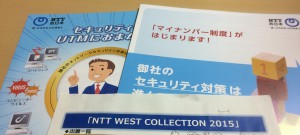 時世に合わせてマイナンバー関連セキュリティのソリューションが中心でした。友人のK氏にアテンドしてもらい(もったいなや)、一通り見て回り説明を聞かせてもらいました。
時世に合わせてマイナンバー関連セキュリティのソリューションが中心でした。友人のK氏にアテンドしてもらい(もったいなや)、一通り見て回り説明を聞かせてもらいました。![IMG_3175[1]](http://teamwakuwaku.com/blogdb/wp-content/uploads/2015/10/IMG_31751-e1446113761383-225x300.jpg) IT業界を離れて早7年半経ちますが、娑婆はどんどん複雑かつ高度化していることだけはわかりました。自分の知識不足はともかくとして、旧友やら昔の先輩やらにも沢山お会いできて感謝感謝です。これから「富山県よろず支援拠点」へのマイナンバー関連の相談も増えてくると思いますので、情報収集の一環としても有意義だったのではないかなと感じています。
IT業界を離れて早7年半経ちますが、娑婆はどんどん複雑かつ高度化していることだけはわかりました。自分の知識不足はともかくとして、旧友やら昔の先輩やらにも沢山お会いできて感謝感謝です。これから「富山県よろず支援拠点」へのマイナンバー関連の相談も増えてくると思いますので、情報収集の一環としても有意義だったのではないかなと感じています。
で、午後は中小企業基盤整備機構開催の「経営者保証ガイドラインセミナー」に参加。![IMG_3179[1]](http://teamwakuwaku.com/blogdb/wp-content/uploads/2015/10/IMG_31791-e1446113745683-225x300.jpg) 経営者の過度な保証に頼らずに企業のライフサイクルに取り組みましょうと、一昨年に日本商工会議所や全銀協が公表したガイドラインの周知活動です。どこか変わったのかなと思い、情報収集のつもりで参加したのですが、ガイドライン自体は変わっておらず、まだまだ地域の企業の皆様に対する周知が不十分だということで全国行脚をしているということでした。私にとっては整理された資料と整理された説明を聞くことができ、頭の中がスッキリ整理されたかなという感じです。こちらも感謝感謝。
経営者の過度な保証に頼らずに企業のライフサイクルに取り組みましょうと、一昨年に日本商工会議所や全銀協が公表したガイドラインの周知活動です。どこか変わったのかなと思い、情報収集のつもりで参加したのですが、ガイドライン自体は変わっておらず、まだまだ地域の企業の皆様に対する周知が不十分だということで全国行脚をしているということでした。私にとっては整理された資料と整理された説明を聞くことができ、頭の中がスッキリ整理されたかなという感じです。こちらも感謝感謝。