久しぶりに塩野七生さんの『ローマ人の物語』を読んだ。
というか、数ヶ月の通勤電車の中で、ちょぼちょぼと読み継ぎ、ようやく文庫本一冊読み終えた、ちうのが正しい言い方だ。
今回読み終えたのは『ローマ人の物語 文庫24 賢帝の世紀(上)』である。
ローマの五賢帝といえば、高校生の時に世界史で教わった、ネルヴァ、トラヤヌス、ハドリアヌス、アントニヌス・ピウス、マルクス・アウレリウス・アントニヌスの五人である。
特に今回読んだ24巻はトラヤヌスの巻であり、ローマ史上最大版図を達成した人物として覚えさせられたものだ。
ローマの皇帝はホンマに色々な人がいるものだと、この人の本を読んでいてつくづく思うが、トラヤヌスという人は、大変謹厳実直な人のようだ。
イタリア半島出身ではなく、属州出身としては初めての皇帝だった、からかどうかはわからないが、そういうことが影響したのか、頑張らなくっちゃ!という心の声を塩野さんは聞いたのか、「なんでそんなに頑張ったの? そうよね、属州出身の初めての皇帝だものね」というような投げかけをしておられる。
自慢ったらしいことは言えないが、私も結構(無理すんなよ、と思いつつ)頑張り抜くきらいがあるので、この人の姿勢には共感するところがある。
但し、トラヤヌスはなぜか男色で、女性を避けたらしい。(この点は私とは大いに違う)
妻はいたようだが、子どもはおらず、そのため、皇位継承者には他人のハドリアヌスを選んだということだ。
次のハドリアヌスも男色で、そのため子どもがおらず、そのため皇位継承におけるゴタゴタが起こらなかった、という妙な話である。
そんなことで、次は「文庫の巻の25 ハドリアヌス」の巻である。
次も楽しみだ。(ちょっと読書スピードがゆっくり過ぎるかな)
「読んだ本」カテゴリーアーカイブ
園 善博氏の『本がどんどん読める本』
1.書名 本がどんどん読める本
2.著者名 園 善博
3.出版社 講談社
4.読了日 H21.7.4
5.ポイント
前に読んだポール・シーリーのフォト・リーディングの手法と極めて近い。
やはり、目的を持つこと、全体を眺めること、質問を投げかけて著者と対話するようにして読むこと、パラパラめくること、などがスピード読書術の共通的なやり方なんだなと思った。
<読書の前提>
まず目的を持つこと
達成したときの状態をイメージすること
<読書の進め方>
(1) 目次を読んで何が書いてあるのか想像する。目次を書き出す。
大見出しをまず、全部書き出す。(中見出しや小見出しのスペースを空けておく)
次に中見出しを全部書き出す。(小見出しのスペースを空けておく)
次に小見出しを全部書き出す。
※極力、目次の丸写しではなく、本をめくりながら行う。
(2) プリペアードマインドをセットする。
① その本を読む目的を明確にする。
② どんな知識が学べるか想像する。
③ 本を読んで学習したことでどんな「ごほうび」が得られるか想像し、言葉で表す。
(3) プライミングを行う。
① 目的に関わりそうな単語を「ウォーリーを探せ」の感覚で探すようにざっと見る。
② パラパラ読みを行う。
(4) 複数の質問を設定する。(詳細把握の技法)
① その質問に関するキーワードを頼りに本を読んでいく。(ターゲットリーディング)
② 一つの質問が終わったら、次に二つ目の質問で同じことをしていく。以下同様。
(5) 答を得たら要点をメモしておく。
メモの手順は、(1)のツリー構造と同じように書いていく。
(6) 読み終わったらメモを見ながらブリーフィングを行う。(内容の振り返り)
(参考)エビングハウス曲線を活用した効果的な学習のこと
ベストな復習スケジュール:学習した翌日に1回目、1週間後に2回目、その2週間後に3回目、さらにその1ヵ月後に4回目と、2ヶ月かけて4回の復習をする。
やり方は、ページをめくってポイントだけ読むとか、目次を見て記憶のあやふやな ところだけ読み返すとか、要点メモをチェックするなど、簡単に。
松岡正剛さんの『多読術』
本についての記録を久しぶりに書く。
猛然と読書への意欲が沸いてきた。
ここ数年なかった感覚だ。
とにかく疲れていたから。
それはさておき、松岡正剛氏の『多読術』を読んだ。
松岡正剛氏は私が大学生の頃「遊」という雑誌を編集なさっており、何冊か私も購入して読んだものだ。
値段が高かったので、貧乏学生にはなかなか毎月定期購入というわけにはいかなかったが、大変食欲がそそられる雑誌だった。
前衛的というか、科学と宗教が渾然となっているというか・・・。
私が今でも持っているのは「ジャポネスク」について特集された号だ。
やや思想がかったような印象を受け、この人はちょっと危ない人ではなかろうか、と思っていた。
従って、「遊」は読んだが、松岡氏に近しくなりたいとは思わなかった。
その後の松岡氏の活躍ぶりは言うまでもない。
某巨大通信会社と組んで出版された『情報の歴史』などは、私も購入した。
素晴らしい大作だと思う。
情報の意味を有機的に結び付けてみる、という実験的な試み。面白い。
極めて真面目な常識人であり、読書人なのであろうと思う。
今にして思えば、折角4年間も東京で遊んでいたのだから、一度ぐらい松岡氏のオフィスを訪ねて謦咳に触れてみても良かったかも知れない、とちょっと思う。
さて『多読術』。
松岡氏は、驚異的な読書量の持ち主であることは周知のとおりである。
最近はやりの「速読術」をきっとこの人も心得ているのだろう、と思っていた。
が、さにあらず。
いや、たぶん、読むスピードは間違いなく常人には考えられないくらい早いのだと思うが、いわゆる速読術ではないらしい。
夜中3時まで鉛筆と辞書と地図と年表を傍に置きながら、一生懸命に読んでおられるようだ。
「いちばん心がけたことは、寝ないようにするということ」
これがこの人の驚異的な読書量の基本であるようだ。
「読書というもの、夜に根っこをのばすんです」
なるほど。
言いえて妙。
今の私にはできないが、そのくらいの気合で本に立ち向かわないといかんということだというのがよくわかる。
但し・・・
「読書を神聖なものだとか、有意義なものだとか、特別なものだと思わないほうがいい。読書はもともと多様なものだ」
とも言っておられる。
極端な話、昔竹村健一氏が著書の中で「自分が寝っころがって本を読む。スタイルを気にしていて読めなければ意味がない。読むためには自分の好きな格好で読めば良い」というようなことを書いておられたが、それとまさに共通する。
しかし、まあ、なかば自由人のような竹村氏と、万巻の書物を読んできた松岡正剛氏とが同じような見解を持っていたとは驚きだ。
その他、気に入った箇所を一部抜粋。
「本はすでにテキストが入っているノート」
「(本は、書いたその人が)自分にプレゼンテーションしている」
「本は、リスク、リスペクト(敬意)、リコメンデーション(おすすめ)の3R」
その他その他。
大変ユニークで参考になった。
俄然、読書欲が沸いてきた。
ちょうど先日注文した本6冊も、出張中に届いていた。
さあ、明日から読書も生活の一部にしっかり加えていくぞ。
(肩の力を抜いて、でも片っ端から手当たり次第に)
ドラッカーの遺言
魚津私立図書館で『ドラッカーの遺言』(講談社)という本を借りて読んでいる。
中に「スーパー経営者は恥ずべき存在」という一節がある。
お金持ちの代表とも言うべきJ.P.モルガンというモルガン財閥の創始者が「トップの人間が一般社員の20倍を超える給料を得るようであれば、それは誤った経営である」として、そういう会社にはモルガン氏は投資をしなかった、という話が紹介されている。
スーパー経営者が得る高額な報酬ほど恥ずべきものはない、と断じている。
最近のアメリカでのビッグスリーや金融機関の経営層の巨額ボーナス騒ぎを考えると、モルガンやドラッカーの警告が活かされていないと感じるとともに、巨大金融機関の祖であるモルガンがそういう発言をしていることが意外だった。
ドラッカーはさらに、リーダーを待望してはいけない、リーダーの登場を恐れよ、カリスマは唾棄すべき存在だ、など、みんなもっと勉強して知識を蓄え、たゆまざる変化に対応していきなさい、そうすればリーダーなどに頼らず自分で判断できる、というようなことを書いておられる。
また経営の本質とは「どんな長所を活かし、何をすることで、どれだけの成果を挙げるのか?」であると語っている。
その他その他、まことに示唆に富む本である。
世界一の見識だと思う。亡くなってしまったのは残念だが、この人の考えや提案からはまだまだ学ぶことは多い。
経営者必見! 失敗学のすすめ
10年ほど前に畑村洋太郎という工学系の学者が書かれた『失敗学のすすめ』という本を読んだ。
日本の組織は、失敗した人を袋叩きにするか、臭いものに蓋をするか、的な始末の仕方が多いように思う。
ムラ社会だからか、なあなあにして、なんとなくなかったことにするケースも多い。
そのため、失敗が教訓として生かされない。
旧日本軍(特に陸軍)の上層部もそういう傾向にあったようだ。
作戦で失敗した参謀を、「可愛そうだから」とか「あいつはオレが可愛がったやつだから」とかいう理由で、責任ある部署から離すということをせずに、別の方面へ転勤させ、そこでほとぼりが冷めるまで別の責任ある作戦参謀にしておく、という問題の根絶にならない情実人事などもあったやに書いてある。(『失敗の本質』by戸部良一氏ほか・・・これについては稿を改めて詳述する機会もあるだろう)
一方で、下々の者に対しては徹底した減点主義である。
失敗した者に対しては、失敗したこと自体を責め、それに携わった者の「抜け」を責め、そのついでに怒鳴り散らしながら原因追求をする。
責任追及と原因追求と責めを同時にやるものだから、皆、怒鳴られまいとして、失敗などなかったように振舞うか、過度に問題が小さいように取り繕ってしまう。
そんなだから、失敗が教訓として生かされない。
ああ。
なんというニッポンか。
そんな我が国の「隠し事社会」に科学的にメスを入れたのが、畑村洋太郎氏である。
たまたま昨日上司が「失敗学」というのがあるそうだ、という話をしているのを耳にしたため、家に帰ってから久しぶりに書棚から引っ張り出して読んでみた。
10年前の本なので、多少日焼けの跡があった。
あちこと線を引いたり書き込みがしてあって、へえっ、結構勉強したんだなあと我ながら感心してしまった。
要は、失敗が組織の経験知となるようにPDCAを回せ、そのためには、まず「バカヤロー!!」と怒鳴り散らすのではなく、「なぜそういう失敗が発生したのか、当事者からよく話を聞く、傾聴する」ということが必要だ、処罰はその後で、規則に基づいて行う、というようなことである。
文庫も出ているが、ハードカバーで読んでもいい本である。
特に、最近の中小企業で失敗されるケースには、どんぶり勘定、利益度外視の売上至上主義的経営、というのが多いように思う。
経営者は、誰も責める人がいないので、もしも計画どおりいかない事象が発生したらば、こういう本でも読んで、なぜ失敗したのか、冷静に、客観的に、データを分析するということもやりながら、考える必要があると思う。
大体が直感が当っているのであろうと思うが、それを裏づけ、関係者(たとえば金融機関)にきちっと説明することも求められるし、正しい分析をすれば、正しい課題・正しい対策も、正しく設定できるはずだからである。それが大向こうをうならせ、金融機関からの融資もスムーズに引き出せる、ということにつながるからである。
さて、この本を嚆矢として、世に失敗学ブームが巻き起こったが、畑村氏はその後も色々な事件を題材に著書を出しておられるようである。
ニッポン社会も少しは冷静になって、失敗に対して大人の対応ができる(原因究明と、失敗の責任者を法に照らして処罰する、ということを切り分けて行う)ようになっていかねばならない。
我々40代がそういう社会に作り変えていかなければ、いつまで経っても第二次世界大戦のときのx軍の失敗と同じことを繰り返すことになりかねない。
小室直樹氏曰く、日本社会は構造的には第二次大戦当時となんら変わっていない。
やんぬるかな。
いや、なんとかせねば。
リチャード・クーの本
野村総研のリチャード・クー氏の『日本経済を襲う二つの波』(徳間書店)という本を読んでいる。
今年の6月に出版されたものだが、なかなか面白い。
主張の中の特に重要なポイントは、現在のアメリカ発世界同時不況は「バランスシート不況」であり、これは金融対策だけでは解決しないという点だ。
すなわち、ITバブルがはじけたときに、FRBのグリーンスパン議長が低金利政策をとって貸し出しを増やし、それでもって潜在している住宅バブルを吹き飛ばそうとしたが、企業にとっては自社のバランスシートが傷んでいるために信用力の回復のために借金返済に走り、どんなに低金利になってもお金を借りるという行動にはなりにくい、それよりも必要な支援は企業の自己資本増強であり、すなわち財政出動なのだが、グリーンスパンはそれをしなかったために金利は下がる、住宅価格は下がる、企業は金を借りないので投資に回らない、という負のサイクルに入って行った、そういう中にあって今しなければならないことは、財政出動による銀行や企業への資本注入である、という主張である。
私のような金融音痴にもわかりやすい書き方をしてある。(ここにそのわかりやすさを伝えられない自分がもどかしいが)
で、そういう財政出動論者として、それこそ今度のオバマ政権で財政分野のリーダーになるサマーズ氏や麻生総理の「支援発言」で久しぶりに注目を集めているIMF(世界通貨基金)のストロスカーンという専務理事にエールを送っておられる。
これまで竹村健一や長谷川慶太郎、大前研一などの議論を見てきたが、今回のリチャード・クー氏の本は大変なものだ。
大変わかりやすく論旨も通っていて、歴史認識もしっかりしている。
10年以上前から存在は聞いていたが、こんなにすごい人だとは思わなかった。
この人にかかっては、ポール・クルーグマン教授もバーナンキ現FRB議長も、所詮学者であり、経済の実際の中で有効な手を打てる識見はない、と両断される。
まるでサマーズさんの再登板を予見していたかのような感じで、ビックリしている。
それともう一つ面白い点。
金融庁の検査官の人数を10倍に増やせ、と主張し、通ったらしいのだが、その後の金融庁の肥大ぶり、そして銀行への締め付け、それの結果として表れる中小企業への貸し渋りなどのしわ寄せ・・・。
この人は、日本の役人が自己肥大化という習性を持ち、権限を持たせるとそれに乗じてどんどん大きくなり、保護しなければならない対象のことよりも自分たちの権益拡大に走るということへの理解がなかったため、金融庁を大きくせよと言った結果、実際に大きくなったまでは良かったのだが、その後の彼らの無見識ぶり(資本として銀行に注入したお金を「返すのが当然」と発言していた幹部がいるらしい・・・資本というのは返すべき「融資」ではないにも関わらず、である)、暴走・暴言ぶりにあきれかえっている。
資本として注入した公的資金を「返せ」と言われると、銀行は資本勘定からはずさなくてはならなくなり、その結果銀行の自己資本比率が下がる。自己資本比率が下がると、それ以上低下しないように、返済の困難だと思われる企業には融資しなくなる。それが貸し渋りと言われる。つまり、助けなくてはならない中小企業への金融の道を、金融庁が銀行を締めることによって、自ら閉ざしているというわけだ。
曰く「権力をふりかざし要りもしない発言を繰り返し、箸の上げ下げにまで口を出し、銀行経営に干渉した。これらの金融庁の余計な干渉も、結局のところ、銀行の自然な回復をかなり遅らせることになってしまった」
ああ、すごくわかりやすい。
ありがとう、リチャード・クーさん。
当分、この人の発言や著書から目を話せないぞ、と。
今日は自宅で仕事の日・・・のはずだったが
『本当に頭が良くなる1分間勉強法』 (中経出版、石井貴士著)という本を読んだ。
2ヶ月ほど前に勉強したフォト・リーディングと極めて似たやり方だ。
早速子供たちに教えた。
自分もやってみようと思っている。
コツは、短時間で何度も、である。
それも1ページを1秒間で、読まずにぼやっと感じるように見る、である。
最近関心を持っている新しい「記憶術」もそうなのだが、脳のパターン認識力や、目の周辺視野の力や、直感の力などを利用するものらしい。
色彩を使うという点では、マインドマップ手法でも見られるやり方だ。
ただし、1分間という短時間で、初めて接する知識までをも即座に理解して記憶して定着させるという魔法ではない。
ある程度理解したものを短時間で重要ポイントを見つける(感じる)という手法だ。(と思う)
そういう意味では、子供たちの受験勉強などに威力を発揮するものなのだろうが、私の溜まっている読書にも活用したいと思っている。
今後の読書生活や次の資格試験などに活用していこうと思う。
仕事が溜まっているが、夜までまだ数時間あるので、これからやろうかな。(やんなきゃな)
塩野七生『ローマ人の物語』のこと
塩野七生さんの『ローマ人の物語』を断続的にゆっくりと読んでいる。
今は文庫本の21「危機と克服」の(上)を読んでいるところだ。
アウグストゥス、ティベリウスというきっちりした皇帝の後、カリグラ、クラウディウス、ネロと続き、若気の至りのネロが混乱を招いて死んでしまった後、ガルバ、オトー、ヴィテリウスという聞いたこともないような軍人皇帝が1年の間に入れ替わり立ち代り国家の混乱の中、次々に就任しては殺されていくというややこしい時代だ。
ややこしく、さらにまた、カエサルのような素敵さも天才性もなく、ネロのような稚気ではあるが魅力的なところもないような人物たちのようである。
塩野七生さんは叙述家であり、立派な歴史家でもあると思うので、批判するつもりは全くないが、こういう混乱期の魅力のないリーダーたちをどういう心境で描いていたのだろうか、とふと立ち止まって考えてしまう。
面白くないというわけではないが、なんとなく淡々と叙述が進められているような気がして、たぶん塩野七生さんも面白くないなあと思いながら筆を進められたのではないかなあと忖度してしまう。
彼女にとって血沸き肉踊る心持ちで描いていたであろう人物たちは、グラックス兄弟やハンニバルであり、スキピオ・アフリカヌスであり、スッラやマリウスであり、そしてカエサルでありアウグストゥスたちであったろう。
それらの激動の人物と比べると、なんとも小粒の面白みに欠ける人たちを、塩野さんはどういう思いで書いていたのかなあと思う。
だからこそ、この時代の皇帝たちを描きながら、つい、カエサルだったらどうしたとか、アウグストゥスはこうしたとかいうふうに、すぐ筆が飛んじゃうんではなかろうか。
などと考えつつも、この人の描くローマとローマ人の歴史に今日も耽溺している。
面白い。
読んでいる本 塩野七生『ローマ人の物語 文庫版17~20』
塩野七生さんの『ローマ人の物語』。
文庫本でちまちまと読ませていただいている。
高坂正堯さんの『文明が衰亡するとき』という素晴らしい本がある。
それと比較をするのは適切ではないと思う。
なぜならば、それぞれ、範囲もボリュームも著者の専門領域も異なるし、さらには著者の関心のありかすら別である可能性があるからだ。
ではあるが、高坂氏の本と「同じくらい」素晴らしいと思って読んでいる。
現在ようやく「悪名高き皇帝たち」を読み終えたところだ。
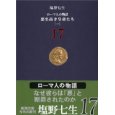
オクタビアヌスの後のティベリウス、カリグラ、クラウディウス、ネロという4人の皇帝をめぐる物語である。
カリグラやネロは若くして権力者になってしまい、それが元でものごとがよく見えなかったのではないか、という気がする。
治める、ということは、自分が好きにする、ということではなく、人々がいかに満足を得られるような演出をするか、ということかも知れないなとこの巻を読んで思った。
そういう演出を政治というのかも知れず、そうなると若さというのは、熱狂で人々から迎えられていい調子になっているときはいいが、ひとたび世の中の調子がおかしくなると、どういう方向に持っていくべきかとか、一時的にみんなの不満をそらすためにどういう手を打っておいたらいいかとか、誰を取り組みのリーダーにすべきかというような調整的な能力が必要で、それは若い君主にはなかなか求めることが困難なのではないかなと思う。
明確な意思があって、それをやり続ける意思があって、実行できる体力と脳みそがある。そして人々をして主役だと思わせるような演出ができる。
これが世の中を引っ張っていき、かつ人々から慕われながら仕事をしていくリーダーに求められる条件ではなかろうか。
思慮の浅さ、という点では、いくつかの善政もしたのだろうけれども、やはりカリグラやネロに及第点は与えられないだろう。
そんなことを思った。
大前研一の本を読んで
大前研一の『50代からの選択―ビジネスマンは人生の後半にどう備えるべきか』 (集英社文庫)という本を立ち読みでパラパラと読んだ。
その中に、50代からの人生は40代後半で考え、準備していかなくてはならないという主旨のことが書いてあった。
私も今46歳。
このままあと4年が経過すれば給与はいやでも3割カットとなる。これは、そういう会社の制度なのでしょうがない。
そうして54歳ぐらいで肩を叩かれ、関連会社に行き、今よりも割に合わない仕事をテクテクと続けるか、まだ売れる可能性のある今この時期に自分の力を信じて新たな世界に飛び出していくか、大前研一の本を読むと、今だからこそできることをすべきではないか、60代になってから何かを継続しようと思っても、大概は何もできないと書かれてあった。
確かにそうだろうな。
何かひとつのことを成し遂げるとしても、60歳からではちょっと遅すぎるような気がする。やはり50代でのスタートだろう。そのためには40代からスタートを切っておかなくては間に合わない。今が旬だ、今がチャンスだ、と自分に言い聞かせている。
