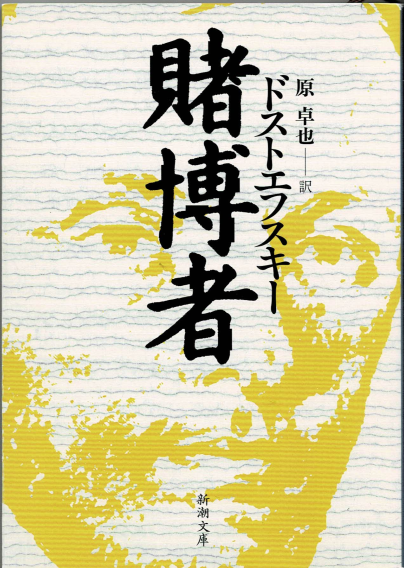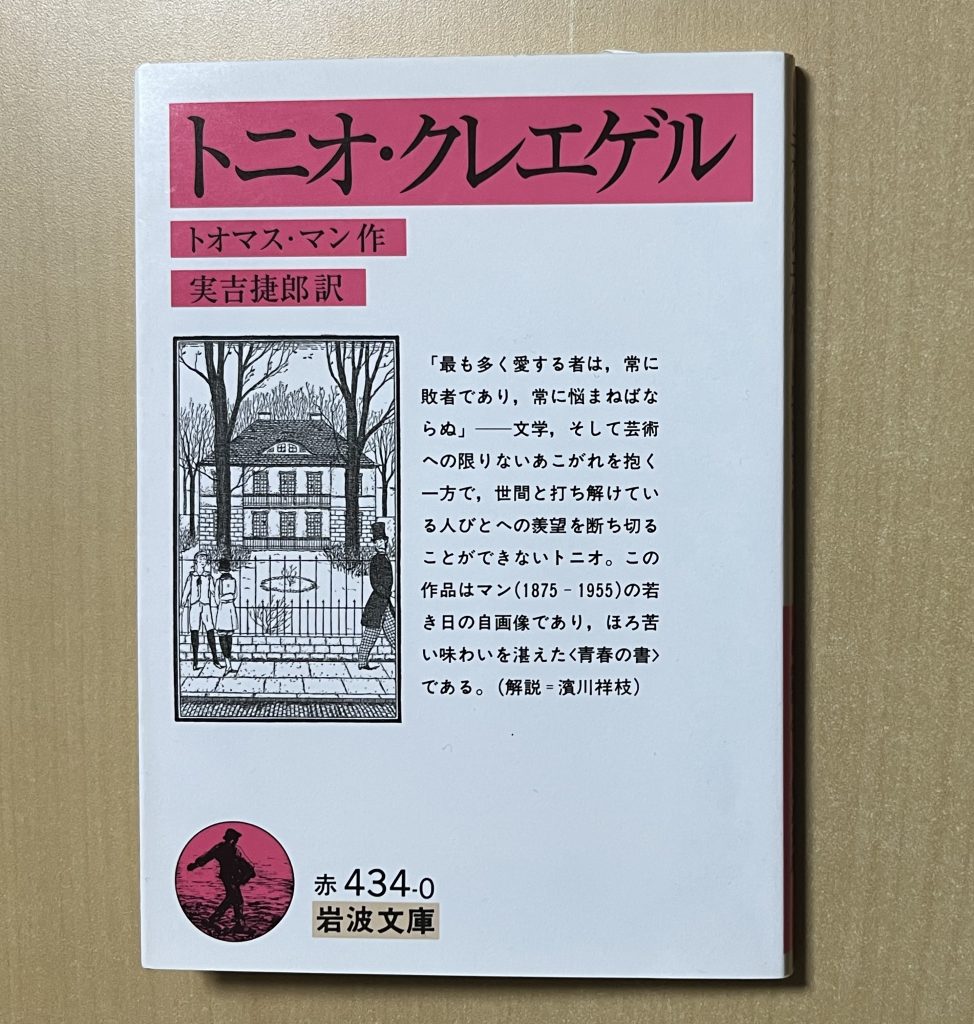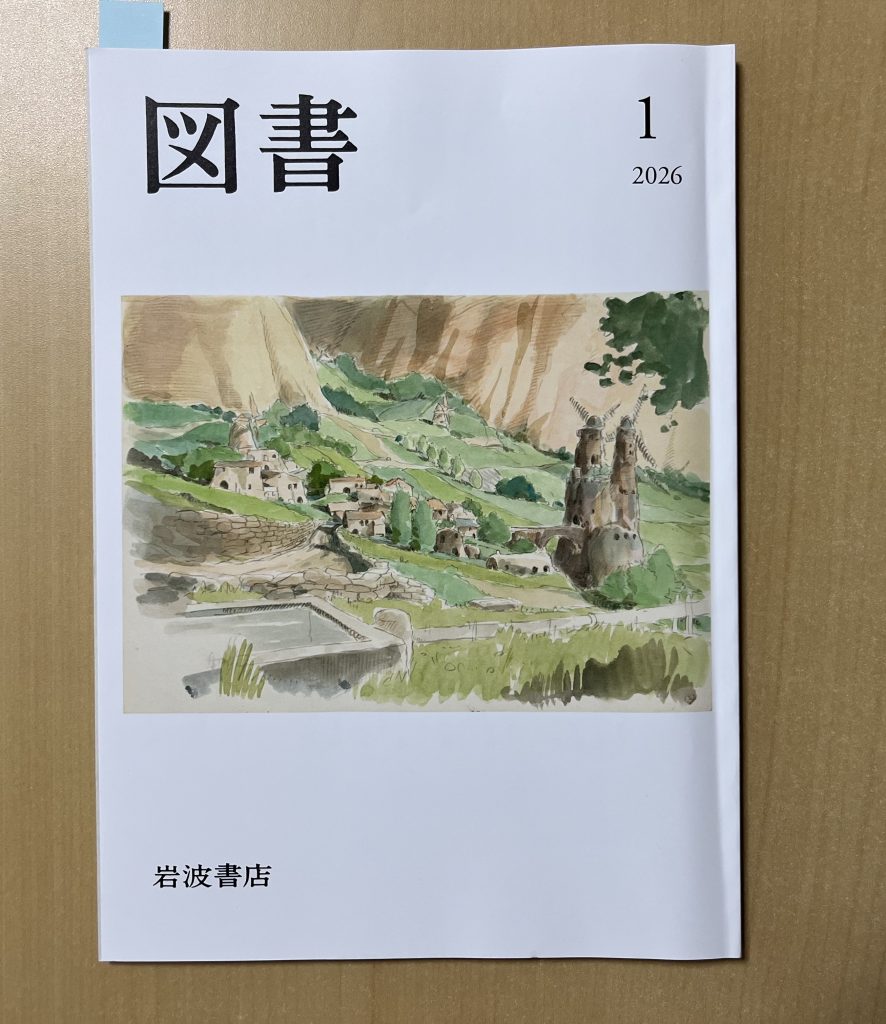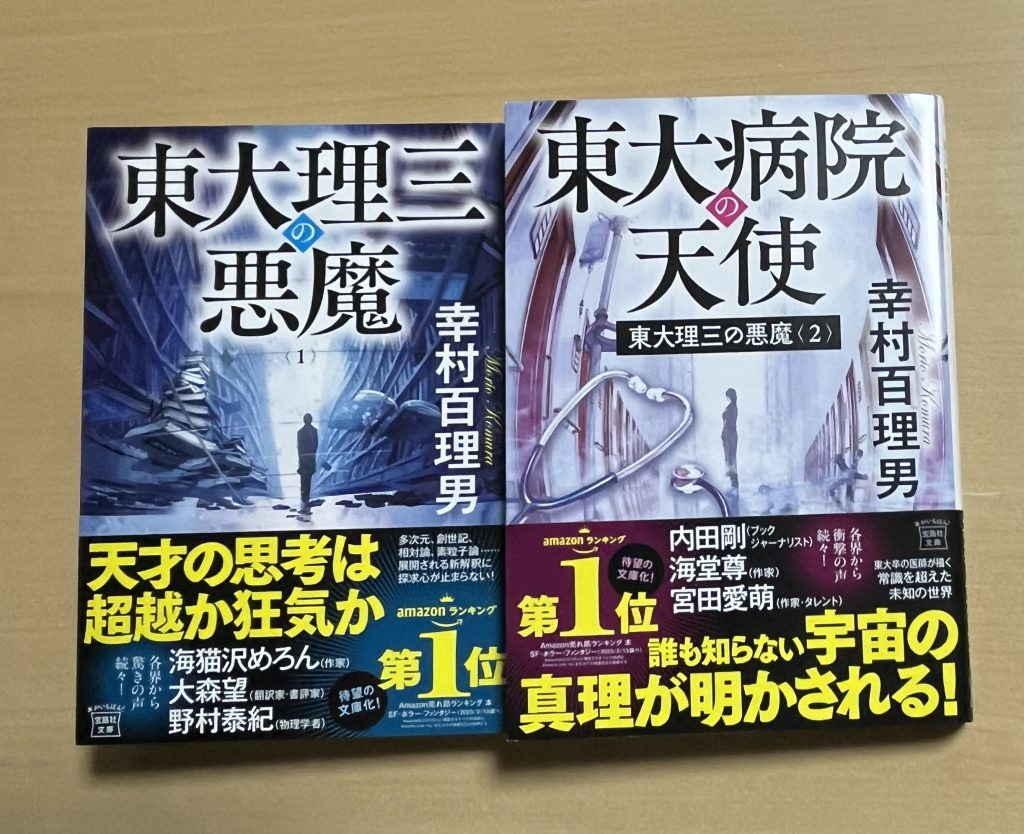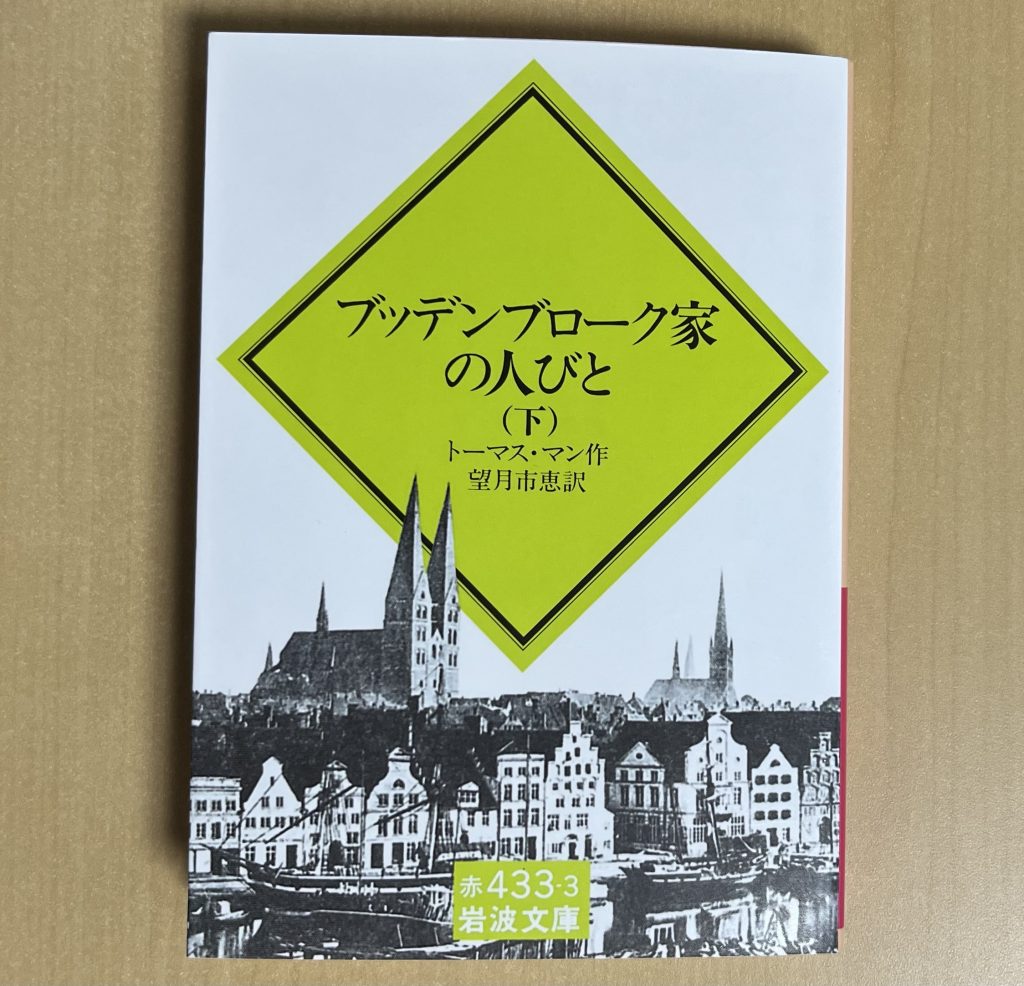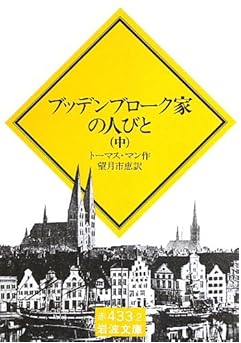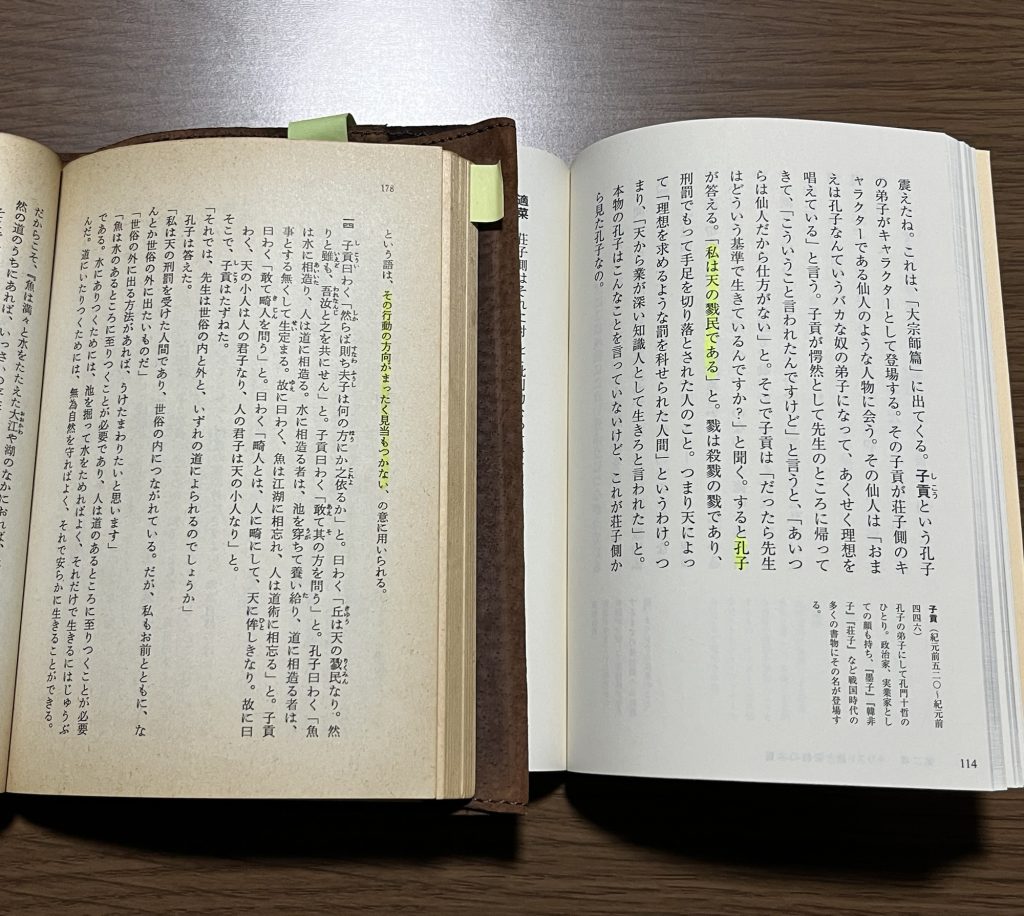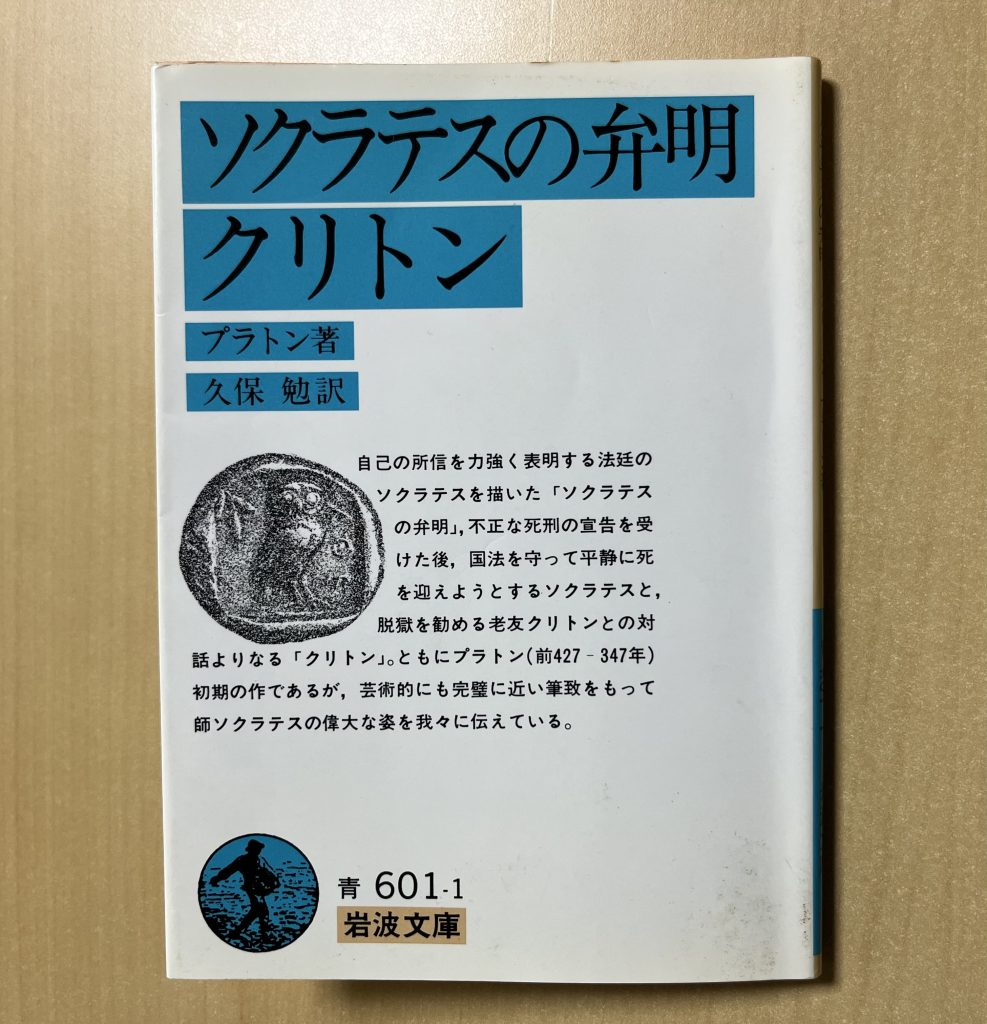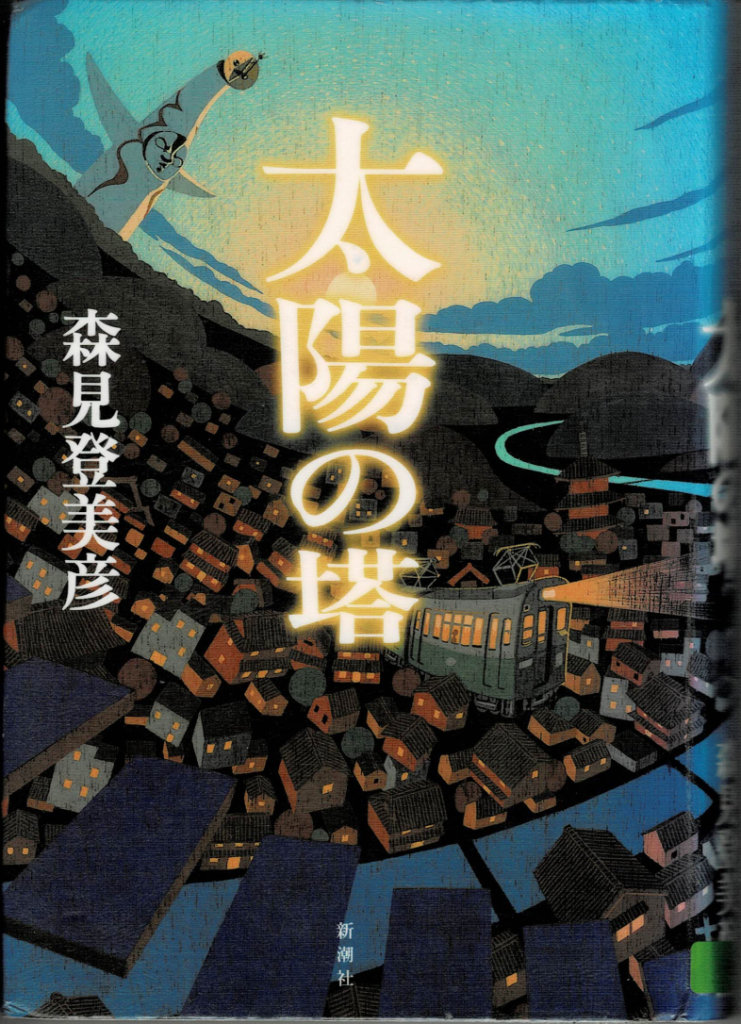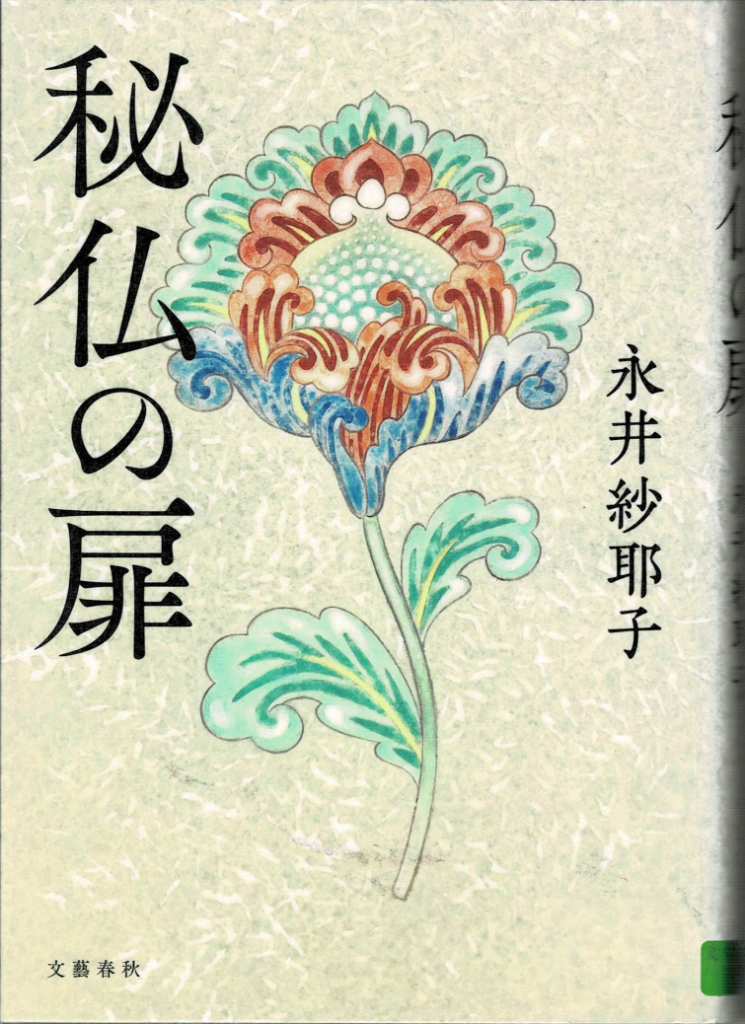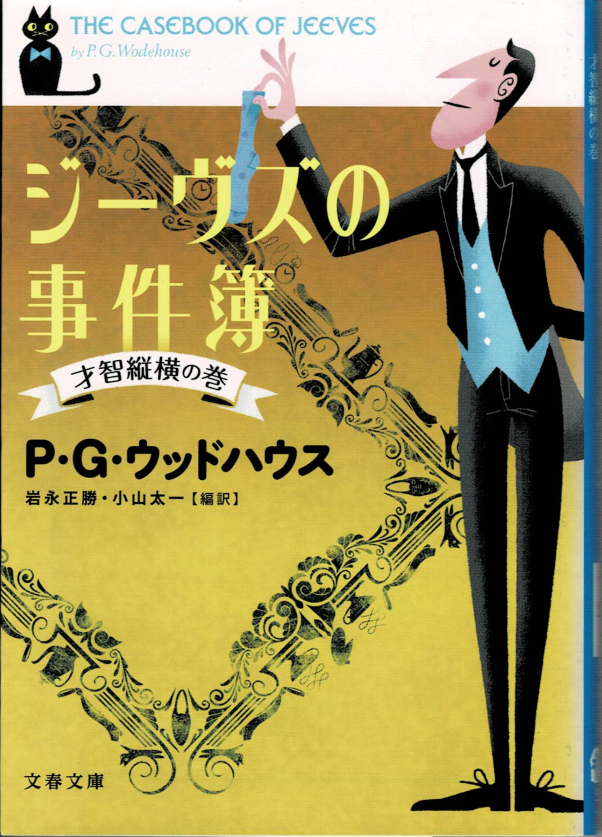年末にいつもの書店を訪れた際、入口の棚に岩波書店の「図書1月号」が差してあり、手に取って家に持ち帰ってパラパラとめくっていましたら、鹿島茂さんというフランス文学者の方の「共同体家族の構造と父親殺し=神殺し」というタイトルの論考(連載の11回目のようです)がありました。
最初のパラグラフで「カラマーゾフ」「トッド」「父親殺し」という言葉が目に入り、つい先ごろ取り寄せて読んだフロイトさんの『ドストエフスキーと父親殺し』と、こりゃあ密接な関係がありそう。立て続けにこういうものが手に入るというのは、これぞまさしくセレンディピティだと感じ、他のことを放り出して読みました。
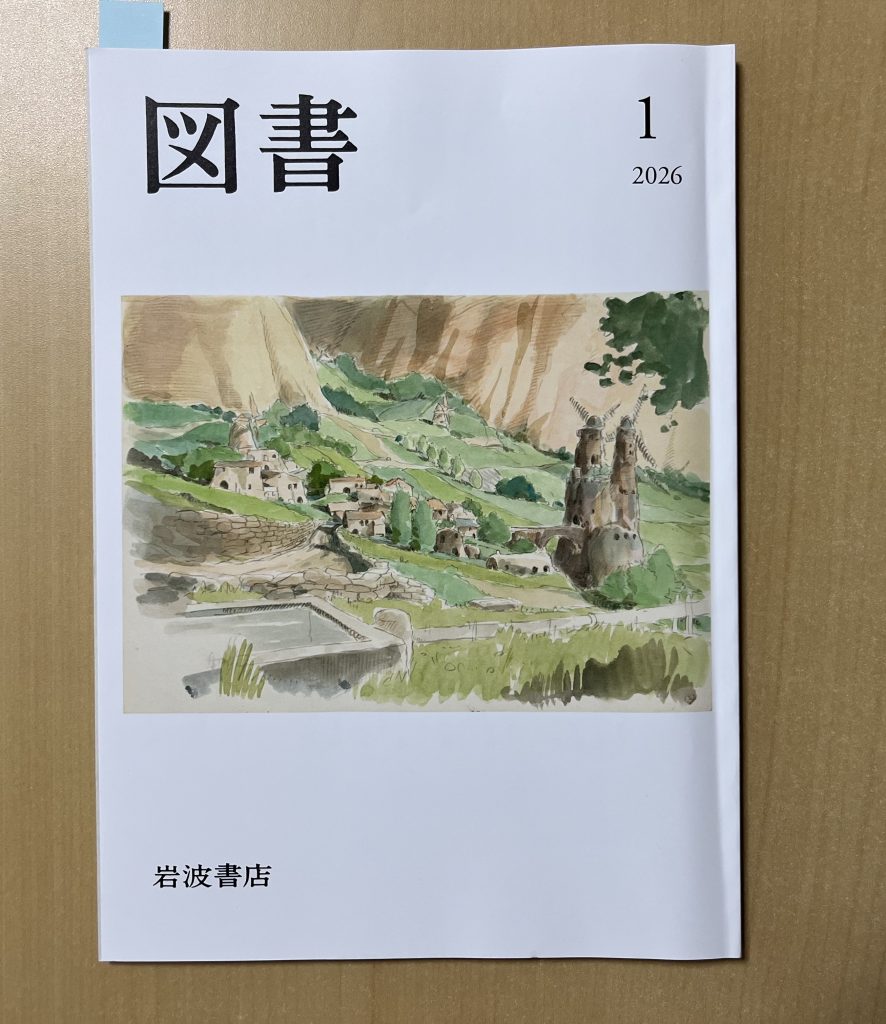
この中の「トッド」というのはフランスの歴史人口学者・人類学者のエマニュエル・トッド氏のことで、彼は「ある地域の伝統的な家族構造が、その社会の政治思想やイデオロギーの基盤(インフラ)を決定づける」という家族構造理論というものを提唱している方で、子供が家庭内で経験する「親との関係(自由か権威か)」と「兄弟との関係(平等か不平等か)」という2つの価値観が、国家のあり方の「設計図」になるということだそうです。日本では新書を中心に多くの著書が出版されています。
この論考からの抜粋ですが、トッド氏がある著書の中で「(カラマーゾフの)犯人はひとりではなく、何人もいるのである。つまりそれは兄弟たちである」と書いているそうです。続けて、物語(『カラマーゾフの兄弟』)の初めの方に出てくる、カラマーゾフ家の家族会議が彼らの屋敷でではなくなぜゾシマ長老の庵室で行われたのか、とか、トッド氏の「犯人兄弟全員仮説」がフロイトさんの理論を参照して導かれている、とか、吉本隆明さんの「対幻想」「共同幻想」とか、色々と興味深いことが書いてありました。ページ数にしてわずか4ページほどの短い論考ではありましたが、難しくてよく理解できなかったというのが正直なところです。セレンディピティには感謝しつつも自分の理解力の低さにはやや情けない思いを感じました。
他方、先に手元に届いて読んだフロイトさんの『ドストエフスキーと父親殺し』ですが、こちらは文庫本のタイトルにはなっているものの40ページほどで、こちらも割と短い文章です。1928年に書かれたものだということなので、『カラマーゾフの兄弟』が完成した1880年の50年ぐらい後のものということになります。
昨年12月13日のブログで生成AIに教わったことを書きましたが、それまでフロイトさんが『カラマーゾフの兄弟』について述べているということを全く知りませんでした。フロイトさんは精神分析の創始者であり、私の学んでいる交流分析の始祖エリック・バーン博士も直接の師弟関係はないものの精神分析をフロイトさんの娘の弟子だったエリック・エリクソン氏から学んだという関係にあるようです。ではありますが、なんとなく、このフロイトさんには、あまり近づこうという気持ちになりませんでした。(難しそう、という印象からかも知れません)

ページを開いてびっくり。いきなり「小説『カラマーゾフの兄弟』は、これまで書かれたうちで最高級の小説であり、作中の大審問官の逸話は世界文学の最高傑作の一つであると語っても、過大な評価ではない」とあり、ドストエフスキーを4つの観点で精神分析を行なおうと試みています。4つの観点とは、①道徳家の顔、②犯罪者の顔、③神経症患者の顔、④詩人としての顔、ということで、このあたりからして既に意味がわからなくなってくるのですが、①の道徳家としての顔や②の犯罪者としての顔については、結構ひどいことを書いています(本当なのかも知れませんが)。そのくせ④の詩人としての顔については分析する手掛かりがないとあきらめっぽいことを一言だけ書いて終わっています。
上の鹿島茂さんの論考との関係では、「カラマーゾフ家の兄弟のうちで、(中略)すべての兄弟たちは心理学的には有罪なのである。ドミートリーもイワンもスメルジャコフも、みんな同罪なのである。」という辺りが共通しているような気がします。それだからといって何かが明確になったというわけではありませんが、まあ色んな人が『カラマーゾフの兄弟』について色んなことを言っている、それだけ多くの人が関心をもってこの小説を扱っているということはそれだけ魅力の深い物語なのかも、という印象を持ったということです。
ドストエフスキーのお父さんは、領民に殺されたということですが、フロイトさんによると、実はドストエフスキー自身が父を殺したかった、そのため「犯人がまるで救済者のよいうにみえているかのようである。」「犯人が殺してくれなかったら、自分がみずから手を下さねばならなかった」「原犯罪ともいうべき父親殺しに立ち戻った」「この犯罪者の口から、文学者らしい方法でみずからの罪が告白された」という論を立てています。ホントかな?(本当に父を殺したいと思っていたのかな?)と思うのですが、フロイトさんはそういう分析をしてドストエフスキーが小説の形で父を殺したかった思いを遂げていると考えたようです。
さらには「古今をつうじた文学の三大傑作が、どれも父親殺しという同じテーマを扱っている」「ソフォクレスの『オイディプス王』、シェイクスピアの『ハムレット』、そしてドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』である。」と述べ、父親殺しの動機も共通であると書いています。筒井康隆さんのSF小説にも「エディプスコンプレックス」という言葉が結構出てきますが、フロイトさんの理論に関係あるのでしょうね。
ところが、ここではどうも決定的なことが書いてはなく、どうやら『トーテムとタブー』という別の論考で、父親殺しの理論が確立されているということを、「図書1月号」で知りました。どうも『ドストエフスキーと父親殺し』は難しいわりに中途半端な印象だったのは、これはエッセイのようなものだったのかも知れません。
ということで、次のテーマは『トーテムとタブー』を探せ、ということになりそうです。