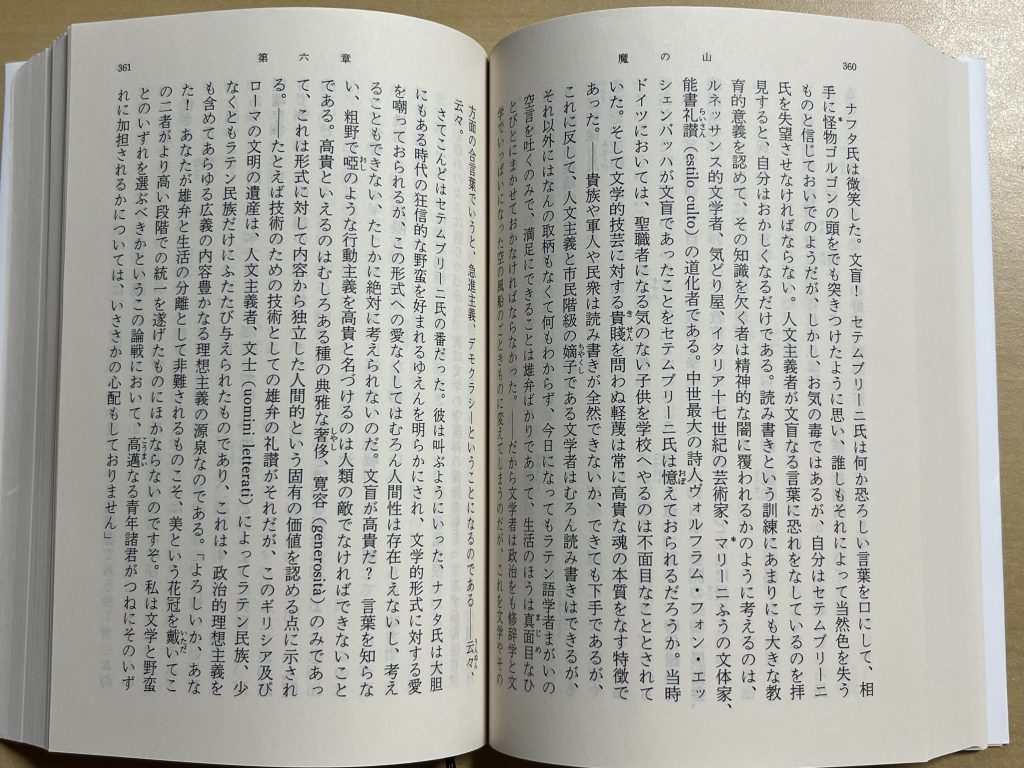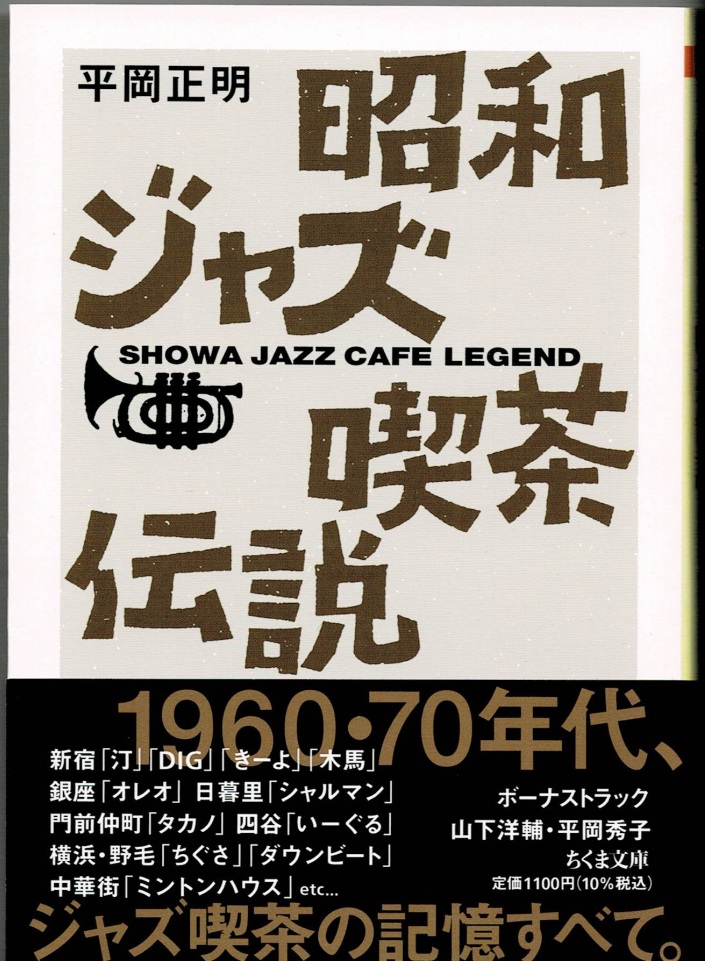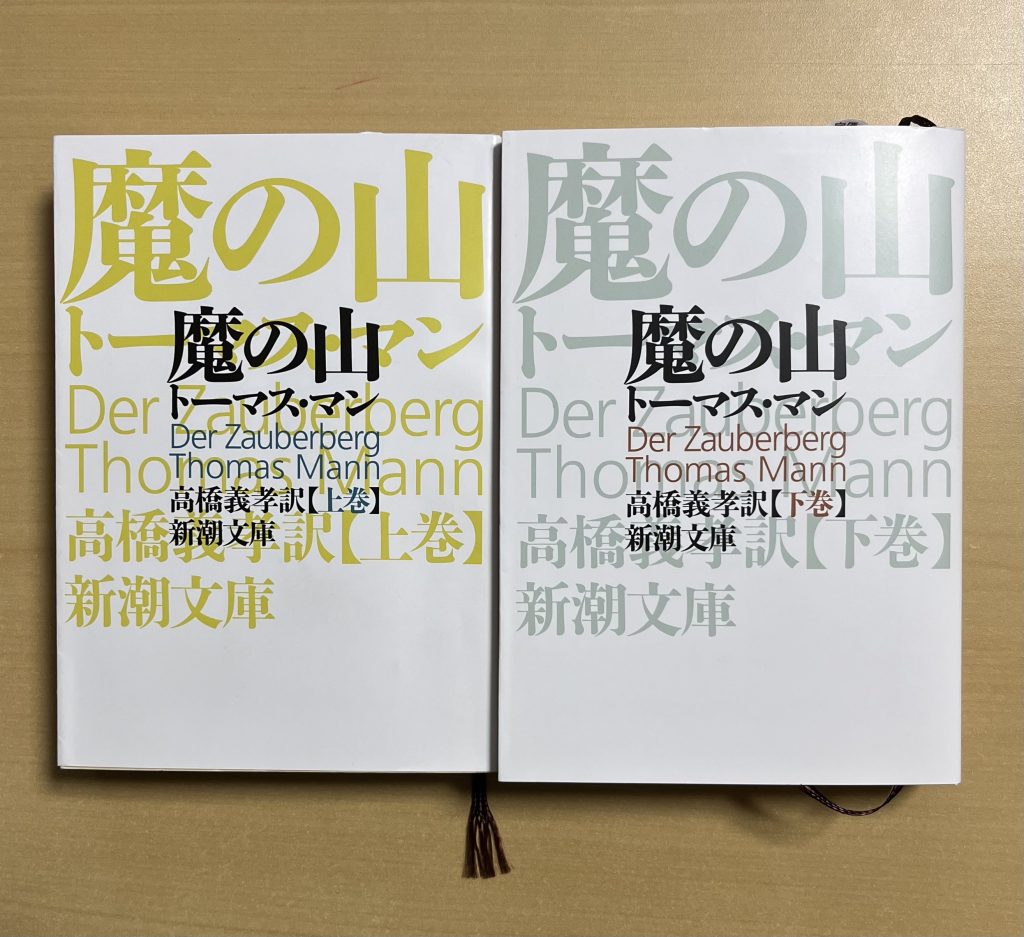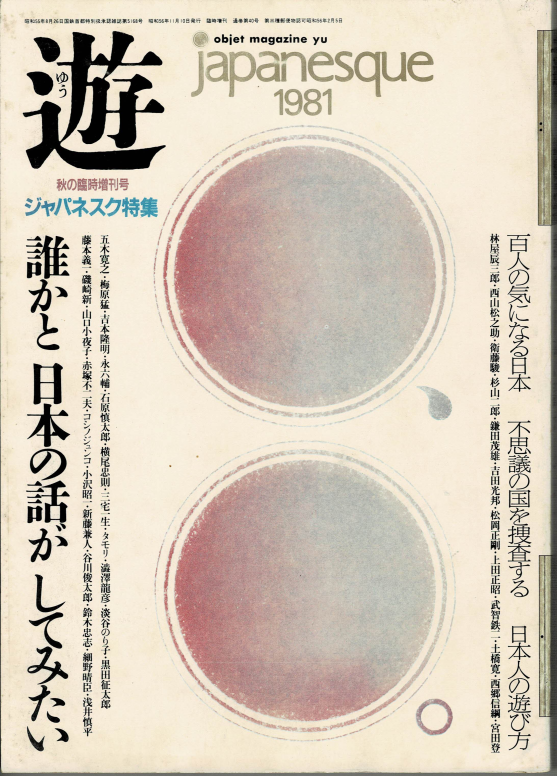心というものがあるのかないのか・・・心理学という学問がありますし、私たちは子どものころから霊魂というものの存在を聞かされており、地獄という世界があって死んだらそこに行かないように善行を積んでいかなければならないという教えに接していましたから、死んで肉体から分離していくものがあるのだろう、それが心もしくは霊魂というものなのだろうと、無条件で思っていました。
しかし、最近『心は存在しない』(毛内拡氏著)https://amzn.to/4gSgQM7という本を知り、これは仮説だとの見解で書かれたものではありますが、もしかすると吉本隆明さんの言っていた「国や社会は人間が作った共同幻想」というようなことと同じように、心や魂も脳が作った幻想ということかも知れないなあ、という仮説を立てて考えてみるのも面白そうだと感じています。
梶本修身さんという方が『すべての疲労は脳が原因』https://amzn.to/4a3B3wbという本をお書きになっていますが、先日ラジオでこの方の話を聴いていたところ、脳の真ん中あたりに自律神経の中枢があって、人間が色々な判断をすればするほどここが疲れて来るそうです。人間は一日に35000回もの意思決定・判断をしているそうなので、それは例えば単に走っているというだけでも(つまり、いわゆる仕事をしているわけではない時でも)周りの状況を見たり、足元の道の状態を感じて安全性を判断したり、ということらしく、尿意を催してトイレに行くのも自律神経が排泄を命じており、身体がその指示に従って動いているのでありそこにも自律神経による意思決定があり、それらの連続で脳の中枢が疲れてしまうのだそうです。沢山肉体を使って「疲れた」と感じることがあり、今日はよく肉体を駆使したからなあと思っていますが、それは肉体が疲れたのではなく、肉体に酸素を供給する前提の状況判断や送るという判断をして送り続ける自律神経の働きが疲れたということらしいのです。確かに言われてみれば、身体が疲れた、と感じても、そのあと事態が急を要するような時には、「動ける、あれ?動けるぞ」ということも実際にありますから、もしかして肉体が疲れたというのも錯覚(脳が、自分が休みたいので、身体を横たえさせようとしていることを勘付かれないように隠れて指示しているために起こる錯覚)なのかも知れません。
優秀な方は、意思決定の量を少なくすることを心がけており、日々の生活の中になるべくルーチンを多く取り入れていると聞いたことがあります。具体的には例えば故スティーブ・ジョブズ氏は、いつも黒のタートルネックとジーンズという風に衣類を選ぶために脳を使わないといった話がありますが、こうした事例も沢山あるようです。してみると、いかに脳を活力あふれる状態で使い続けられるかということは、一つには判断しなくても良いようなことの判断をしなくても良いような生活習慣を取り入れることのようです。
と同時に、睡眠が極めて重要だということも梶本修身さんは仰っていました。
睡眠と言えば上田泰己さんという方が『脳は眠りで大進化する』https://amzn.to/3DNy6Unという本を書いておられ、こちらも注目しています。日本人の睡眠が短いということは以前から指摘されており、この本の中でもOECD33か国中日本人は男女とも最も短いということが書いてあります。日本人の平均睡眠時間は7時間22分とのことですが、個人的にはそんなには寝ていないなあと感じます。それでも40代の激務時代から比べれば伸びてはいます。そういえば大谷翔平さんが睡眠をとても重視しているという話はよくインタビューでも言っておられますし、スケートの浅田真央さんも良い睡眠のためのマットを持参して遠征に行っておられたという話も聞いたことがあります。
論理性に著しく欠ける話ではありますが、脳科学の最新研究成果だと言われている上記の色々な話を総合すると、どうも、脳の真ん中にあって色々な命令をつかさどる機能が生命の本質なのではなかろうか?という仮説を持っています。その機能≒自律神経を司っている部分は、生れて来たからには生き続けるということがプログラムされているように思います。例えば他の人から危害を加えられそうになったら、人は一般的には防衛や反撃をします。肉体的な危害もあれば精神的な侮辱などのことも危害と捉えると、防衛や反撃は、自己の生存を守るための反応ですので、脳の中枢にある自律神経を司るものがそれを命じているのだなと考えます。
スピノザは『エチカ』https://amzn.to/41P9sNkという書物の中で人間の基本的感情を3つに限定して、それ以外の感情はその3つの基本的感情から派生しているものだといったことを述べています。3つの基本的感情は「喜び」「悲しみ」「欲望」(文庫(上)181ページ)ということで、(ここからは交流分析からの学びに関係していますが)それらはいずれも人間の生命を維持することを目的にしたもののようです。怒りやすい人も泣きやすい人も呵々大笑しやすい人も、恐らく子どもの頃にそういう反応をした際に「生命」を維持できた、という成功体験が積み重なって大人になってもそういう感情が表出しやすくなっているのではないかと思います。
そこで改めてアリストテレスがどのようにそこら辺りを見ていたのか?ということを調べてみようと思い立ちました。彼の『心とは何か』https://amzn.to/4hf3fyPという本が岩波文庫から出版されています。邦題は他にもいくつかのタイトルがあるようですが。この本の解説に「アリストテレスは、プシュケーが身体から独立した存在であることを否定」とあり、「心とは身体がある一定の能力をもった状態である」「一種の能力」とあります。さらに「心は、生きていることの原因であり、その原因とは、栄養摂取能力、感覚能力、運動能力、思考能力」ともあります。ちょっとだけ脱線しますが、アリストテレスはこの本の中で「睡眠と覚醒については別のところで考察する」と述べており、この別の考察について書かれたものはなんと『アリストテレス全集第6巻』という大部の著書に当たらなければならず、すぐには手が出ませんが、上記の「眠り」の本や「すべての疲労は脳」の本などとも関係があるかも知れないと考えると興味が尽きません。アリストテレスを絶対視するつもりはありませんが、今の色々な科学の多くが遡れば彼の思惟に行きつくことを考えると一旦彼が何を語っていたのかということに触れ、改めて考えるのも意味があるのではないかと思います。改めて同書の解説ですが、この本は「難しい著作のなかにあって、内容の深さの点から言っても、頂点に位置する」のだそうで「他の著作で論じた論点の上に築かれており」「この講義で用いる重要な概念に受講者があらかじめ通じていることを前提にしている」のだそうです。「睡眠と覚醒」などにしても別の所に書いたからそっちを先に読んでからこっちに来なさいね、ということなのだろうなという気もします。
生きんかな、というのが生命の本質だとすれば、そのために色々な外からの刺激にどう反応すれば最も生命維持にとって有効かを経験や知識から選択して判断している、ということが私たちの日常生活なのでしょうか。しかし中には『心配事の9割は起こらない』https://amzn.to/3W1LZ7Uとか『反応しない練習』https://amzn.to/49XM0zmといった、実際にそうだなあということもあり、ちょっと見渡せば、自律神経を酷使して「つっかれたあ」と感じなくても良いような知恵が周囲には沢山あることにも気づきます。
脳と心について、感情の起伏、睡眠による疲労回復、元気溌剌で過ごすために工夫できることなど、調べ始めたところですので、今後もっと勉強し2025年はこういう知恵も使いながら楽しく心地よく過ごしていけるようにしたいものです。