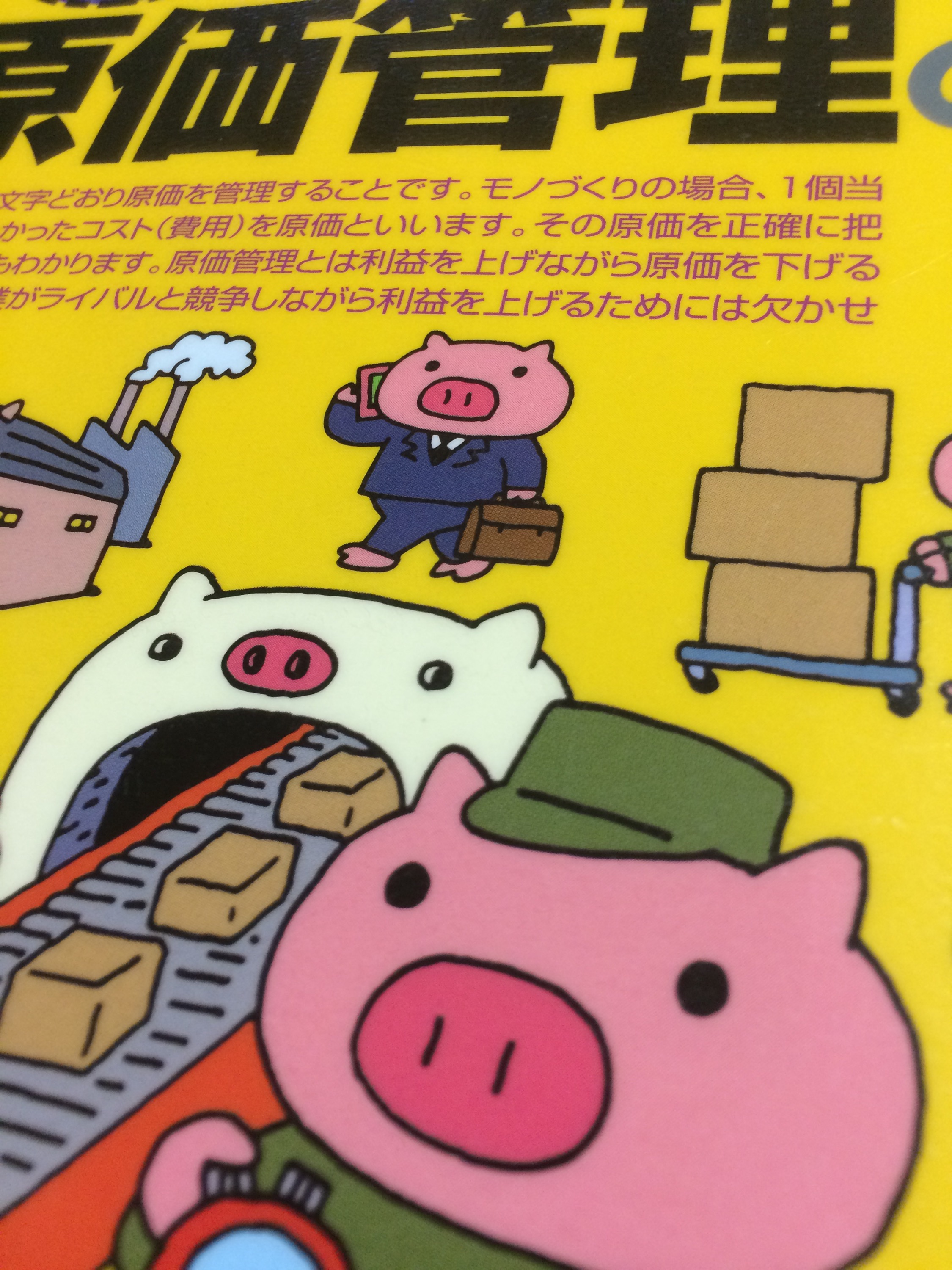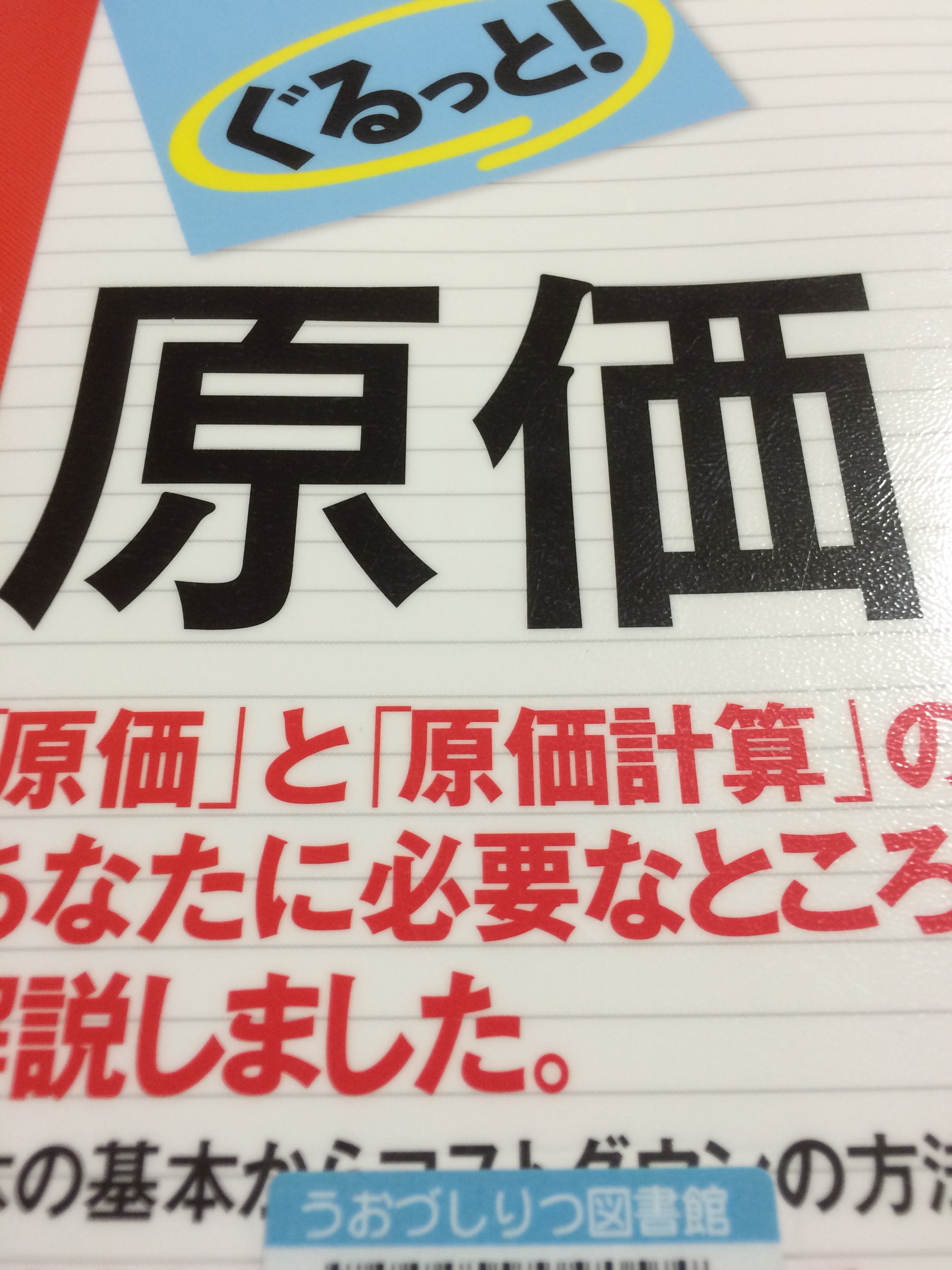外で着ることのできるTシャツを買おうと、ユニクロに行きました。
相変わらずここはお客さんで賑わっていますね。
無地では面白くないなあと、デザインの施してあるのを見ていたら、隣の女性が「あ、ゴーストバスターズのTシャツがある」と言ってしばらく見入ってました。
女性が去るのを待っておもむろにその棚を見ると、ゴーストバスターズに出てくるマシュマロマンのデザインのTシャツの下から、どこかで見た小太りの米国人男性の顔がプリントしてあるTシャツを発見。
ややっ!
これはもしや、と広げてみると、なーんと、やはり我がジョン・ベルーシ&ダン・アイクロイド、ふたり合わせてあのブルース・ブラザースではありませんか。
![IMG_2792[1]](http://team-work.sakura.ne.jp/blogdb/wp-content/uploads/2015/06/IMG_27921-e1434794428770-225x300.jpg)
即購入したのは言うまでもありません。それも2枚。しばらくぶりに嬉しい買物でした。