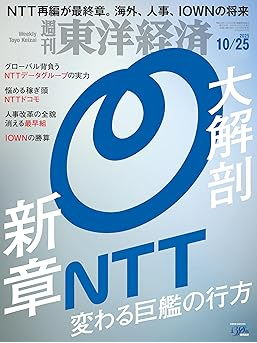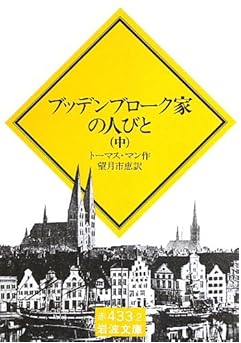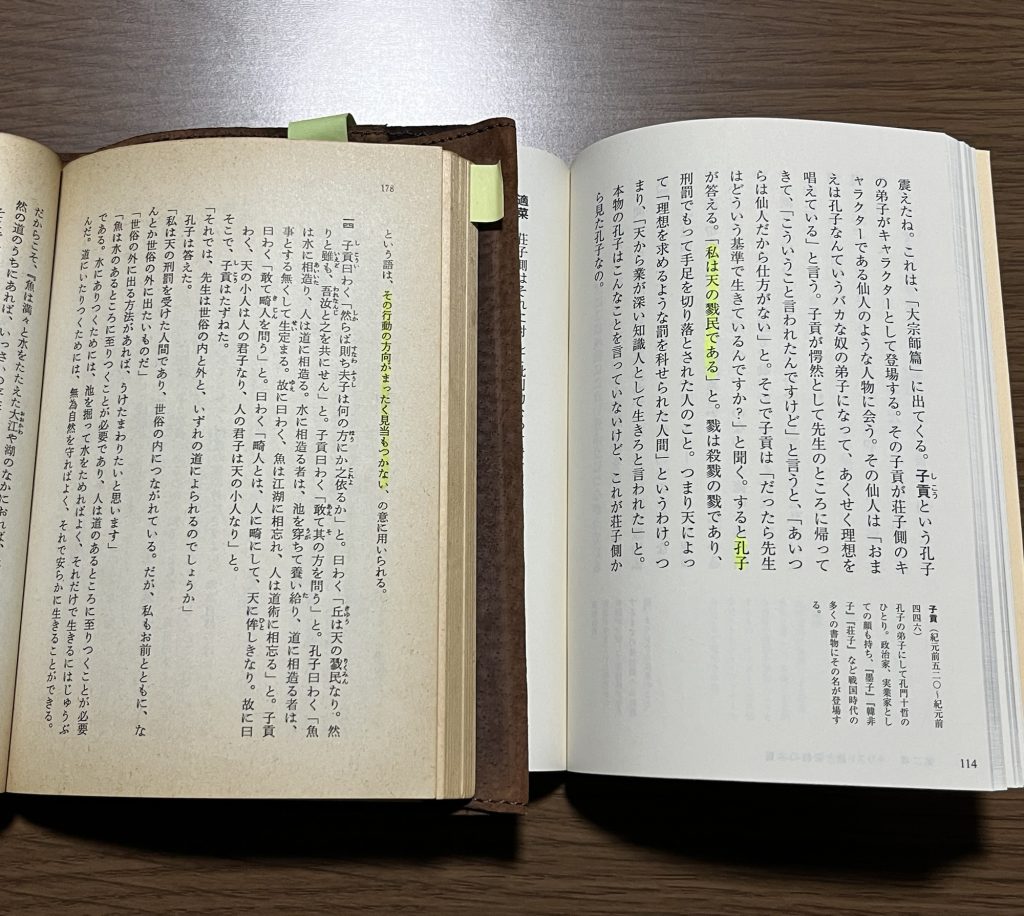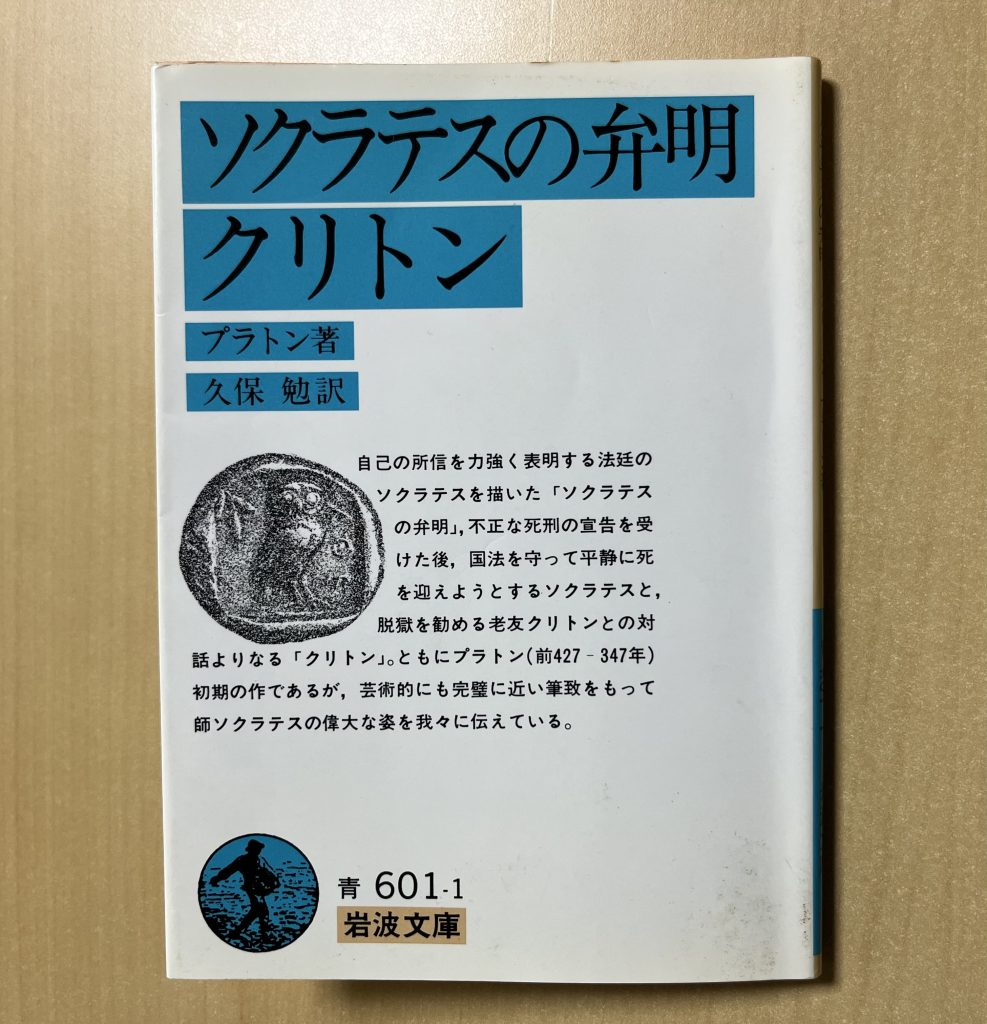「君がもしそういった彼らの売り物のうちで、どれが有益でどれが有害かをちゃんと知っているのだったら、いろいろな学識を買い入れるということは、それが誰からであろうと君にとって別に危険はない。
だが、もしそうでないのなら、君は何よりも大切なものを危険な賭けに晒すことのないように、よくよく気をつけたほうがいい。
実際、学識を買う場合には、食べ物を買う場合よりも遥かに危険が大きい。なぜって、これが飲食物だったら、卸商人や小売商人からそれを買っても、別の入れ物に入れて持ち帰ることができるし、飲んだり食べたりして、体に入れる前に家に取っておいて、食べたり飲んだりして良いものといけないもの、その量や時期などについて、識者を呼んできて相談することができる。
だから、それを買うのに大した危険はない。だが、これが学識となると、別の入れ物に入れて持ち去るわけにはいかない。一旦お金を払うと、その学識を直接魂そのものの中に取り入れて学んだ上で、帰るまでには、すでに害されるなり益されるなりされてしまうからだ。」
この文章の、たとえば「売り物」を「情報・知識・知恵」などと読み替え、「買い入れる」「買う」を「仕入れる」「取り込む」と読み替えるとどうでしょうか。
プラトンが書いたソクラテスの対話として、『ソクラテスの弁明』に続く第二段として『プロタゴラス』と取っ組み合いをしています。
この文章を読んで、思いもかけず、現代の情報過多時代に私たちの脳の発達が追い付かなくなって、情報を適切に処理できない場合があるという現状に思いが及びました。
例えば生成AIとの付き合い方。
アメリカでは生成AIに相談して自死に至った若者がおり、その親族が訴訟を起こしているという悲しい出来事も起きています。
私自身は、自分の仕事の中では、知っていることの範囲内で整理のために使うことが多く、知らないことが生成された時は出典を確認したり他の方法での検証も行うようにしています。
或いは最近のSNSがもたらす世の中の分断。
本当のことやら嘘のことやらが判断つかなくなるように溢れかえっています。
東日本大震災の時には動物園からライオンが逃げ出したという投稿が写真付きでなされていました(南アフリカの写真を日本での出来事のごとく投稿したものだったと思います)。
よく言われているように、コンピューターのアルゴリズムによって、私たち自身がいつの間にか自分の好むようなフィルターバブルの中に入ってそれで世界観が構築・変容・強化されてしまったり、エコーチェンバー現象で多様な考え方と接することが著しく減ってしまったり、ということもあります。
それあある意味本人にとっては心理的安全性の高い居心地の良い時間の過ごし方なのかも知れません。が、それがためにちょっとでも考え方や意見が異なると、相手を「敵」と見なして「排除」したり過度に攻撃的になったりということで、ここ最近はまたSNS空間が荒れ模様になってきているように思います。それだけ世の中がギスギスしているのか、了見が狭くなっちゃったのでしょうか。或いは情報を冷静に仕分けをする能力(脳力)が追い付いていないのか。
仕事柄、経営相談に応じる際、特に事業を始めてあまり時間の経っていない創業者の方々などは、私たちのことを「先生」とお呼びになることがあります。先生と呼ぶ呼ばないということとは関係ないかも知れませんが、ご相談者は、私たちが提供する情報・知恵・考え方・経験談を「直接魂そのものの中に取り入れて学ぶ」可能性があります。大半のご相談者は自分で決めなければいけないということを認識おられますが。判断し決定するのはあくまで本人である、私たちはその判断材料を提供する役割だ、決して「教祖」のごとくなってはいけない、ということを肝に銘じつつ、またそのことをしっかりお伝えするよう今後とも心がけていくべきだと、改めて感じた次第です。