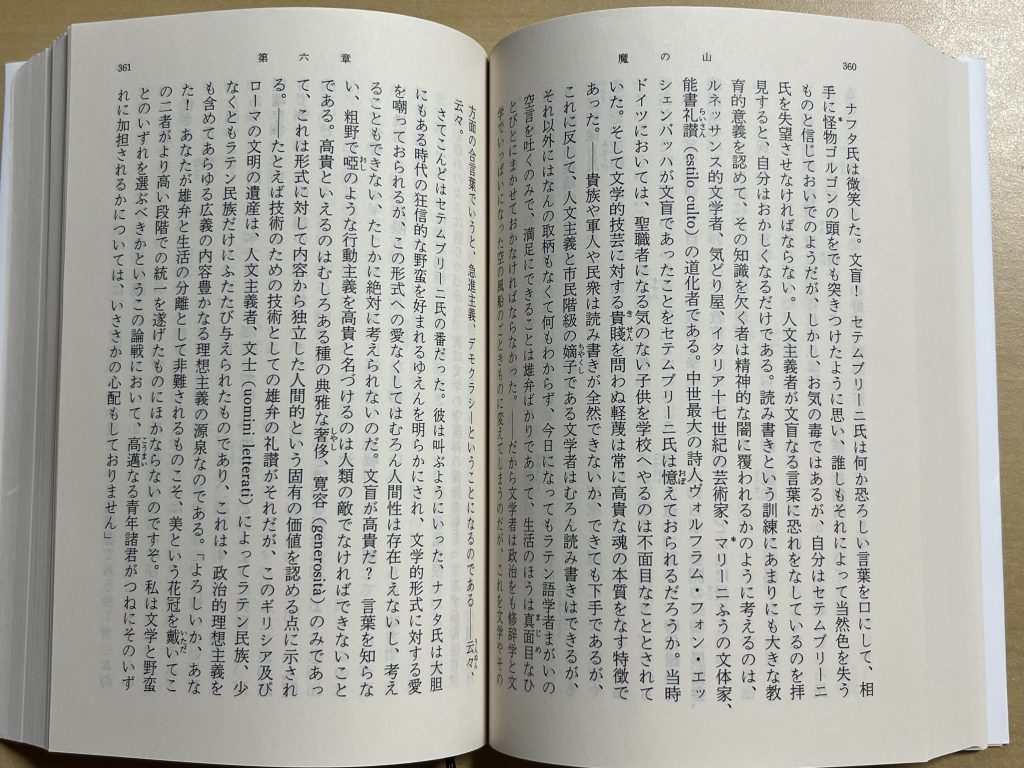年明けから挑戦していたトーマス・マンの『魔の山』をようやく読み終えました。1912年に書き始めて1924年まで12年間、1200ページの大作となったものです。私も意を決してから読了するまで5カ月かかりました。理解できたかというと文字を追うのが精いっぱいでほぼ理解できていないと思います。
そもそもどういういきさつでこの本を読むことにしたのか、記憶が定かではありません。大方、筒井康隆さんがお勧めしていたから、というような理由ではないかと思いますが。
最初は岩波文庫で上巻を買って読み始めようとしたのですが、全く歯が立たず、新潮文庫であればもう少し平易な言葉で書いてあるかも知れないと思い込み、新潮文庫で上下巻を買い、取り組みました。しかし新潮文庫の方も難解であることは変わりなく、これは原書がそもそも回りくどく難しい単語を並べ立てているからかも知れないなと観念して、そのまま続けました。
訳した高橋義孝さんが解説で「ユーモア小説」だと書いておられますが、どう読んでも面白おかしいという感じではありません。むしろ本当に難解で、書いてあることの1割も理解できていないような気がします。シーツ・オブ・サウンドばりの文字が敷き詰められている書面、観念的な言葉の羅列、しかも突然場面が変わったり、行間を読まないといけないような意味深な文脈。
ではありましたが、最後まで読んで「ユーモア小説」だと言われれば、そう思えなくもありません。むしろ、壮大なドタバタだったのではないかとすら思えてきました。小説であることを考えると、登場人物の死すら「出来事」として傍観的なものとして扱われているのかも知れず、私の中では筒井康隆さんの『俗物図鑑』が思い起こされてきました。
そうは言いつつ、箴言的な、「あっ」と気づくような文章もあちこちにあり、小説でありながら沢山のページの角を折り曲げ、線を引くというようなこともしました。
箴言ではありませんが、20世紀の前半に書かれたこの本で、こういうことを書いていたのだ、と感じた部分を一つだけ紹介しておきます。『魔の山』上巻p570に「だから意識なるものは、結局のところ、生命を構成している物質の一機能」という言い回しがあり、これは最新科学の一つかも知れませんが、毛内拡さんの『心は存在しない』(本は読中)という著書に関連してラジオで「結局肉体と別に魂というものがあるわけではない」というようなことをおっしゃっていたことに通じるような気がします。もちろん学説の一つであって、解明されたものではないのかも知れませんが。
わからないことが多いため、生成AIに色々尋ねてみました。得られた回答らしきものをnoteに投稿しましたので、ご関心がありましたら覗いてみて下さい。https://note.com/light_quokka2104/n/n1daf7d493f51
さ、次へ。