起業や事業化に当たっての進め方として、目標を設定しそこに至る道筋や必要な資源などを考えて取り組む「コーゼーション」型と、今何ができるかということを手持ちの資源から考えて取り組んでいく「エフェクチュエーション」型の、2つのアプローチ方法があり、それらを市場での自社のポジションや市場の成熟状況などに応じてうまく使い分けて行くことが大切だとありました。
私はこれら2つの言葉を初めて知りましたし、うまく発音できるかもおぼつかないのですが、現実の世界では、後者のような走りながら考えるということが往々にしてあるような気がします。重要なのは、走りながら考える場合であっても、予め損失許容範囲を定めておくということのようです。これにしても、多くの人は意識してか無意識のうちでかは別として、そのようにしておられるようにも思います。子どもの頃の「小遣いの範囲内で遊ぶ」という習慣みたいなものかも知れませんが(例えが卑近すぎるかも知れません)。
もしかすると、旧日本軍の「失敗の本質」に見られるような戦力の逐次投入や現代の日本企業にも見られる損失回避のための追加投資によってさらなる損失をもたらす、いわゆるサンクコストのようなもの、或いは賭け事に依存して負けても負けても借金を増やしてまた賭け事をしてしまう・・・結果的に、そのうち取り返すことができるのかも知れませんが、多くの場合取り返すことができない結果になるのは、この損失許容範囲を決めていないことが原因かも知れません。
他にも、「目から鱗」といって良い知見をいくつも得られました。機会があればまた投稿したいと思います。
月別アーカイブ: 2024年3月
志賀直哉さんの『和解』
奈良の東大寺は二月堂の裏参道がとても良い風情です。大阪で7年半勤務をし、東大寺にも何度も足を運びましたが長らくそのことを知らず、確か司馬遼太郎さんの『街道をゆく』のいずれかの回のものを読んだ際、それも大阪滞在中の晩期にようやく知った次第です。
二月堂の裏参道から大仏さんの方には行かず二月堂から三月堂を抜け、若草山の麓の茶屋街を通っていくと、やがて春日大社に出ます。春日大社を左に見つつ境内の終わりまで行くと、目の前に急に鬱蒼とした森が現れます。春日山原始林の一角です。奥に足を踏み入れず、人が歩けるように整備された道があるので、そこを進んで行きます。「下の禰宜道」又は「ささやきの小道」と言われる遊歩道です。そこを200~300mも歩くと、森を抜け、民家の立ち並ぶ町に出るのですが、そこからすぐの所に「志賀直哉旧居」という看板のあるモダンな家があります。場所は奈良市高畑町という所になります。

へえーっ、ここがあの有名な志賀直哉さんが・・・このような場所で暮らしていたのか・・・春日大社まで徒歩10分、東大寺や興福寺や猿沢池が散歩コースなんて、なんて優雅な場所に住んで小説を書いていたのだろうか・・・ととてもうらやましく感じたものです。この方の小説はその頃はまあ読んだことがなく、どんな人物なのかもさっぱり知りませんでした。(写真は2009年8月に現地で撮影したものです)
とりあえず中に入らせていただいたのですが、部屋のしつらえを見てびっくり。子どもたちの教育にとても熱心なことがわかるような子ども部屋になっていました。いわゆる教育パパといった感じではなく、子どもたちの自発性を重んじる、自分たちで学んでいこうと思わせるような環境作りをしておられるなあという印象を持ちました。なんと庭にはプールまであったようで、その跡が残っていました。
奈良市高畑に住む前は、奈良市幸町という所に住まわれていたようで、通算奈良には13年住んでいたことになります。しかしその後、男の子の教育のためには東京が良いということで、東京に移住してしまいました。そんなこんなでこの人は生涯(幼児期も含め)23回も引越ししておられるようです。88年の生涯ですので、なんともせわしない感じがしますが、それでもこの高畑には丸7年住んでいたようなので、それなりに居心地が良かったものと思います。私も2階の部屋に上がらせてもらって窓外の風景を眺めていたら、とても気分が落ち着き、いつまでもここの空気を吸うていたいものだと思いました。家を作るならこういう家だなあとも。
その後『暗夜行路』に挑戦しましたが、なかなか進まぬうちに、遂に15年も経過してしまいました。この人は若い頃に父親と不和になり、わだかまりを長いこと抱えて過ごし、三十代初めには取り返しのつかないくらいの険悪な間柄になっていた、しかしその後34歳頃に不和が解消された、ということを見聞きしており、『暗夜行路』もそういうことをテーマにしたものだということです。一小説家がその父親と喧嘩しようが何しようが構わないし、そのことを長編小説で書き連ねられても、私にとってほとんど意味がない、そもそも私小説とは他人様のプライベートを読まされるものであり、共感できるものであれば有益かも知れないが、場合によっては作家さんと傷をなめあうだけのなぐさみにしかならないのではないかという心持ちが私にはあり、あまり私小説を読んで来なかったということが、途中で投げ出してしまう原因かも知れません。
何かの拍子で志賀直哉さんが父と和解したことそのものをテーマにした短編小説に書いているということを知り、そんなことが小説になるんだ、という思いと、どういういきさつで和解したのだろうということに関心がわき、読んでみました。
ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』は「父殺し」がテーマだと言われています。男の子が父親を憎いと思うエディプスコンプレックスも「男子が最初に出会う女性の性愛の相手である父に対する怒り・憎しみ」だと言われます。男の子とその父親というのは根本的にライバル関係(なんて生易しいものではなく、果ては殺し合いにまで発展することもあるくらいに恐ろしいものかも知れません)にあるというのは、頭で考えてどうこうなるものではないような生物としての宿命かも知れません。或いは、自分の中の嫌な部分が父の中に見出され、自分は父の嫌なところを受け継いでいるという事実を直視したくない無意識の抵抗みたいなものもあるのかも知れません。しかし志賀直哉さんの物語は、父親をうざい存在だと思う息子の無意識で無自覚な感覚が、やがて、自分は一体何に抵抗していたのだろうか、何と「無意味」で「馬鹿げている」ことをしていたんだろうか、と気づく瞬間があります。ここに至る経緯には、志賀直哉さんの最初のお子さんが生後数十日で亡くなってしまったことや、その翌年に二人目のお子さんを授かったこと、気丈だった祖母が随分弱ってしまったこと、などがあり、なぜか卒然と父を赦す気持ちが芽生え、母(志賀直哉さんの実の母は既に亡くなっており、継母に当たる方)の仲介を得て父との長年の確執を終えることになったようです。この時父親も「これまでのような関係を続けて行く事は実に苦しかった」と吐露してくれます。今の私は息子である志賀直哉さんの立場も、父親の立場もわかるせいか、このセリフを読んだ瞬間に、熱いものがどっと溢れ出しました。良い小説だと思います。
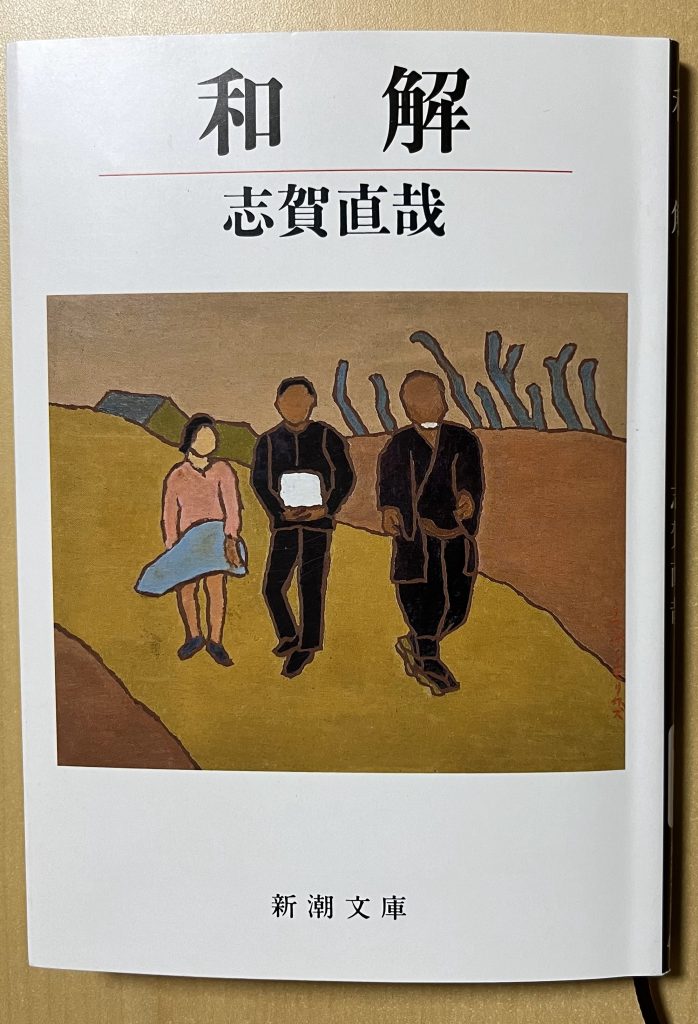
この和解に至るまでの行程は随分長く、この人の日常風景が延々と語られます。しかし所々に志賀直哉さんの心情の変化をもたらす伏線のようなものが描かれています。
例えば新潮文庫のp68には「前々夜から前日の朝までジリジリとせまってきた不自然な死、それにあるだけの力で抵抗しつつ遂に死んでしまった赤児の様子を凝視していた自分にはそれは中々思い返す事の出来ない不愉快だった。総ては麻布の家との関係の不徹底から来ていると思った」とあり、自分の周囲で起こる不幸な出来事、それと向き合えない自分、すべてを父のせい、又は父との間柄が不仲である現状のせい、という風に、自分以外のなにかに責任を転嫁している様子が描かれています。
そして父に詫びを入れ、父からも赦しの言葉をもらったあとは「非常に身体も心も疲れて来た。そしてそれは不愉快な疲れ方ではなかった。濃い霧に包まれた山奥の小さい湖水のような、少し気が遠くなるような静かさを持った疲労だった。長い長い不愉快な旅の後、漸く自家に帰って来た旅人の疲れにも似た疲れだった。」(P131)とあり、爽快な感じではないものの、重荷を下ろしたという感じが伝わってきます。
実はあまり目立った扱いにはされていないものの、志賀直哉さんの奥様(康子(さだこ)さん)の、この短気者(志賀直哉さんのことです。意外に短気だったようです)に対する気遣い・支えがあったればこそ、今日に至ったのではないかと思います。
それにしてもこの「濃い霧に包まれた山奥の小さな湖水のような」という自分の心持ちを表す表現は、なかなか思いつかないような表現だと思いましたが、私にとってはしっくり来るものでした。世の中には悲しい結末の物語もあり、エンディングを知ることは恐怖であることも往々にしてありますが、この『和解』は実話に沿っているということも含め、久しぶりにカタルシスを味わうことができました。
今も新鮮な耳ざわりの「ララバイ・オブ・バードランド」(byクリフォード・ブラウン&サラ・ボーン)
ラジオ番組を聴いていたら、クリフォード・ブラウン(tp)とサラ・ボーン(vo)の「ララバイ・オブ・バードランド」をやっていました。1954年の録音だそうで、なんと今から70年前のものですがちっとも古びていない新鮮な印象で聴くことができました。初めて聴いたのが40年前だったのでその時点でも30年前だったことになります。

昨年ニューヨークのジャズクラブ「ブルーノート」を訪ねる機会がありました。ブルーノートと言えば、このクリフォード・ブラウンをはじめ、アート・ブレイキー、もホレス・シルヴァー、ハンク・モブレー、ジミー・スミス、リー・モーガン、ルー・ドナルドソン、ハービー・ハンコック、ウェイン・ショーター、トニー・ウィリアムス、オーネット・コールマンなどが演奏したことがあるということのため、そのような系統のものを期待していましたが、今はそういうのは流行っていないのか、ジャズそのものがどんどん進化しているためか、この夜の演奏はラップのようなそうでないような、あまりすんなりとは音が耳に入っては来ませんでした。
ジャズの良い演奏を聴くなら、かならずしも最新のものでなくても、こういう古い録音でも十分新鮮な感じを受け取ることができるなあと独り言ちています。これは別にジャズに限らず、クラシックでも落語でも通じることかも知れません。(単に古いものを懐かしむ私自身の高齢化の進行か、はたまた成長がストップしただけのことなのかも知れませんが)
