司馬遼太郎さんの『坂の上の雲』を読みました。
そして、10年ほど前にNHKのテレビでやっていたドラマもようやく“追い見”しています。
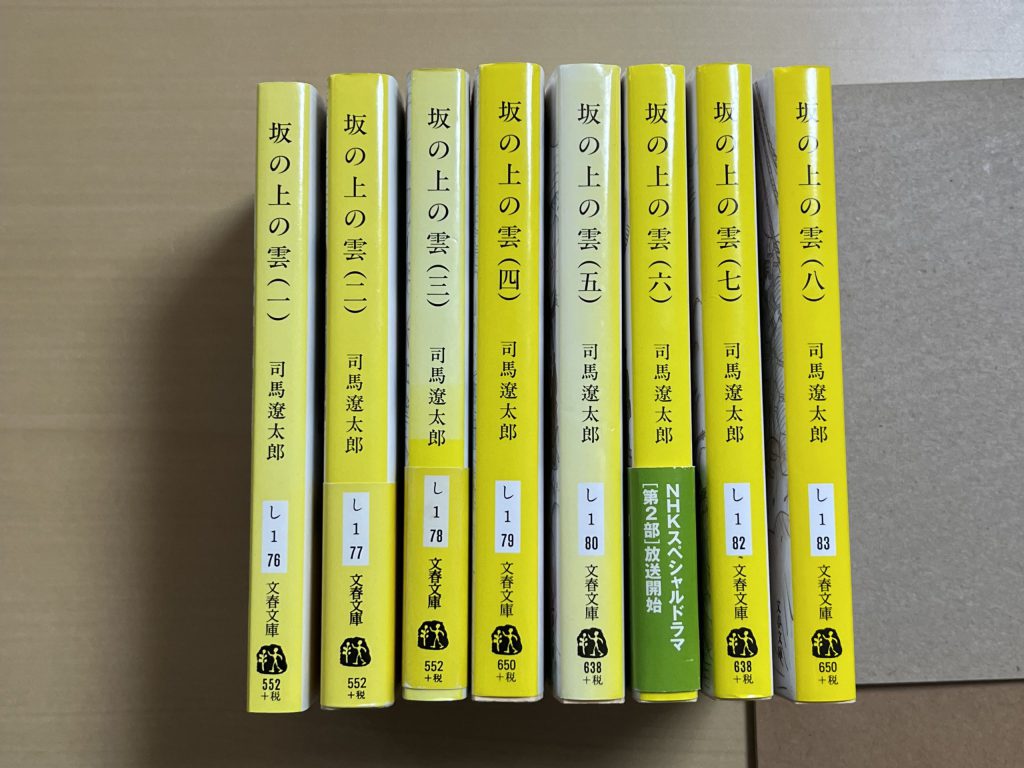
4年前にある先輩から経営戦略の参考になるので是非読んだら良いと言われており、チャレンジしたのですが、文庫版3冊目の途中で挫折してしまいました。その後昨年から再度挑戦しましたが、やはり3冊目の途中から読むペースが遅くなりました。何が原因か。一つは、正岡子規の命が燃え尽きるのを見たくないという気持ちが働いたのと、もう一つは、そこを越えた次に出てきた戦闘シーンの多さ、人が砲撃にあって沢山亡くなる、これでもかこれでもかというくらいに「突撃」と「殲滅(される)」の繰り返しに、この小説はいったいなんなんだろう? 司馬さんはなんのためにこのように人が次々と勝算のない突撃で意味もなく亡くなり続けるシーンを描いているのだろう? という疑問がわいてきたこと、だったのではなかろうかと思います。(指揮官たちは「意味もなく」とは考えていなかったと思いますが)
司馬文学の金字塔と言われているくらいの『坂の上の雲』は日本が明治維新を経て、さらに瑞々しく希望あふれた豊かな国になっていく道程を描いたものだろうと勝手な想像をしていました。もちろん日露戦争を描いたものであることは承知していました。実は私の誕生日は、戦前は陸軍記念日と言われていたそうです。日本陸軍の生みの親たる大村益次郎さんの誕生日だったと聞いたことがあり、それに因んでかと思っていましたが、どうやら日露戦争・奉天会戦における戦勝記念日だったことから来ているようです。そのため、どんな戦争だったのかという関心もありました。経営戦略の勉強という観点とは別の意味でも読書欲をかきたてられた次第です。
しかしタイトルにある「坂の上の雲」など私の眼には一向に見えてきませんでした。そして、日本という国を俯瞰するのみならず、戦いの相手だったロシアについてもじっくりと丁寧に、特にバルチック艦隊が母港を出て喜望峰を回り、マダガスカルで無為な時間を過ごし、東南アジア付近では疑心暗鬼になり、といったことを実に丁寧に読む者がその情景が目に浮かぶような丁寧さで書いてくれています。組織の統率、指揮官はいかにあるべきかということを、彼我の対比も含め、描いています。単に日本がどう、ロシアがどうという単純比較ではなく、日本の軍隊における(組織の意思決定の仕方・データの扱い方などの)良い点、だめな点、ロシア側の良い点、だめな点もかなり客観的に描かれていたと思います。組織論といっても、人それぞれに着目した、だれそれはこの時こういう発言をした、といった感じですが、一方で民族的な習性といったような、やや曖昧なことに原因を求めるような記述もありましたが。
私の勝手な想像とは裏腹に、司馬さんの『坂の上の雲」は、決して希望あふれた豊かな国になっていく道程というよりは、太平洋戦争での滅亡の原因がこの成功体験の中にあった、ということを説明しようとしたものではなかったか、という気もします。特に陸軍に対しては「滅亡」という言い回しを何度か使っています。そして、司馬さんがこの小説の連載を始めた1968年といえば、太平洋戦争終結からまだ23年しか経っておらず、当事者も大勢生存していた時期であり、日露戦争の従軍者もおられたとのことであり、色々書きにくいこともあったのではないかと想像します。
いったいなにが楽しくてこんなこと(突撃と殲滅の延々たる繰り返し)を書き連ねているのだろう?と思っていました。しかし司馬さんは相当つらい思いをしながら書いていたんではなかろうか、と最終巻のあとがきを読んで思いました。司馬さんは「あとがき」の最後にこんなことをさらりと書いています。「私の四十代はこの作品の世界を調べたり書いたりすることで消えてしまった。この十年間、なるべく人に会わない生活をした。友人知己や世間に生活人として欠礼することが多かった。古い仲間の何人かが、その欠礼について私に皮肉をいった。これはこたえた。(p358)」
ただ司馬さんの作品の年譜を見ると、この十年ほどの時期に『竜馬がゆく』『『燃えよ剣』『尻啖え孫市』『功名が辻』『城をとる話』『国盗り物語』『俄 浪華遊侠伝』『関ヶ原』『北斗の人』『十一番目の志士』『最後の将軍』『殉死』『夏草の賦』『新史太閤記』『義経』『峠』『宮本武蔵』など、幕末や戦国時代のものを中心に、その後の大河ドラマの原作になった大作も沢山書いておられ、とてもエネルギッシュに作品群を世に出しておられ、四十代を日露戦争のあとなぜだけで浪費したわけではないということも事実としては押さえておきたいと思います。
さて、司馬遼太郎さんの『坂の上の雲』から自戒としての抜き書きです。
・人間の頭に上下などはない。要点をつかむという能力と、不要不急のものはきりすてるという大胆さだけが問題だ(秋山真之)(文庫版二 p230~231)
・大海図に点々と軍艦のピンがおされている。軍艦が移動するごとにそれがうごく。たれの目にも状況把握が一目瞭然であり、状況さえあきらかであれば、つぎにうつべき手-たとえば艦船の集散、攻撃の目標、燃料弾薬の補給など-がどういう凡庸な、たとえば素人のような参謀でも気がつく。作戦室の全員が、書記ですら、刻々の状況をあたまに入れてそれぞれの分担を処理している。(文庫版二 p252)
⇒見える化の重要性と有効性
・マカロフの統率法は、水兵のはしばしに至るまで自分がなにをしているかを知らしめ、なにをすべきかを悟らしめ、全員に戦略目標を理解させたうえで戦意を盛りあげるというやりかたであった。(文庫版三 p326)
・命令があいまいであることは軍隊指揮において最大の禁物(文庫版四 p261)
⇒軍隊を企業に置き換えて読む
戦略や戦術の型ができると、それをあたかも宗教者が教条をまもるように絶対の原理もしくは方法とし、反復してすこしもふしぎとしない。(文庫版五 p50)
・日本軍の師団参謀たちの頭は開戦一年余ですでに老化し、作戦の「型」ができ、その戦闘形式はつねに「型」をくりかえすだけという運動律がうまれていまっていた。「型」の犠牲はむろん兵士たちであった。(文庫版七 p42)
⇒日本軍を大企業に置き換えて読む
・戦術家が、自由であるべき想像力を一個の固定概念でみずからしばりつづけるということはもっとも警戒すべきこと。情報軽視という日本陸軍のその後の遺伝的欠陥。(文庫版五 p355)
⇒これも陸軍を企業に置き換えて読む
一行動が一目的のみをもたねば戦いには勝てないというのがマハンの戦略理論であった。東郷がこの「目的の単一性」という原則に忠実であったのに対し、ロジェストウェンスキーが二兎を追うためにその行動原理がきわめてあいまいになっていることをマハンは指摘している。(文庫版七 p331)
