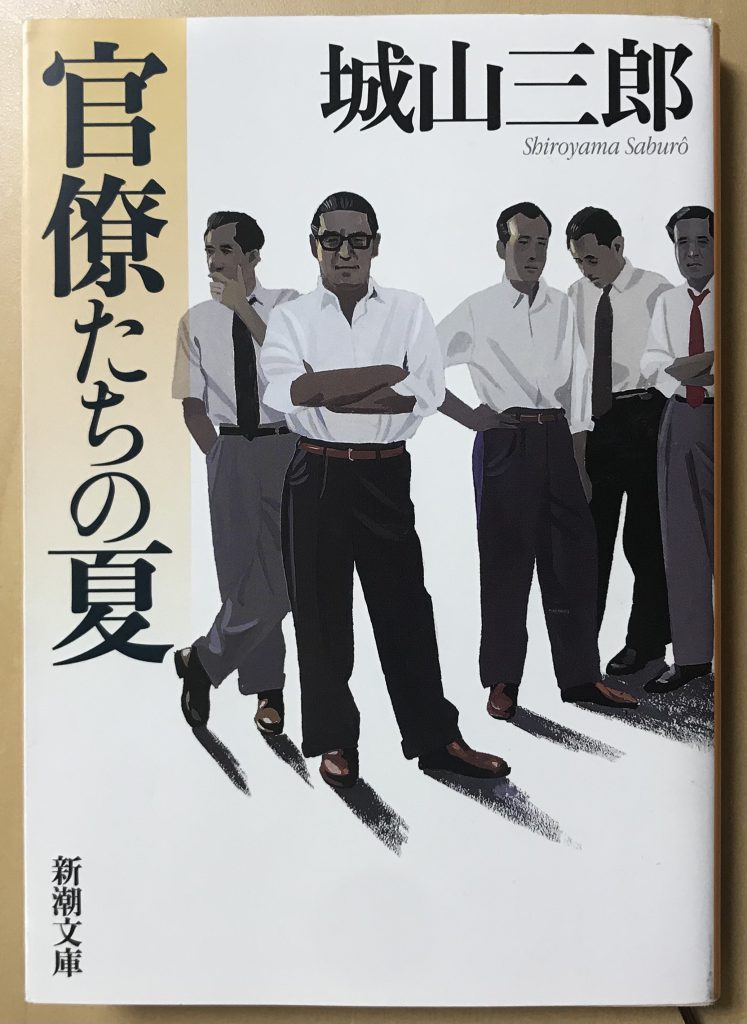(この投稿は、中陳個人の感想であり、歴史上の事実について誤った認識があるかも知れません)
令和2年度第3次補正予算により、経産省から新たに「事業再構築補助金」という補助金が出されました。この事業再構築補助金の申請を考えている事業者さんからの相談に備え、城山三郎さんの『官僚たちの夏」を初めて読みました。
というのは、1960年代、1970年代の頃、日本株式会社と揶揄されるくらいに、日本の官と民とが協力して、軽工業から重化学工業に脱皮し国際競争力を高めていったという歴史があり、今回の事業再構築補助金は、まさにそのような大きな産業構造の転換を目指しているのではないかと感じ、では、当時はちなみにそのような動きがどのように作られていったのかということを小説を通じて知ることができないだろうかと思ったのです。
当時は日米繊維交渉や鉄鋼交渉、自動車交渉など、様々な貿易摩擦が発生し、都度、官民一体となって交渉に当たり、量的な制限を課されつつも、より良いものをより安く提供できるよう技術革新などにも取り組んでいたのであろうと認識しています。そのような様々な動きの中で、経済人でもスター経営者が生まれたり、当時の通産省からはこの小説のモデルと言われる佐橋滋さんや少し下って天谷直弘さん、堺屋太一さんなどスター官僚を輩出していました。
目指すべき産業モデルも米国などに存在していた時代でした。しかし、今は、目指すべき産業モデルがなかなか見当たらず、みんなでGAFAMになれというわけにもいかず、しかし日本の産業構造を変えて、より生産性を向上させていく必要があると、現在の経産省の方々は考えているのではないかと思います。あくまで想像です。60年代70年代は産構審という会議体を通じて官民が協力していたと教わったことがあります。通産省、学者、民間がそうした場を通じて、文字通日本の産業構造をどうするかといったテーマで喧々諤々の議論が交わされていたものと思います。今も産構審は存在し、議論はなさっているようですが、当時とは位置づけが変わっているのか、あまり表に出てきていないような気がします。目指すべき産業構造や産業モデルが見当たらないからなのかも知れません。勝手な想像ですが。
事業再構築補助金では、まず「概要」に「日本経済の構造転換を促す」ことを目的とすると書いてありますが、この重要ポイント、案外見落とされているかも知れません。つまり「経済の構造を変える」ことに寄与しそうな事業に補助金を出す、と冒頭で明言してあるのです。また「公募要領」の審査項目には「リスクの高い、思い切った大胆な事業の再構築を行うものであるか」とあります。これらを総合して考えると、今の経産省が50年前の通産省のように、この1兆円を超える予算を活用して、新たな産業を興し、日本の産業構造をより生産性の高いものにシフトさせたいと考えているように思えてなりません。
さて、件の『官僚たちの夏』、主人公の思いとは裏腹に、肝いりで提案した法律案(特定産業振興臨時措置法案)はロクに審議もされずに廃案となったということでした。企業が自らリスクをとって世界と勝負していくべきとい自由経済論とのせめぎあいで負けたとか、もう官が一緒になってやっていかなければならないほど日本企業はひ弱ではなくなったとか、様々な考え方に敗れたというようなことで、官民一体となって産業構造の転換に取り組んでいたと思っていた私からすれば「あれ?」という感じでした。しかし、どうも、その法律は廃案になったものの、一方で「構造改善を図る企業に政府融資をとりつける体制融資で振興法の精神をある程度具体化した」(本書p316)とあることやIBMに対するコンピュータ業界の合従連衡が功を奏したといったことなど、その後の官民連携のいくばくかの部分は佐橋さんが描いたような道筋を法律とは別のところで進んでいたようです。
法律案の原案には次のようにあったそうです。「経済の変革期に当り、対外競争力を急速に強化するためには、産業再編成により、生産規模の適正化をはかることが必要である。この産業振興のための基準は、政府・産業界・金融界の協調によって定める。政令によって指定された産業は、この振興基準に従って、集中・合併・生産の専門化などの努力をする。金融機関は、この振興基準にそって資金の供給を行う。政府も、政府関係金融機関を通じて資金を補給するとともに、課税について減免措置をとり、また、振興基準による合併などについては、独占禁止法の適用除外とする。」
今回の事業再構築補助金についても、合併などによって新製品等を新市場に売っていくというものも含まれています。中小企業の企業規模を大きくして生産性を上げよという主張は、デービッド・アトキンソンさんの主張にも表れているところであり、今回の補助金にもそういう考え方が反映しているのかも知れません。当時の法案(とその後の動き)と今の補助金、狙いが似ているような気がします。『官僚たちの夏』を読んで、益々その意を強く持ちました。