正岡子規の『病床六尺』を見ていたら子規が死の二週間程前にフランクリンの自叙伝について、文字が小さいことと体力が相当落ちている状態のために「三枚読んではやめ、五枚読んではやめ、苦しみながら」読んだにもかかわらず、「得たところの愉快は非常に大なるもの」で「何とも言はれぬ面白さであった」と書き記していました。子規が死の直前まで前を向いて生きていたことに感銘するとともに、ベンジャミン・フランクリン(1706~1790)という人と真面目に向き合ってみようと思ってこの本を求めました。本をひもとく中でごく最初のあたりのページにこれまで出会ったことのない考え方に触れ、これは面白いと思い、全体的に抜き書きをしてみました。あくまで個人の感想ですが、FBとTwitterで投稿した内容を再録しておきます。なお1902年の今日9月19日は子規の命日とのことです。
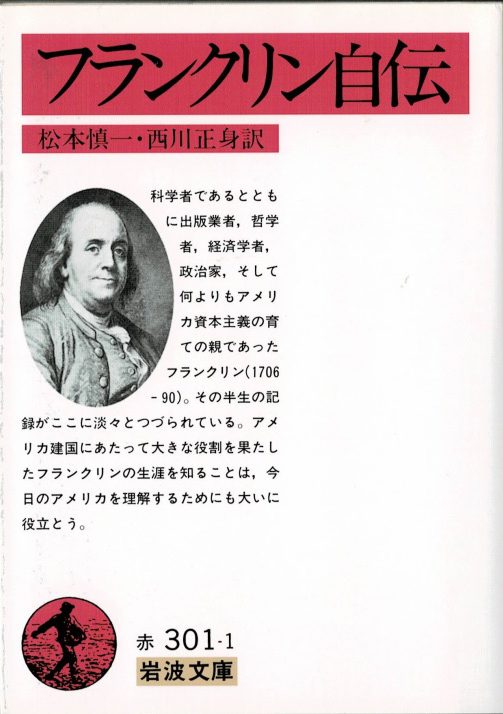
私は他人の自惚れに出逢うといつもなるべくこれを寛大な目で見ることにしている。自惚れというものは、その当人にもまたその関係者にも、しばしば利益をもたらすと信ずるからである。(フランクリン自伝p9 2020.8.15)
議論好きという性質はともすると非常に悪い癖になりやすいもので、この性質を実地に生かすとなると、どうしても人の言うことに反対せねばならず(中略)談話を不快なものにしたり、ぶちこわしたりしたしまうほかに、あるいは友情がえられるかも知れない場合にも不愉快な気持ちを起させ、恐らく敵意をさえ起させる(フランクリン自伝p27 2020.8.16)
私はトライオン式の料理法を習い覚え、馬鈴薯や米を煮たり、早作りプディンをこしらえたり、その他二、三種類の料理ができるようになったので、私の食費として毎週払っている金の半分をくれるなら、自分は自炊をしたいがと兄に申し出た。兄は早速承知した。そこでやってみると、まもなく兄のくれる金が半分は残ることが分かった。この残った金は本を買う足しにした。(フランクリン自伝p30 2020.8.17)
飲食を節するとたいてい頭がはっきりして理解が早くなるもので、そのため私の勉強は大いに進んだ。(フランクリン自伝p31 2020.8.18)
クセノフォンの『ソクラテス追想録』を求めたところ、その中にこの論争法の例が沢山出ていた。私はすっかり感心して、いきなり人の説に反対したり、頑固に自説を主張したりする今までのやり方を止め、この方法に従って謙虚な態度で物を尋ね、物を疑うといった風を装うことにきめた。(フランクリン自伝p32 2020.8.19)
談話の主要な目的は、教えたり教えられたり、人を喜ばせたり説得したりすることにあるのだから、ほとんどきまって人を不快にさせ、反感を惹き起こし、言葉というものがわれわれに与えられた目的、つまり知識なり楽しみなりを与えたり受けたりすることを片端から駄目にしてしまうような、押しの強い高飛車な言い方をして、せっかくの善を為す力を減らしてしまうことがないよう(後略 フランクリン自伝p33 2020.8.20)
人に物を教えようとする時に、押しの強い独断的な言い方で自分の考えを述べたのでは、人は反対しにくい気持になって素直には聞いてくれないだろう。また他人の知識から教えを受けて賢くなりたいというのに、しかも現在の考えを固執するようなことを言っては、議論を好まぬ謙遜で思慮のある人なら、おそらく間違っていてもそのままにしておいて直してはくれないだろう。(フランクリン自伝p33 2020.8.21)
人は金を沢山持っている時よりも少ししか持っていない時のほうが、気前のよいことがあるものだ。多分文なしだと思われるのがいやだからであろう。(フランクリン自伝p47 2020.8.22)
理性のある動物、人間とは、まことに都合のいいものである。したいと思うことなら、何にだって理由を見つけることも、理窟をつけることもできるのだから。(フランクリン自伝p67 2020.8.23)
私は鋳型を考案し、手もとにある活字を打印器に使って鉛に字を打ちこみ、こうしてかなり上手に足りない活字を揃えたものだ。また時にはいろいろなものを彫りもしたし、インキも作れば、店番もしたし、その他何でもやった。つまり、万屋だった(フランクリン自伝p101 2020.8.24)
私は人と人との交渉が真実と誠実と廉直とをもってなされることが、人間生活の幸福にとってもっとも大切だと信じるようになった。(フランクリン自伝p108 2020.8.25)
私は有能な知人の大部分を集めて相互の向上を計る目的でクラブを作り、これをジャントーと名づけて、金曜日の晩を集まりの日にしていた。(中略)会員はすべて順番に倫理・政治ないしは自然科学に関するなんらかの点について少なくとも一つの問題を提出し、仲間の討論にかけることになっていた。(フランクリン自伝p112 2020.8.26)
議論のために議論するとか、相手を言い負かすために議論するとかではなしに、真理探究という真面目な精神で行うことになっており、(中略)議論が喧嘩腰になるのを避けるために、独断的な言い方や真向から反対するといったことは一切禁制となり、それを破る者には小額の罰金を課することにした。(フランクリン自伝p112 2020.8.27)
自分の勤勉ぶりを事こまかに、また無遠慮に述べたてるのは、自慢話をしているように聞こえもしようが、そうではなくて、私の子孫でこれを読む者に、この物語全体を通して勤勉の徳がどのように私に幸いしたかを見て、この徳の効用を悟ってもらいたいからである。(フランクリン自伝p116 2020.8.28)
何かある計画をなしとげるのに周囲の人々の助力を必要とする場合、有益ではあるが、自分たちよりほんのわずかでも有名になりそうだと人が考えやすい計画であったら、自分がその発起人だという風に話を持ち出しては、事はうまく運ばない。(フランクリン自伝p150 2020.8.29)
何かある過ちに陥らぬように用心していると、思いもよらず、他の過ちを犯すことがよくあったし、うっかりしていると習慣がつけこんで来るし、性癖のほうが強くて理性では抑えつけられないこともちょくちょくある始末だった。(フランクリン自伝p156 2020.8.30)
第一 節制 飽くほど食うなかれ。酔うまで飲むなかれ。
第二 沈黙 自他に益なきことを語るなかれ。駄弁を弄するなかれ。
第三 規律 物はすべて所を定めて置くべし。仕事はすべて時を定めてなすべし。
(フランクリン自伝p157 2020.8.31)
第四 決断 なすべきことをなさんと決心すべし。決心したることは必ず実行すべし。
第五 節約 自他に益なきことに金銭を費すなかれ。すなわち、浪費するなかれ。
第六 勤勉 時間を空費するなかれ。つねに何か益あることに従うべし。無用の行いはすべて断つべし。
(フランクリン自伝p158 2020.9.1)
第七 誠実 詐(いつわ)りを用いて人を害するなかれ。心事は無邪気に公正に保つべし。口に出だすこともまた然るべし。
第八 正義 他人の利益を傷つけ、あるいは与うべきを与えずして人に損害を及ぼすべからず。
第九 中庸 極端を避くべし。たとえ不法を受け、憤りに値すと思うとも、激怒を慎むべし。
(フランクリン自伝p158 2020.9.2)
第十 清潔 身体、衣服、住居に不潔を黙認すべからず。
第十一 平静 小事、日常茶飯事、または避けがたき出来事に平静を失うなかれ。
第十二 純潔 (前略)これに耽りて頭脳を鈍らせ、身体を弱め、または自他の平安ないし信用を傷つけるがごときことあるべからず。
(フランクリン自伝p158 2020.9.3)
第十三 謙譲 イエスおよびソクラテスに見習うべし
私はこれらの徳がみな習慣になるようにしたいと思ったので、同時に全部を狙って注意を散漫にさせるようなことはしないで、一定の期間どれか一つに注意を集中させ、その徳が修得できたら、その時初めて他の徳に移り、こうして十三の徳を次々に身につけるようにして行ったほうがよいと考えた。(フランクリン自伝p159 2020.9.4)
古くからの習慣のたえまない誘引や、不断の誘惑の力に対してつねに警戒を怠らず、用心をつづけるには、頭脳の冷静と明晰とが必要であるが、それをうるにはこの徳が役立つ。(フランクリン自伝p159 2020.9.5)
知識は、人と談話する場合でも、舌の力よりはむしろ耳の力によってえられると考えたので、下らない仲間に好かれるようになるにすぎない無駄口や地口や冗談などに耽る習慣(それが私の癖になりかけていた)を直したいと願った。そこで沈黙の徳を第二においた。(フランクリン自伝p159 2020.9.6)
多くの人の場合、(中略)私が用いたような方法を知らないために、このほかの徳不徳の点でよい習慣を身につけ、悪い習慣を破ることの困難に出会うと、これと戦うことを断念し、「所々しか光っていない斧が一番いい」と結論を下してしまう。(フランクリン自伝p168 2020.9.7)
私が作った徳目の表は最初は十二項目しかなかった。ところが、クェーカー教徒の友人が親切に言ってくれたのだが、私は一般に高慢だと思われていて、その高慢なところが談話のさいにもたびたび出て来る。何か議論するとなると、自分のほうが正しいというだけでは気がすまないで、おっかぶせるような、むしろ不遜と言ってもいい態度があるとのことで(中略)、できればこれを直したいものだと考え、謙譲の徳を表に加え、その語に広い意味を持たせた。(フランクリン自伝p172 2020.9.8)
会計の知識があれば、悪賢い男に欺されて損をすることもなくてすみ、子供が一人前になってその後をついでやれるようになるまで、従来の取引関係をつづけて恐らく利益のある商売を営むこともでき、けっきょくいつまでも一家の利益、繁昌のもとになる。(フランクリン自伝p183 2020.9.9)
他人の敵意のある行動を恨んでこれに返報し、敵対行動を続けるよりも、考え深くそれを取りのけるようにするほうがずっと得なのである。(フランクリン自伝p190 2020.9.10)
組合経営(※)というものは喧嘩別れになりがちのものであるが、私の場合は幸いなことにすべて円満に経営され、円満に終わったのである。これは私が予め用心して、喧嘩の種が一つもないように、各当事者がなさなければならぬこと、ないしはしてほしいことを残らず明瞭に契約書中で取り決めておいたのによるところが多いと思う。(中略)契約当時には当事者同士がお互にどんなに尊敬と信頼を持っていたにしても、仕事の上の心配や気苦労などが不公平だという考えが起ると、それにつれてちょっとした妬み心や嫌気が頭をもたげ、そんなことから友情にひびが入り、せっかくの組合関係もだめになって、訴訟沙汰やその他の面白くない結果に終わることがよくある。(フランクリン自伝p203 2020.9.11)※投稿者注:今日私たちが認識している「組合」と同義ではない可能性があります。(共同代表の株式会社みたいなものかも)
あらゆる他の宗派は、真理はすべて自分にあるものと考え、自分と異るものがあれば、異るほうが誤っていると考えている。それはちょうど霧の日に道を行く旅人に似ている。少し先を行く人々も、後から来る人々も、また左右の野原にいる人々も、すべて彼には霧に包まれているように見え、自分も他の人々と同様やはり霧に包まれているのに、ただ自分の周りだけが明るく見えると思いがちなものである。(フランクリン自伝p216 2020.9.12)
人間の幸福というものは、時たま起るすばらしい幸運よりも、日々起って来る些細な便宜から生れるものである。(フランクリン自伝p237 2020.9.13)
私が見てきたところでは、理窟屋で反対好きで言葉争いに耽るような連中は、多くは仕事の方がうまく行かないようだ。彼らは勝つことはある。しかし、勝利よりも役に立つ、人の好意というものをうることは決してないのだ。(フランクリン自伝p244 2020.9.14)
怠けているところを自分自身に見つけられるのを恥じよ。(中略)なさねばならぬことが山ほどある以上、夜が明けるとともに起き出すことです。太陽に見下ろされて「恥知らず。ここに横たわる」と言われるな。(フランクリン自伝p323 2020.9.15)
あなたの力が足りないという場合も、あるいはおありのことでしょう。ですが、そうであったにしても、着実に仕事をおつづけになることです。そうなされば、きまって大きな効果が上るものなのです。(フランクリン自伝p324 2020.9.16)
力は勇気ある者に、至上の幸福は有徳の士に、学問は勉強家に、富は用心深い者に授かる。(フランクリン自伝p326 2020.9.17)
つねに注意深く、用意周到であれ、どのような些細な事柄についても。時に、わずかな怠りでも、大きな災いを招きかねない。釘が一本ぬけて蹄鉄がとれ、蹄鉄がとれて馬が倒れ、馬が倒れて乗っていた者が命を落とした。(フランクリン自伝p327 2020.9.18)
儲けはいっときのことで定めないものであるのに、出銭は生涯つきまとう変りないものですし、「かまど二つを築くは易く、かまど一つに火を絶やさぬは難し」です。(フランクリン自伝p336 2020.9.19)
経験の経営する学校は月謝が高い(フランクリン自伝p337 2020.9.19)
番外編①(『フランクリン自伝』の翻訳者・松本慎一氏による昭和12年5月の解説より)
フランクリン自伝は、明治中期以来わが国の青年の愛読書(フランクリン自伝p352 2020.9.19)
フランクリン自伝は世界自叙伝文学中の古典としてきわめて広く読まれ、刊行後約一世紀の間に、英米のみにても版を重ねること幾十百版に及び、今日においてもその需要を絶たない(フランクリン自伝p353 2020.9.19)
彼が書き終えたのは計画の半分ぐらいに止まり、その活動のもっとも花々しかった晩年の三十年間には及びことができなかった。(フランクリン自伝p354 2020.9.19)
カール・マルクスは新大陸における最初の偉大な経済学者としてフランクリンに敬意を払っている。(フランクリン自伝p355 2020.9.19)
フランクリンはワシントンよりもリンカンよりも、より多くアメリカ資本主義の育ての親である。アメリカを理解するためには、フランクリンを知ることが、少なくとも甚だ有益だと思われる。(フランクリン自伝p356 2020.9.19)
番外編②(『フランクリン自伝』の翻訳者・西川正身氏による昭和31年8月のあとがきより)
フランクリンの自伝は、単に「優れた人生教科書」であるだけでなく、「アメリカ資本主義の揺籃史」として、アメリカ研究者にとって必読の書なのである。(フランクリン自伝p363 2020.9.19)
フランクリンは「アメリカ資本主義の育ての親」であったが、フランクリンをその面から見て行こうとする者にとって、マックス・ウェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』は必読の書である。同書には、「若い商人に与える忠告」をはじめ、フランクリンからの引用、彼への言及がそこここに見当たる。(フランクリン自伝p367 2020.9.19)
なお、この本を読んで初めて、当時のアメリカがヨーロッパの植民地であり、植民地であったということは領主様がいてヨーロッパ本国から色々課税指示が来て、でも現地の人たちは議会を作って抵抗したり、その一方で先住民と戦争をしたり先住民の人たちに自分たちの代理戦争をさせたりという、アメリカ独立前の人々の営みを、知識として知ることができました。
