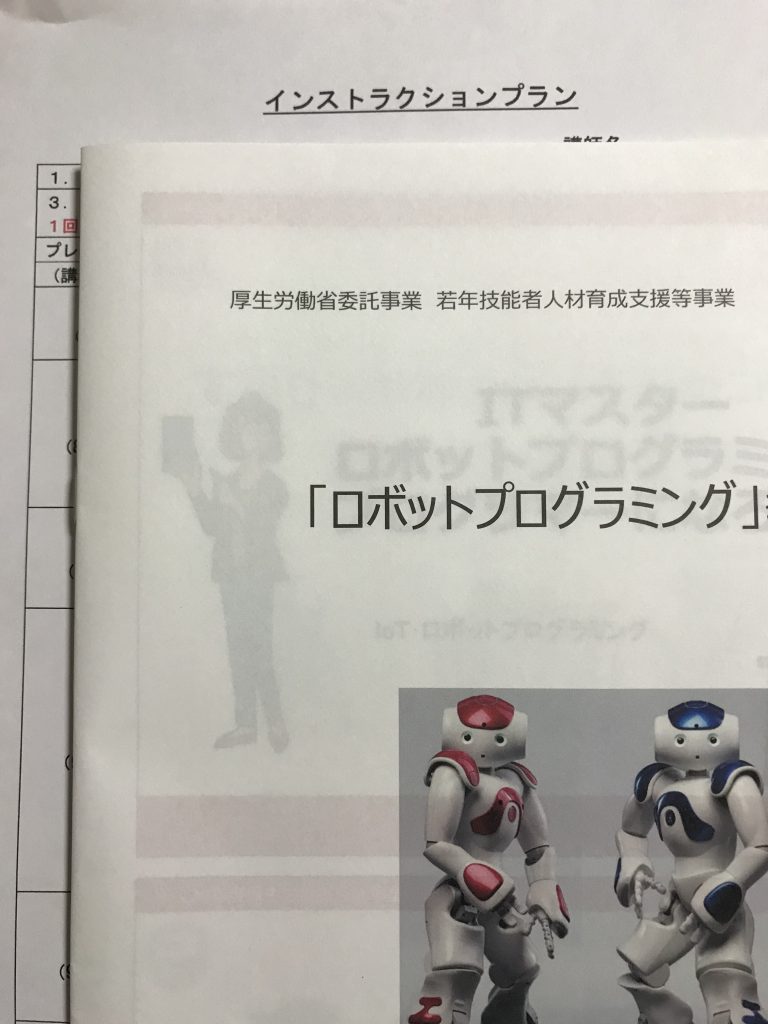昨年何度か長野市で仕事をする機会がありました。行く都度目についたのは、横断歩道で人が渡ろうかとしていると、そこに差し掛かった車の7、8割が一時停止をしているということです。初めはさほど気にもならなかったのですが、タクシーもバスも一般乗用車も関係なく皆さん一旦停止をなさる。しかもその道路は長野駅から善光寺へ伸びる、片側一車線ではあるもののメインストリートの一つで、路線バスや観光客を乗せたタクシーなどがビュンビュン通る道路です。私も何度も車が止まってくれました。これ、富山ではまず見られない光景です。
善光寺のお膝元だからだろうか、歩行者に優しい人たちだなあと長野市のドライバーの「マナー」の良さに感動していた矢先、先だって自動車運転免許センターで講習を受ける機会があり、そこで驚くべき調査結果を聞きました。
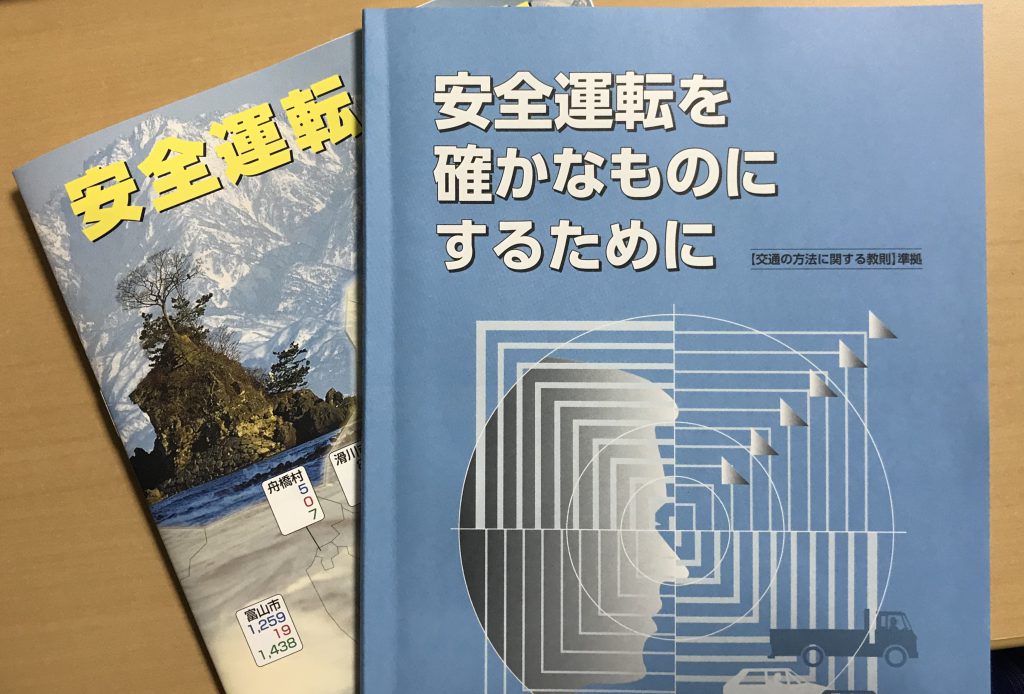
それは、信号機のない横断歩道を歩行者が横断しようとしている場合に一時停止する車がどれだけあるかを調べたJAFの調査結果です。もちろん全車ではなくサンプルではありますが。ちなみに、信号機のない横断歩道を歩行者が横断しようとしている場合、クルマは一時停止しなければならないというのは、交通法規であり、違反した場合、それが「横断歩行者等妨害等」の認定をされると2点減点となります。そうです、「マナー」ではなく「交通法規」なのです。
調査結果では、我が富山県は全都道府県中44位という情けない結果。5.3%しか止まってくれないということでした。実際体感的にはそのくらいだろうと思います。私の家族が、ある時横断歩道を渡ろうとしていた人がいたため、停止線で一時停止をしたところ、後続車に追突され車が大破、全損(幸い家人にはケガなし)という事故に巻き込まれたことがあります。後続車のドライバーはハンドルを握りアクセルを踏んだ状態で、スマホとにらめっこをしており、横断歩道の手前で車が止まるなんて想像しておらず、そのままのスピードで進行した、まさか先行車がそこで止まるなんて、ということでした。(当然ブレーキランプは・・・ドライバーが前を見ていれば目に入ったはずですが)
誠に情けない我が富山県に対して、くだんの長野は、なんと68.6%。堂々の一位です。それでも7割ということで、法律違反をしている車が3割あることはあるのですが。しかし、歩行者が横断歩道を渡ろうという時にそれほど恐れを抱かずに横断歩道に足を踏み入れることができるし、ドライバーも横断歩道に差し掛かる際には、そこを渡ろうとする人がいるかも、という前提で若干スピードダウンして通ろうとします。実際長野市で見た多くの車両がそうでした。この違い、一体なんなんでしょう。
ちなみに、この調査は2016年から毎年JAFが行っているもの(2019年調査結果はここに掲載されています⇒
https://jaf.or.jp/common/safety-drive/library/survey-report/2019-crosswalk )だそうで、当然毎年パーセンテージも順位も異なりますが、私たち富山の人はもう少しちゃんと交通法規を守らなくてはならないのではないだろうかと真剣に考えさせられました。家族でもよく話し合いをしようと思います。