新規事業に関する政策が色々打ち出されています。
魚津市でも創業や新規ビジネスを支援すべく「うおづビジネスプランコンテスト」という催しが初めて開催されました。
魚津市になんからの関わりのあるビジネスプランを募集するというもので、結構短い募集期間だったように思いますが、47件もの応募があったそうです。
今日はその中から厳選された8件のプレゼン大会でした。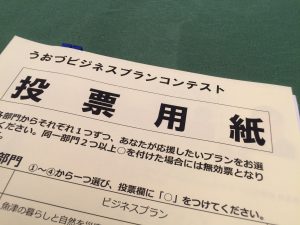
プレゼンに先だって経済評論家の森永卓郎さんの基調講演が行われました。
有名なライザップでの減量経験談で会場を沸かせた後は、本業の経済論をひとしきり。
いくつか私なりに選んだキーワードを記しておきます。
①1960年から1975年までの高度経済成長時代
②この時代に夫婦に子ども2人の計4人という「標準家族モデル」が作られた。
③〇〇の動きに乗れば必ず儲かる、といううたい文句はこの高度経済成長時代の呪縛による引っ掛けであり、現代の多様化した時代にはありえない。
④標準家族モデルでは、みんな同じライフスタイルでありみんな欲しいものは同じだった。だから隣がカラーテレビを買えばうちも、となったし、戦後のベビーブーム世代が一斉に大人になったので大量生産・大量消費が起こりえた、奇跡の時代だった。(一部筆者補足)
⑤2015年10月の国勢調査では30代前半男性の過半数が非婚。
⑥女性から見た男性の4区分。イケメン、フツメン、ブサメン、キモメン・・・後ろ二つはちょっとひどいなあと思いますが、我々男組も女性に対してコンテストだのランキングだのタイプ分けだのすることを思えば、これで平等ってことかも知れません。しかし話術が巧みだったりお笑いができれば後者もイケるため、森永さん曰く「変な人が増えてきた」ということです。
⑦すなわち多様化の時代ということ。
⑧ここで話題は急転直下。日本が目指すべき経済社会はイタリア型という主張。(色々批判はあるそうですが森永さんはこの主張を10年来持ち続けているとのこと)
⑨イタリア企業の特徴その1。現場への権限移譲による現場の裁量の自由度とスピーディーな意思決定。
トップが絶対権限でデザイナーと販路と商品を決める。後は現場任せ。トップは口を出さない。たとえばフェンディは年間1500もの新商品を出している。上司がこまごまと口を出さないからこれだけのことがスピード感を持ってできる。おっさんがごちゃごちゃ言って社員の感性を評価せず、評価は市場に委ねる。その中でヒットしたものはどんどん売る。市場に出して売れなければ廃番にする。だからモノマネの国も追いつけない。だから真似されない。
社員はどうやったら効率が良くなるかをいつも真剣に考えている。その改革案・改善策はどんどん自分で実行できる。上申不要、会議もない。残業はなく夏休みは1か月以上取得するが、それは働かないのではなく一年を11か月で考えて段取りし、効率改善を必死に考えている結果である。それでいて一人当たりGDPは日本とほぼ同じ。高い経済成長を100年以上継続している。(100年前はアルゼンチンに出稼ぎに行くいくらいに経済レベルは低かった)
価格競争に陥るコモディティ商品よりも付加価値の高いアート商品を考え具現化している。例えば百均でも売っているトイレブラシでも本物の植木鉢っぽくすることで数千円の値段で売れる。
⑩アートとは、岡本太郎氏の定義によれば「見た瞬間、なんだこりゃ!?と思うが、一歩離れると気になってしょうがないもの。よって単に美しいものはアートにはなりようがない」というものだと。
⑪イタリア企業の特徴その2。どんな場面に遭遇しても決して暗くならない。
だめになる会社の社長は社員に対して経営環境の厳しさとそれに打ち克つための頑張りを求めるばかり。経営環境が厳しいことなど、社員もわかっている。そこへまた悲壮感を漂わせるようなメッセージを発すると、いわば傷口に塩を塗りつけるようなことになる。社員はやる気が失せる。そして会社は社長が宣言したとおり厳しさの中でだめになっていく。・・・森永さん25年間の中小企業研究から発見した「法則」だそうです。
対してイタリアの経営者の社員向けメッセージのポイントは3つだけ。歌おう、食べよう、恋をしよう。かの国の人たちはリーマンショックのような大変な経済危機が訪れても切り替えが早くうまいそうです。だめなことは引きずらない。起こったことそれ自体は取り戻しようがない。「次行こ!」ということです。
そういえば、誰かが、植木等のノリで日本経済を再活性化させようではないか、と言っていたような気がします。
もしかすると森永さんだったかも。
良い悪い、好き嫌いはあると思いますが、私自身企業経営の支援をしていく上で、色々参考になる点があった講演でした。
さて、ビジネスプランコンテストの結果は、最優秀賞1名、優秀賞2名、特別賞2名が選出されました。お世話をなさった魚津市及び魚津商工会議所並びに㈱アシステムの関係者の皆さん、大変素晴らしいイベントだったと思います。心から敬意を表したいと思います。
次回に向けたキーワードとして審査委員長の中尾哲雄さんが「交流」「組合せ」「失敗を恐れずに」ということを講評で仰っていました。
今回のイベントを嚆矢として、魚津市、さらには富山県東部地域が元気になっていくよう、私もなにがしかの貢献ができればと思っています。差し当たりは地元で行われる創業スクールのお手伝いなどさせていただき、やる気のある人たちの勇気づけ・理論武装・プレゼン支援などができればと思います。


