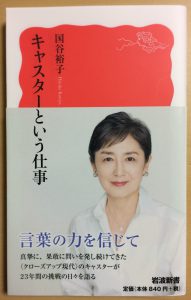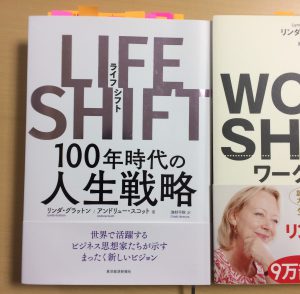先日、NHK-TV「クローズアップ現代」のキャスターを23年間務められた国谷裕子さんのラジオインタビューが放送されていました。http://www.tbsradio.jp/117978(←こちらのサイトでしばらくは音声が聴けるはずです)
ずっと以前は夜9時半頃からやっており、その頃は帰宅して食事をする時間と重なっていたのでよく見ていました。一つのテーマをしっかり掘り下げる時事情報番組であり、毎日違う話題をよくここまで深く取材して対応しておられるなと、スタッフは複数クルーで構成されていたのでしょうけど、キャスター自身は国谷裕子さん一人だったので、毎回感心して見ていました。
いつの間にかその時間帯での放送がされなくなっていたため、番組自体がなくなっていたものと思っていましたが、昨年の騒ぎで継続していたことを知りました。
私から見た「クロ現」での国谷裕子さんのイメージは、公共放送のしっかり者のキャスターという感じでしたが、このインタビューを聞いて意外な事実を知りました。
小学校5年生までしか日本の学校での勉強をしていなかったため、アメリカの大学を卒業した時点で日本のことは全然知らなかった、と仰っていました。一旦外資系の日本企業に就職したものの、マーケティングはどうも自分の居場所ではないと感じ、10か月で退職、自分探しのためにバックパックをかついでたった一人で世界一周旅行に出かけた。その後NHKの海外からのリポーターのような仕事をしたが、あまりうまくいかず半年で降板、降板を繰り返し、自信喪失。日本人でありながら日本のことはわからないし、日本語の扱いも不自由で、キャスターとしても役に立たず、自分のアイデンティティも確立できず・・・というコンプレックスにさいなまれていた時期もあったようです。(ラジオを聞いての私の印象も含みます)
あの国谷裕子さんにしてそうだったのかと、大変驚き、またその心労に思いが至って涙が出ました。と同時に素の国谷裕子さんの飾らない語り口に触れ、改めて好感が持てました。
その文脈からすると、その後の「クロ現」に出ておられた時期も、日本ってどんな国なのか、日本の人々はこの事案をどう捉えているのか、などのテーマを持ちつつの、自分探しの旅をずっとなさっていたのではないかと感じました。
と同時に、この人の真摯な姿勢に改めて感動を覚えました。
フェアネス=公平さとは何か。
どんな人にも聞くべきことを聞くことがフェアネスである、と国谷裕子さんは言っていました。国民の多くが知りたいと思っているであろうことを聞くこと、そうやってものごとの背景にあった真相へ近づいていく。この人のストレートかつ鋭いインタビューの背後には(放送時間の短さという制約ももちろんですが)、日本のことをよく知らないからもっと知りたいという若い頃のトラウマが無意識のうちにあったのかも知れません。もちろん、相当しっかり勉強して毎回の番組に臨んでおられたことは当然のことであり、素人が「知らないから教えて」というお仕事ぶりでなかったことは明らかです。
「クロ現」を離れてはや一年、もとよりNHK職員ではなくフリーだったそうですが、より自由な立場になり、日本を代表するインタビュアー、ジャーナリストとして今後益々活躍されるよう楽しみにしています。この本ももう一回読んでみなきゃ。