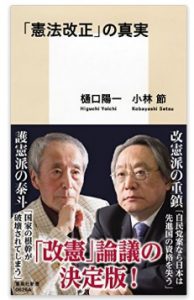本日、おかげさまで交流分析入門講座を開催することができました。
インストラクターの資格取得を目指して丸三年。
最初は色んなことがブツ切りに見えてなんだかよくわかりませんでしたが、諸先輩のお導きのおかげで、学習を進めるにつれ少しずつバラバラの知識が結びついて、実生活や実社会にも活用できるようになってきたような気がします。
今日は、魚津商工会議所さんでの初インストラクターを務めさせていただきました。
なにぶん駆け出しですので、これからさらに学習を進めて行かねばと思っています。
そんな私にとって、人様に交流分析のことをお伝えすることができるのは、何よりも自分自身の勉強になります。
今日一緒に登壇してもらった先輩インストラクターの話の内容、事前に準備する時の自身の学習、参加された方々からの質問、一つひとつが自分にとって新鮮な気づきになります。
将来的には若い方々に早い時期に学んでいただき、自分の人生のかじ取りを自信をもって行っていただけるよう貢献したいと思いますし、企業などの組織においても幹部と従業員の方々に学んでいただき、思いやりと正のエネルギーに満ちたチーム作りができるようお手伝いしていきたいと思っています。
月別アーカイブ: 2016年5月
小山昇さんの『1日36万円のかばん持ち』
株式会社武蔵野の社長ということで本を何冊も上梓されている小山昇さんの最新刊です。
忙しい社長業の傍ら、よくこんなに沢山本を出せるもんだと感心します。
それでも毎週日曜日はきっちり休暇を取っておられるようだし、睡眠時間もきっちり7時間以上とっておられるとのこと。よほど高効率で仕事をなさっている。それこそ秒単位のスケジュールだし、電車に乗る時も降りた後の移動行程と移動時間を考えながら乗るという徹底ぶりです。
さてこの本は、小山さんの思考・行動をそばでかばん持ちをしながらつぶさに体感し、その経験を自分自身の経営に活かすために、1日36万円×3日=108万円の授業料を払ってかばん持ちを名乗り出た色々な会社の経営者の感想などを基に、小山さん自身が編集した実践的経営指南書です。
副題には「三流が一流に変わる40の心得」とあり、このプロセスから出てきた小山流経営哲学が40項目にわたって実例とともに書いてあります。
私自身は人材育成に関心があるため、<心得16 離職率を下げたければ、「1日1時間以上」社員をほめなさい>や<心得22 ストレスに負けない社員をつくるたった「2つ」のこと>などを特に興味深く読ませていただきました。
その他にも、キャッシュフロー経営の重要性について書かれた部分や金融機関との効果的な付き合い方、幹部社員のうまい使い方、など、熟練の経営者ならではの智慧がふんだんに盛り込まれていました。
href=”http://teamwakuwaku.com/blogdb/wp-content/uploads/2016/05/小山昇.jpg”>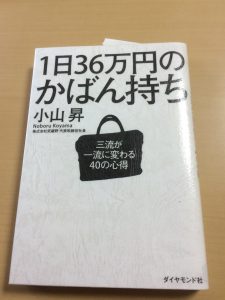
樋口陽一さんと小林節さんの『「憲法改正」の真実』
昨日は憲法記念日ということもあって、新刊の本書を紐解きました。
憲法っていうのは色々な法律の親玉のようなものだと漠然と思っていました。
しかし、確かにその側面はあるものの(あらゆる法律は憲法に反してはならないので)、それ以上に大事なことは、憲法と法律は相当異なった役割を持っているということでした。(憲法は国民の権利を守るために権力が暴走しないように権力を縛る、法律は憲法の範囲内で国民を縛る)
そういう憲法の基本的な役割を本書を読んで初めて理解できたような気がします。
中でも、個人が生まれながらにして基本的な人権を持っているという、私たちの憲法に書かれている人類の普遍的な価値観は、これからも大事にしていきたいものです。
この価値観は、交流分析の哲学で言うところの、①人は誰でもOKである。②人は誰もが考える能力を持っている。③人は誰でも自分の運命を自分で決め、そしてその決定はいつでも変えることができる。という個人の尊厳を大事にする考え方と極めて共通しているようにも感じます。
小宮一慶さんに刺激を受けて、松下幸之助さんの本
昨年、経営コンサルタントの小宮一慶さんが松下幸之助氏に関する本を出されました。
小宮さんによると毎晩幸之助氏の本をひもとき、自分の立ち位置や行為の指針として振返っておられるそうです。
仕事をしていく上での勇気も沢山いただいた、といったようなことをあるラジオ番組で語っておられました。
松下幸之助氏は経営者として偉大な人物ですから、経営者の方々にとっては色々参考になることが多いのだろうと思いますが、小宮さんのような経営コンサルタントにとっても(彼も会社経営に携わっておられますが)良い書物なのだろうなあ、と思い、同業の私もこれからの生き方・仕事への心構えの参考にしようと改めて幸之助さんの本『道をひらく』を求めました。
開いてびっくり。
最初にパラパラっと開いたページに、いきなり「病を味わう」というタイトルの文章が目に入りました。
これって今から悪い細胞たちと闘っていくための(あるいは付き合っていくための)心構えを、幸之助さんが私に諭し聞かせてくれようとしているのではなかろうかと感じました。まさにセレンディピティという感じです。
参考に転載させてもらいます。
「病気になってそれがなおって、なおって息災を喜ぶうちにまた病気になって、ともかくも一切病気なしの人生というものは、なかなか望みえない。軽重のちがいはあれ、人はその一生に何回か病の床に臥すのである。
五回の人もあろう。十回の人もあろう。あるいは二十回、三十回の人もあるかもしれない。親の心配に包まれた幼い時の病から、不安と焦燥に悶々とする明け暮れに至るまで、人はいくたびか病の峠を越えてゆく。
だがしかし、人間にとって所詮死は一回。あとにも先にも一回きり。とすれば、何回病気をしようとも、死につながる病というのも一回きり。あとの何回かは、これもまた人生の一つの試練と観じられようか。
いつの時の病が死につながるのか、それは寿命にまかすとして、こんどの病もまた人生の一つの試練なりと観ずれば、そこにまたおのずから心もひらけ、医薬の効果も、さらにこれが生かされて、回復への道も早まるであろう。
病を味わう心を養いたいのである。そして病を大事に大切に養いたいのである。」
ということで、私も病気のことはお医者さんたちにお任せすることにして、自分自身は次の仕事への行動計画や遊びのことなどに想をめぐらせようと思っています。いきなりいい文章に出会えました。これからも座右の書としていこうと思います。幸之助さん、小宮さん、ありがとうございます。
黒田邦雄さんの『裸のマハ』(映画脚本より)
以前どこかで<面白い映画だ>と聞いたような記憶がかすかに残っていました。たまたま手に入ったので読んでみました。
映画の脚本を基にして黒田邦雄さんという人が著した本です。
一人の女性を描いた肖像画。
「裸のマハ」というのは後世につけられた名前だとか。
絵は裸体のものと衣服を着用したもので同じポーズのものが2種類あり、絵が描かれた18世紀末は女性の裸体の絵などは極めて不道徳であり、唯一ベラスケスが描いた「鏡のヴィーナス」という後ろから裸像を描いたものぐらいで、正面から描いたものなどなかったそうです。
そのため絵の依頼主であるスペインの宰相マヌエル・デ・ゴドイは衣服を着た絵との2枚を制作させ、額縁の中に二重に入れておき、着衣のものを表側に、裸体のものをその後ろに配置し、自分が見たい時だけ着衣の絵をスライドさせて抜き取って見られるようにしていたとのことです。
絵を描いたのは、かのゴヤ。
ゴヤとゴドイは大変仲が良かったそうです。
しかし「マハ」という人物が誰なのか、実際のところよくわからない。
ゴドイという依頼主は当時の王妃マリア・ルイーサの寵愛を受けて25歳の若さで宰相になった元近衛兵。彼は王妃だけではなく貴族の公爵夫人とも深い間柄にあり、しかも奥さんがいて、さらには愛人までがいたという人物。王妃と公爵夫人の間を3日がかりで馬を駆けて往復していたというから相当タフな人ですが、一体いつ政治をしていたのか・・・。
ゴドイが描かせた「マハ」はどの女性だったのか、そして権力と愛をめぐっての争いの最中で毒によって命を落とす女性、殺人か事故か自殺か。宮廷を舞台に幾人もの思惑やら愛憎やら事件やらが複雑に入り乱れ、謎が謎を呼ぶという展開です。
史実を基にしたフィクションだと本の奥付には書いてありますが、史実も相当ややこしかったようです。
この物語の後、スペイン国王の息子がクーデターを起こし、国王、王妃、宰相ゴドイらは1808年に追放されたとのことです。
ゴドイは追放後紆余曲折を経ながらも1851年まで43年間84歳の年まで生きていたということなので、当時としてはなかなかの長寿だったのではないでしょうか。
あっという間に斜め読みしましたが、面白い小説でした。宮廷のドタバタ劇、スクリーンで観ると楽しみが倍増するような気がします。