塩野七生さんの『ローマ人の物語』。
文庫本でちまちまと読ませていただいている。
高坂正堯さんの『文明が衰亡するとき』という素晴らしい本がある。
それと比較をするのは適切ではないと思う。
なぜならば、それぞれ、範囲もボリュームも著者の専門領域も異なるし、さらには著者の関心のありかすら別である可能性があるからだ。
ではあるが、高坂氏の本と「同じくらい」素晴らしいと思って読んでいる。
現在ようやく「悪名高き皇帝たち」を読み終えたところだ。
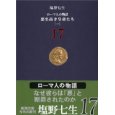
オクタビアヌスの後のティベリウス、カリグラ、クラウディウス、ネロという4人の皇帝をめぐる物語である。
カリグラやネロは若くして権力者になってしまい、それが元でものごとがよく見えなかったのではないか、という気がする。
治める、ということは、自分が好きにする、ということではなく、人々がいかに満足を得られるような演出をするか、ということかも知れないなとこの巻を読んで思った。
そういう演出を政治というのかも知れず、そうなると若さというのは、熱狂で人々から迎えられていい調子になっているときはいいが、ひとたび世の中の調子がおかしくなると、どういう方向に持っていくべきかとか、一時的にみんなの不満をそらすためにどういう手を打っておいたらいいかとか、誰を取り組みのリーダーにすべきかというような調整的な能力が必要で、それは若い君主にはなかなか求めることが困難なのではないかなと思う。
明確な意思があって、それをやり続ける意思があって、実行できる体力と脳みそがある。そして人々をして主役だと思わせるような演出ができる。
これが世の中を引っ張っていき、かつ人々から慕われながら仕事をしていくリーダーに求められる条件ではなかろうか。
思慮の浅さ、という点では、いくつかの善政もしたのだろうけれども、やはりカリグラやネロに及第点は与えられないだろう。
そんなことを思った。
読んでいる本 塩野七生『ローマ人の物語 文庫版17~20』
返信
