2週間ぐらい前から左の腕が時折ひどく痺れることがある。
今年の春先にも似たようなことがあった。
そのときは右腕で、頚椎の5番が出ているのが原因で神経に触っているからだということだった。
結局カイロやら色々行っているうちに夏ごろになって痛みがひいた。
今度は左かい!?といやあな感じがして、とある治療院に出かけた。
中国から来ている人がやっているところで、なかなか上手である。
今回、疲れがたまっていたことに加え、この左腕の痺れについて相談した。
すると、おもむろにヘラのようなものを出してきて、これでやろうということになった。
ヘラといっても、大きさは子どもの手のひらくらいのもので、象牙でできているのか
プラスチック製か竹のものなのか、見ただけではよくわからない。(めがねをかけて
いなかったせいもあるが)
ともかく、そのヘラを首や肩や背中にかけて、版画のバレンでこするように、上から
下に向けてゴシゴシこするわけである。
こする際には、タラーリと油のようなものをたらし、それを皮膚にすり込むように
しながらこする。
そうすると、あーら不思議。
悪いところが紫色に変色する。
同じように均等にゴシゴシやっているのだが、一部分だけが変色するのである。
(もちろん、私にはその様子は見えず、施術者の解説で理解するだけなのだが)
後で風呂に入って鏡でよく自分の肩を見てみてびっくり。
右と左の一部ずつ(場所は別)が見事に紫色に変色していた。
なんとなく、そこに悪い血が集まって、それを白血球たちが始末してくれれば
腕の痺れも治りそうな気がするではないか。
しごけば血が集まって充血するのは当然、という声も聞こえてきそうだが、普通
の充血とは全然違う色であり、しかもそこだけいまだに熱い。
なんだか、中国四千年の技を見たような気がする。
ちなみに日本ではその「ヘラ」みたいなものの名称は存在しないようだし、施術
者も、現物を日本で見たことは一度しかないと言っていた。
中国にはまだまだ色んな深いものが存在しそうだ。
個人的には、痺れがとれれば結果オーライである。
月別アーカイブ: 2008年8月
塩野七生『ローマ人の物語』のこと
塩野七生さんの『ローマ人の物語』を断続的にゆっくりと読んでいる。
今は文庫本の21「危機と克服」の(上)を読んでいるところだ。
アウグストゥス、ティベリウスというきっちりした皇帝の後、カリグラ、クラウディウス、ネロと続き、若気の至りのネロが混乱を招いて死んでしまった後、ガルバ、オトー、ヴィテリウスという聞いたこともないような軍人皇帝が1年の間に入れ替わり立ち代り国家の混乱の中、次々に就任しては殺されていくというややこしい時代だ。
ややこしく、さらにまた、カエサルのような素敵さも天才性もなく、ネロのような稚気ではあるが魅力的なところもないような人物たちのようである。
塩野七生さんは叙述家であり、立派な歴史家でもあると思うので、批判するつもりは全くないが、こういう混乱期の魅力のないリーダーたちをどういう心境で描いていたのだろうか、とふと立ち止まって考えてしまう。
面白くないというわけではないが、なんとなく淡々と叙述が進められているような気がして、たぶん塩野七生さんも面白くないなあと思いながら筆を進められたのではないかなあと忖度してしまう。
彼女にとって血沸き肉踊る心持ちで描いていたであろう人物たちは、グラックス兄弟やハンニバルであり、スキピオ・アフリカヌスであり、スッラやマリウスであり、そしてカエサルでありアウグストゥスたちであったろう。
それらの激動の人物と比べると、なんとも小粒の面白みに欠ける人たちを、塩野さんはどういう思いで書いていたのかなあと思う。
だからこそ、この時代の皇帝たちを描きながら、つい、カエサルだったらどうしたとか、アウグストゥスはこうしたとかいうふうに、すぐ筆が飛んじゃうんではなかろうか。
などと考えつつも、この人の描くローマとローマ人の歴史に今日も耽溺している。
面白い。
押入れ掃除後日談 古い官製はがきは交換しよう
先日押入れ掃除をしていたら、古い年賀状が随分出てきた。
それはそれでいいのだが、一方こちらから出す年賀状は、いつも少し多めに買うものだから、だいたい毎年10~20枚程度余ってしまう。
そういうものがここかしこから出てきた。
古いものでは平成10年ぐらいのものもあり、数えてみると百数十枚になっていた。
平日であったことを幸いに早速郵便局へ持っていった。
確か有償で普通はがきと交換してくれるはずだ。
ちょっと出費にはなるが、使えない「お年玉つき平成10年度の年賀はがき」を後生大事に持っていてもしょうがない。
結果は、一枚あたり5円の手数料で新品のはがきと交換してくれるので、100枚なら100×50-100×5=4500円分の現金ではがきを購入する計算になる。つまり90枚分の新品がこちらの手出しなく手に入るのである。
しかも驚いたことに(知らなかったのは私だけかも知れないが)、今では通常の官製はがきにも「インクジェット用」のものがあり、希望すればそれに代えてくれる。私の場合はパソコンではがきを作成することも時々あるので「インクジェット用」はがきにしてもらった。
まあ500円分損という見方もあるが、上記のとおり使えないものを持っていてもしょうがないと思う私のような人は是非交換されるといいと思う。
ちなみにはがきではなく、80円切手や50円切手との交換もOK(記念切手はだめ)らしいので、官製はがきは書かないけど手紙や絵はがきなら、という方は切手に交換されるという手もあるだろう。
押入れ掃除は気持ちいい
夏休み二日め。
ずっと前から思っていてなかなか実行できなかった「押入れ掃除」をやった。
妻も昨日、今日と二日連続でパートが休みだったこともあり、一緒に朝から取りかかった。
自分が大阪に単身で行っている間に家の色々なルールが形作られていって、それはそれできっちり機能していたのだが、私が帰ってきてスペースを使うようになり、一方妻は妻で押入れの大方を買い込んだ洗剤類や子どもの菓子類やなんやかやとどんどん、ものが増えていった。
そこへ私の工具類やら雑用品やら文具類やらがごちゃごちゃに混ざっていき、60Wの電球がそこかしこにありながら肝心のときには見つからず、また買い足したり、一番散逸していたのは乾電池で、一体どこにどういう種類のものがいくつあるのか・・・とにかくわずか畳2枚の押入れでありながら、収拾がつかなくなっていた。
とにかくまずは中のものを全部出す、というところから始めた。
上の段のものを全部出し終わったら、敷物があった。防虫の紙であるが、1998年10月に敷いた痕跡が残っていた。
なんと10年前である。有効期間は1年間と書いてある。ええっ?て感じだが、そんなもんかも知れない。
下の段。
こちらはまだ新しく、3年前の新聞が敷いてあり、そこらへんで一回何かをしたのだなあとわかる。
さて今度は再度収納の段階。
捨てるべきものを捨てたら、収納である。
これまで収拾がつかないくらいに乱雑だった原因は、どこに何を入れるかというルールがないままに二人でバラバラに収めていたことだと気づく。
そこで再収納する前に、どんなものがどれだけあり、どんなものがよく出入りするかということはこの数年の状況でわかる。
そこで、前からあった整理棚を用い、どこにどういうものを収納するかを決め、一気に収納していった。
朝8時から午後2時まで、結構かかったが、おかげでスッキリした。
どこに何があるかも瞬時にわかるようになったし、重複して無駄なものを買う恐れも少なくなった。
掃除をして幸せになる、というような表題の本が昨年暮れくらいからヒットしていたが、掃除や整理整頓は気分転換にいいし、健康にもいいというような気がする。
妻との会話もでき、良い一日だった。
さあ、この調子で明日は書類関係の整理だ。
海水浴について
珍しく今年は海水浴をしていない。
いつもは(大阪にいたときも含めて)両親、妻子と一緒に氷見に一泊海水浴旅行をしていたものだが、来春の子どもたちの受験ということもあり、今年は控えた。
もっとも私自身、7月に転職した一方で、妻との会話時間の確保のためのドライブや、前の職場の人と約束していた山登りなど行事も色々あり、海水浴というところまで気持ちが行っていなかったせいもある。
この後、お盆から1週間休みがあるが、墓参、妻の実家への挨拶、仕事の勉強と休み明けに向けた準備、押入れの整理など、やらなくてはならないことが目白押しだし、休み明けからは会社の重要なミッションであるお客様の経営相談という仕事が年末まで入っている。ボリュームも大変なものなので、よほどうまくやらないと業務量の多さでパンクしてしまう危険性がある。恐れることはしないが、準備はしておきたい。
そんなこんなで、今年は海水浴は我慢するが、来年はきっとまた行くぞ、と思っている。特に強く希望しているのは朝日海岸である。子どもたちもうまく進学しておれば、一泊ぐらい、コテージに泊まってというようなことをしたいものだ。
楽しみは先にとっておこう。
読んでいる本 塩野七生『ローマ人の物語 文庫版17~20』
塩野七生さんの『ローマ人の物語』。
文庫本でちまちまと読ませていただいている。
高坂正堯さんの『文明が衰亡するとき』という素晴らしい本がある。
それと比較をするのは適切ではないと思う。
なぜならば、それぞれ、範囲もボリュームも著者の専門領域も異なるし、さらには著者の関心のありかすら別である可能性があるからだ。
ではあるが、高坂氏の本と「同じくらい」素晴らしいと思って読んでいる。
現在ようやく「悪名高き皇帝たち」を読み終えたところだ。
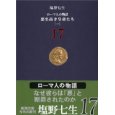
オクタビアヌスの後のティベリウス、カリグラ、クラウディウス、ネロという4人の皇帝をめぐる物語である。
カリグラやネロは若くして権力者になってしまい、それが元でものごとがよく見えなかったのではないか、という気がする。
治める、ということは、自分が好きにする、ということではなく、人々がいかに満足を得られるような演出をするか、ということかも知れないなとこの巻を読んで思った。
そういう演出を政治というのかも知れず、そうなると若さというのは、熱狂で人々から迎えられていい調子になっているときはいいが、ひとたび世の中の調子がおかしくなると、どういう方向に持っていくべきかとか、一時的にみんなの不満をそらすためにどういう手を打っておいたらいいかとか、誰を取り組みのリーダーにすべきかというような調整的な能力が必要で、それは若い君主にはなかなか求めることが困難なのではないかなと思う。
明確な意思があって、それをやり続ける意思があって、実行できる体力と脳みそがある。そして人々をして主役だと思わせるような演出ができる。
これが世の中を引っ張っていき、かつ人々から慕われながら仕事をしていくリーダーに求められる条件ではなかろうか。
思慮の浅さ、という点では、いくつかの善政もしたのだろうけれども、やはりカリグラやネロに及第点は与えられないだろう。
そんなことを思った。
