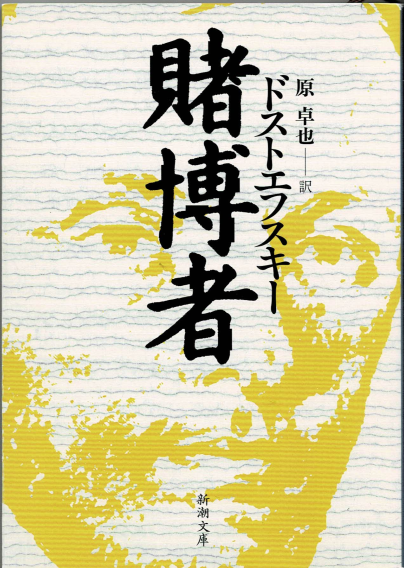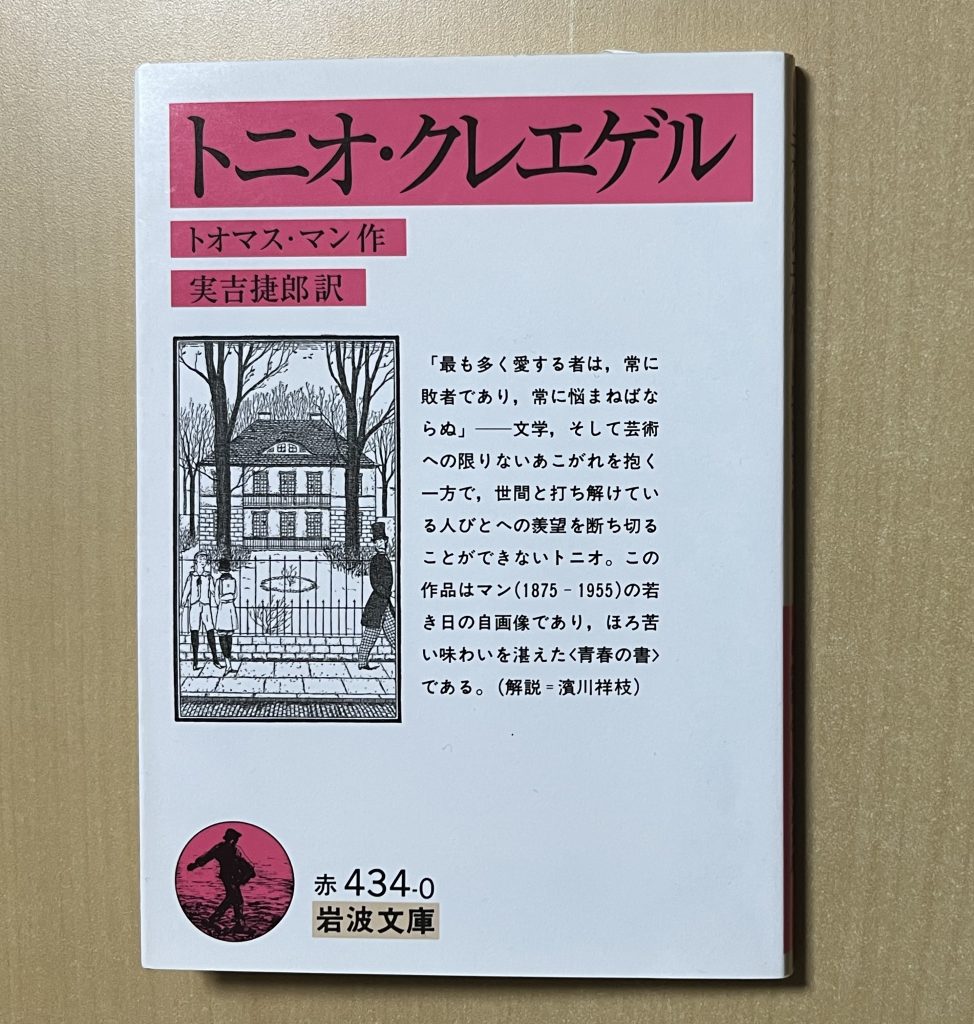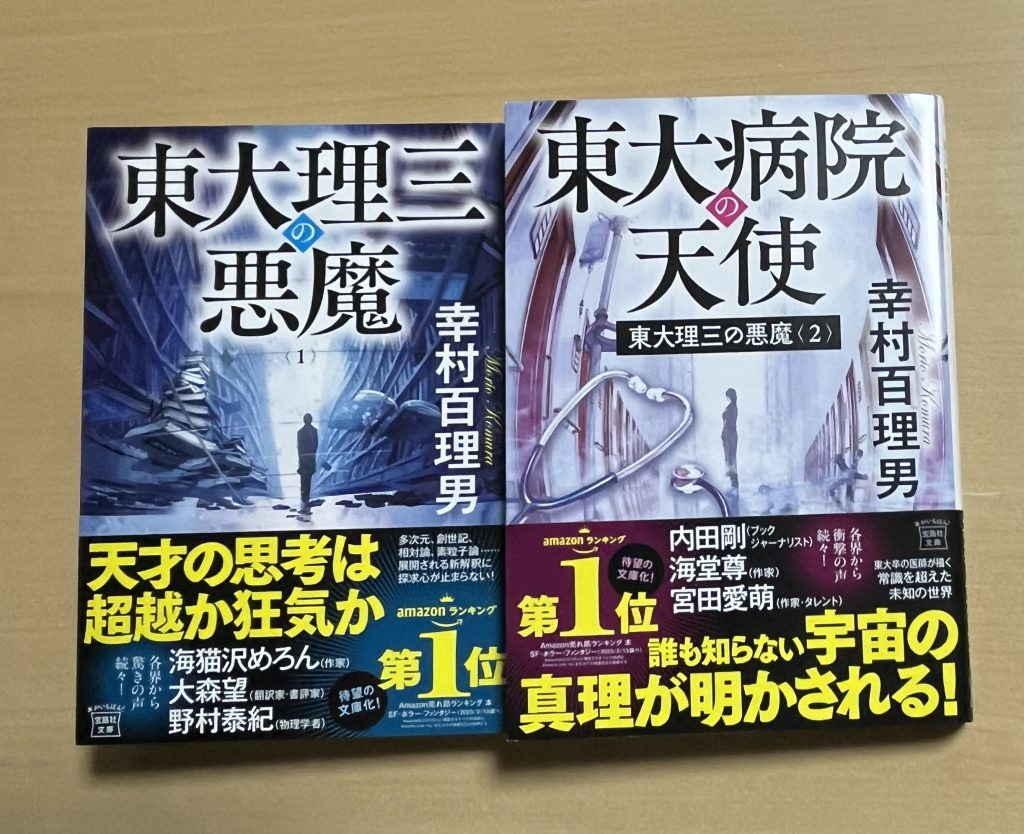フロイトさんが論文「ドストエフスキーと父親殺し」(光文社古典新訳文庫所収)の中で、ドストエフスキーのことをどうしようもないダメ人間であるかの如く酷評しており、ほんまかいなと思い、その最も端的な根拠の『賭博者』を読みました。
この本はほぼ実話をもとにして書かれたということです。
読んでびっくり。ああ、こうもダメ人間だったのか、この人は。と思う記述が至るところに。(フロイトさんが酷評している理由が少し理解できたような気がしました)
病気で寝ている奥さんを置いて、別の若い女性を追いかけて海外旅行に行った。このこと自体、一体この人は何をしておるのか、と思いますし、その女性に対して全身全霊をささげるような(かなり無様な)真似をして、歓心を買おうと必死になっている。挙句はルーレットにのめりこんですっからかんになり、しかもひとところで留まらずにルーレット行脚のために次の旅先まで行く始末。
滑稽なのは彼が訪れた街の名前が「ルーレテンブルク」。ルーレット(賭博)の街という意味の架空の街だそうです。
現代では、ギャンブル依存症というのはだらしないからなどでは必ずしもなく、ある種の病気であり治療可能だということですが、ドストエフスキー存命当時はそういう知見は恐らくなく、ダメな人という判定がなされていたのではないかと思いますし、フロイトさんがそういう論評をしたのも時代背景からしてやむを得ないのかも知れません。(とはいえ、同じ論文の中で「小説『カラマーゾフの兄弟』は、これまで書かれたうちで最高級の小説であり、作中の大審問官の逸話は世界文学の最高傑作の一つである」と絶賛もしているのですが)
それにしてもかくも自分のダメさ加減を、たとえ小説という形にせよ吐露して、それを口述筆記してくれた速記者のアンナ・グリゴリエヴナ・スニートキナさんが、後にドストエフスキーの求愛を受け入れてくれ、しかも彼がその後もギャンブルにのめりこんでも、すっからかんになった後の方が優れた作品を世に出すためのエネルギーになることを理解し、支えてくれた良き伴侶になったそうで、これはこれで彼にとっては僥倖だったのだろうと思います。
また何よりも、この小説に描かれているようなダメな自分を、その経験を、文学という形に昇華させることができるということが、これまた凄いことで、ドストエフスキーのドストエフスキーたる由縁かと思い直している所です。