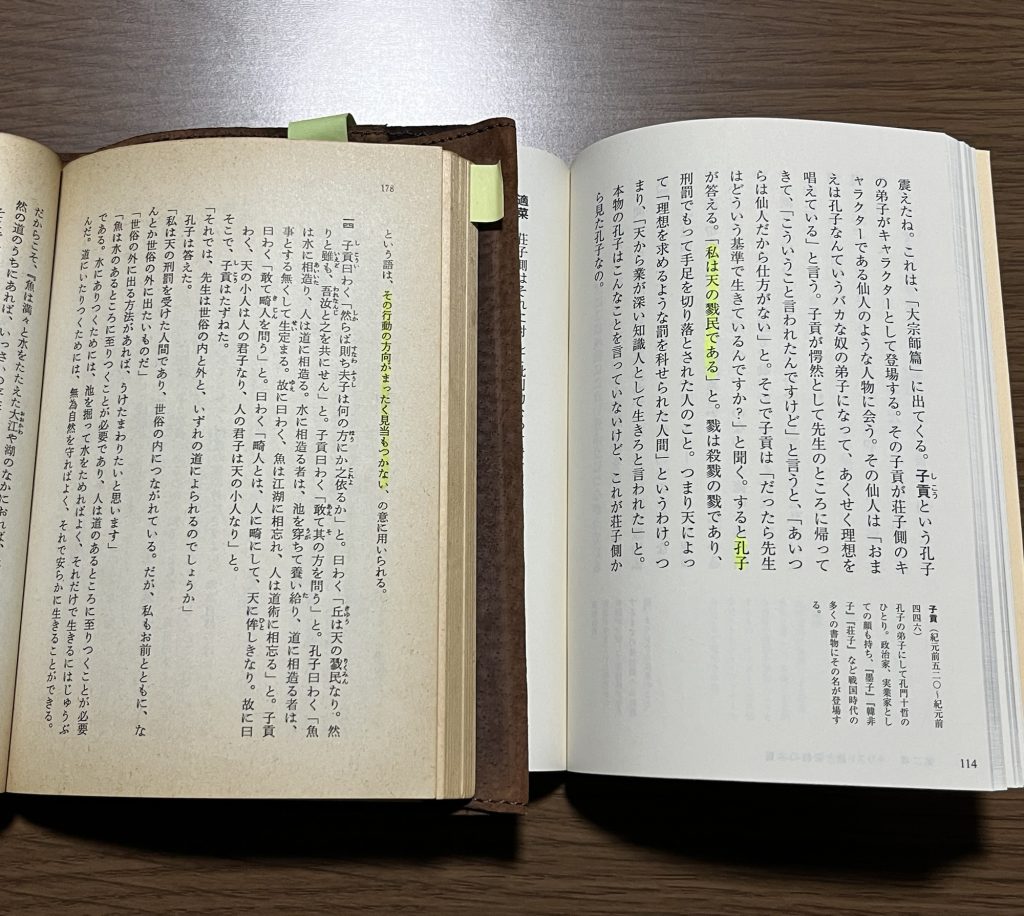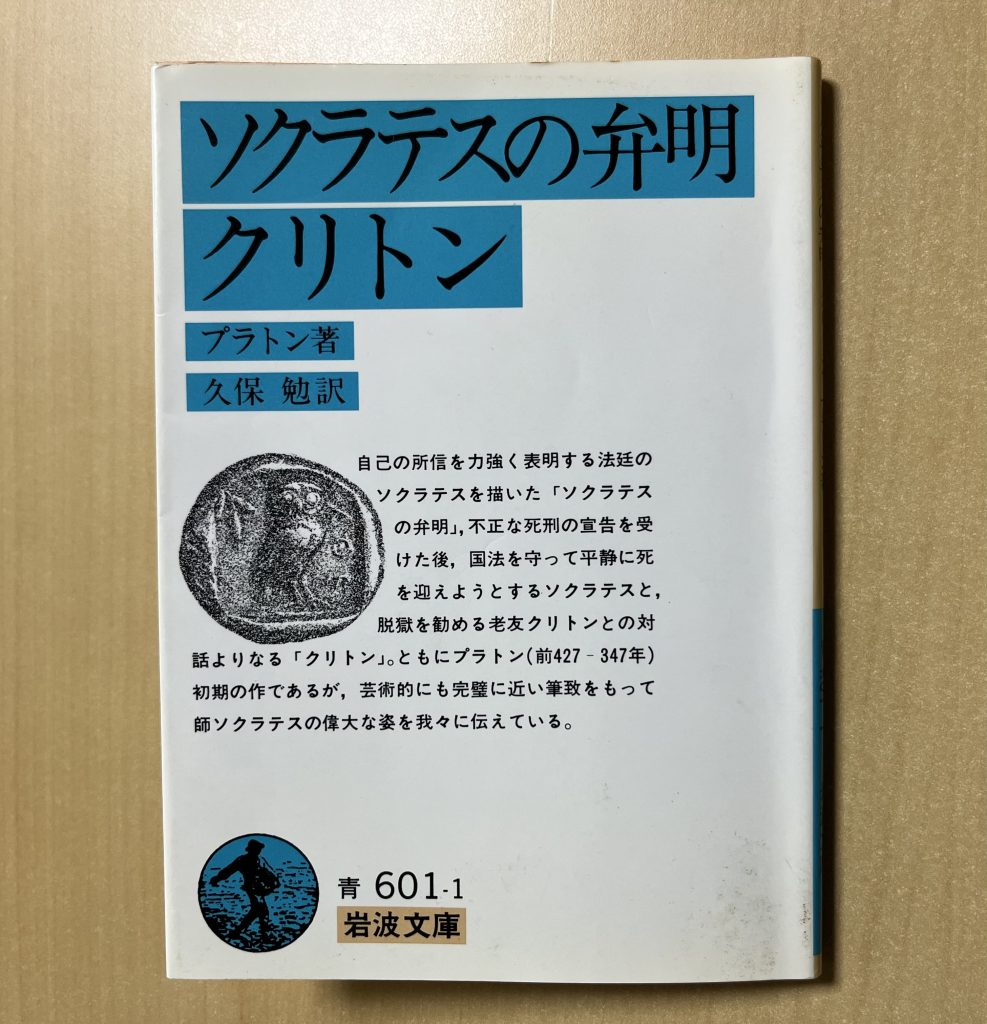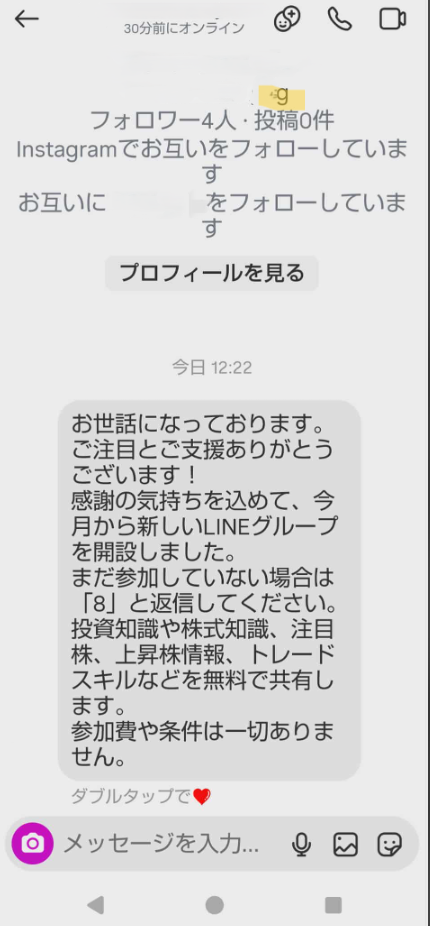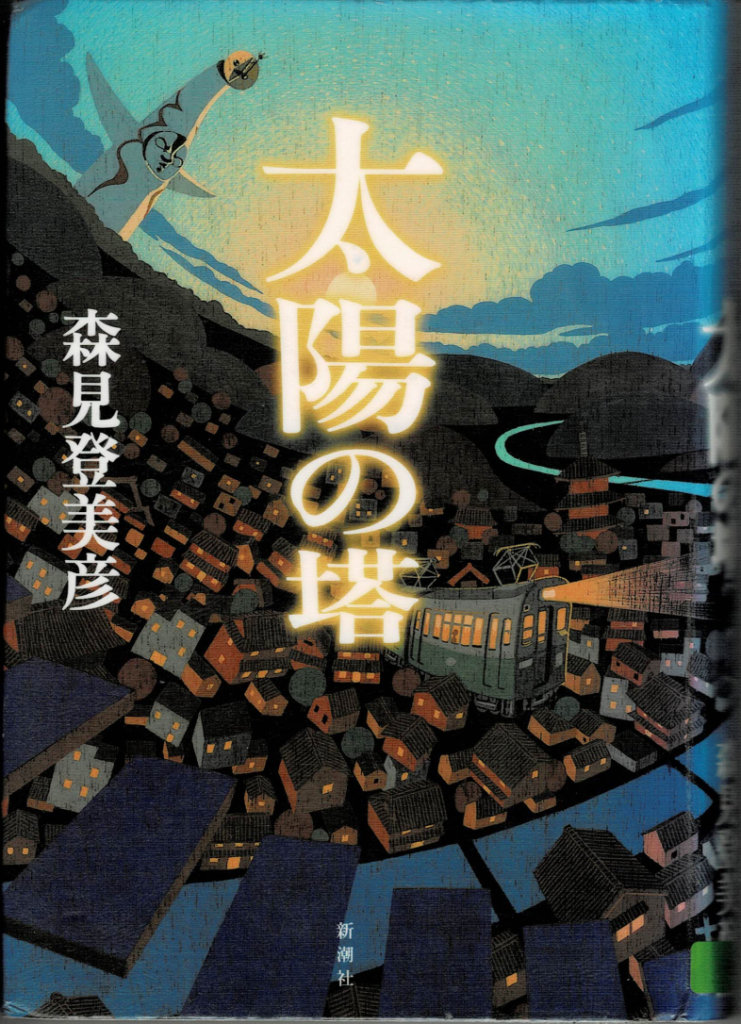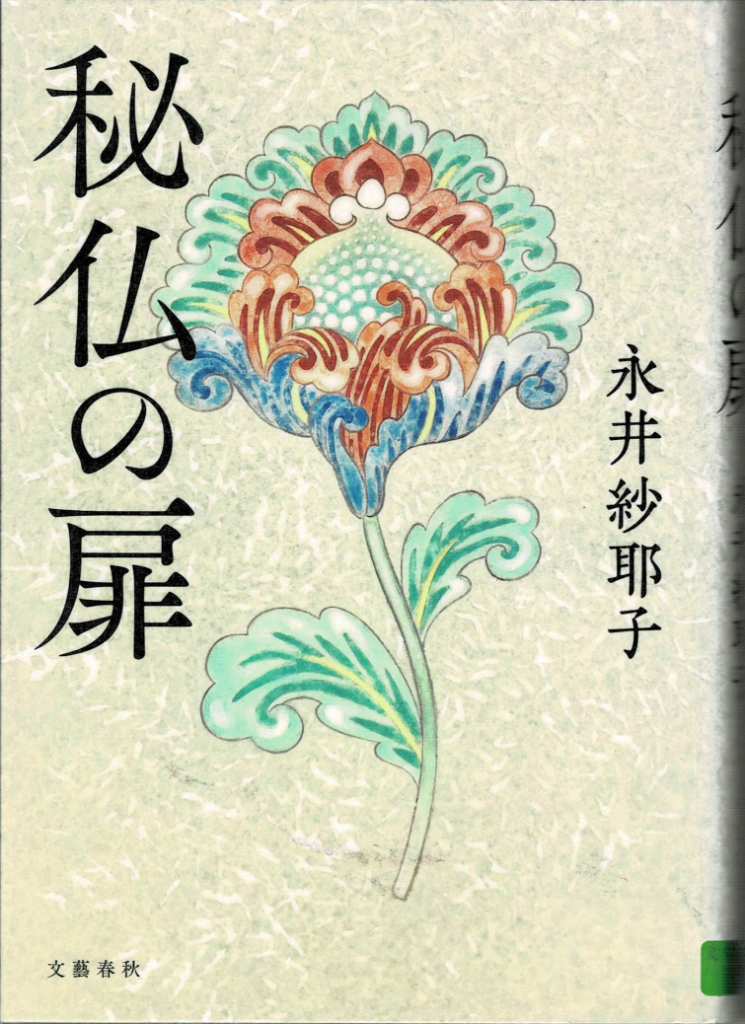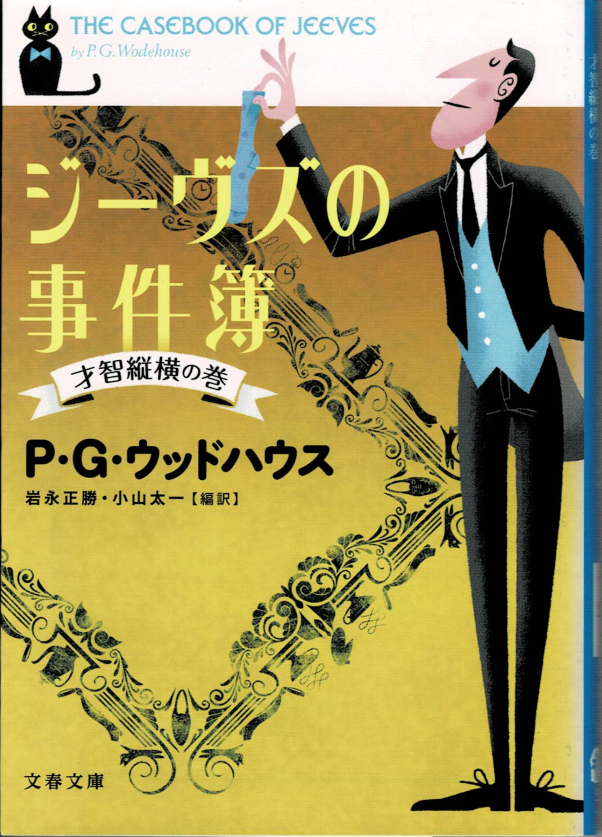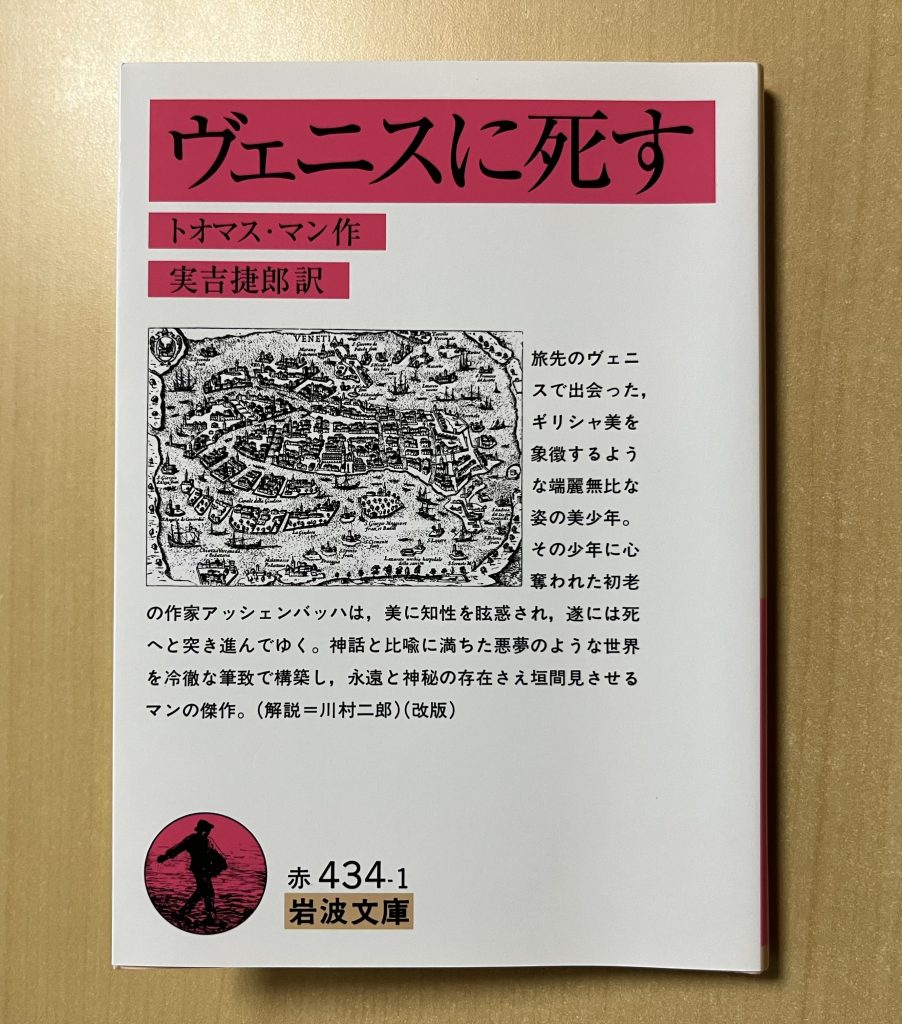『魔の山』から派生して『ヴェニスに死す』を経由して映画まで観て、とうとう『ブッデンブローク家の人びと』まで来ました。『魔の山』と『ブッデンブローク家の人びと』は筒井康隆さんが絶賛している小説ですが、私には高校生の頃に教科書でそういう作家がいるということを見たぐらいでした。古典と言われるものには当時も関心がありませんでしたが、最近はそういうものが読まれ続けていることの意味があるように感じており、こうやって少しずつ触れていくようになってきました。
さてこの小説、まだ中巻が終わったところであり、年内に下巻まで完読できるかどうかわかりませんが、中巻についてコメントしておきます。
この小説は、著者であるトーマス・マンの一族をモデルにしたものだそうで、北ドイツのリューベックを舞台に、ブッデンブローク家の4代にわたる商家の繁栄と衰退を描いたものだということです。
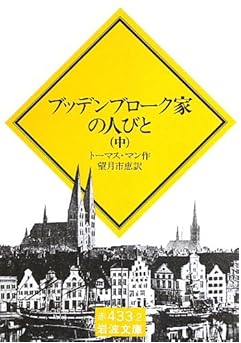
中巻は、大金持ちの実業家の一族の黄昏の始まりが描かれており、色々なほころびが徐々に出て来ています。
中巻の主役であるコンスル・トーマス・ブッデンブローク(コンスルは一族や企業の代表者というような意味のようです)は、必死で家業を守り通そうとするものの、弟やその他周囲の人々はどうも「学び」や「責任感」が不足しているような気がします。弟のクリスティアンなどは勘と虚栄心と好き嫌いが商売の判断基準になっている、没落ゆく商家の典型的な人物に見えます。
お金があるうちは良いですが、そのお金も、群がりくる金の亡者たちによって徐々に浸食されていきます。
とどのつまりは、気の弱い8歳のハンノ(トーマスの一人息子)に対する「存在否定」とも言われるべき父トーマスからの非難の言葉です。これが中巻の一番最後に放たれており、結構衝撃を受けます。その少し前からのハンノが受けている、明るく前向きなピアノレッスンの様子が鈍い輝きを発しているだけに、その後の暗転ぶりがあるのだろうなとなんとなく予感はしていたものの、です。
この中巻最後のトーマスからハンノへの叱責の言葉は私にとっては思いのほか暗澹たる気持ちにさせられました。母の溺愛(?)の反作用かも知れませんが、心の弱いハンノをなんとか元気に、生きがいをもって成長する子に育てたい、という母の気持ちであって決して溺愛というようなものではないと思うので、母ゲルダの振る舞いを責める気持ちにはなれません。
存在を否定されたようなこのハンノは、それゆえに、恐らく心の成長を得ることができず(もしくは中途半端な偏った成長になってしまい)、やがて若くしてこの世を去ってしまうというのが下巻の想像です。
ちょっと暗い話になりましたが、4代にわたる栄枯盛衰ものということで、しっかり向き合っていこうと思います。