中小企業診断士である私がユニクロのような大企業について勉強するのはあまり意味がないかも知れません。しかし私が社会人になった40年前にユニクロの1号店を広島で作った小郡商事は、当時は山口県の一中小企業だったということを考えると、柳井正さんという経営者が仮に不世出の天才だったとしても、今のユニクロではなく、これまでのユニクロの辿ってきた道を知ることで、他の中小企業にとってもヒントになることがあるかも知れない、と考え、時のベストセラーを手に取りました。著者の杉本貴司さんもp6で「私が見つけたのは「希望」である。この国に存在する名もなき企業や、そこで働く人たちにとって希望になるであろう物語である。」と述べておられます。
p38 なにかと言うと柳井が口にしたのが「それになんの意味があるんかね」だった。73歳になった柳井が母校の早稲田大学の新入生たちを前にこんなことを語りかけた。「人が生きていくうえで最も大切なことは使命感を持つこと。自分は何者なのか、そのことを深く考える必要がある」
p78 ノートに自分自身の性格について思うことを書き記していった。俺の長所はなんなのか。逆に短所はなんだ。
p79 ある思考法にたどり着いた。「できないことはしない」「できることを優先順位をつけてやる」悩みというものは、悩めば悩むほど出口が見えなくなってしまう。「いくら悩んでもできないこと」と「よく考えれば、悩むまでもなくできるかもしれないこと」に二分する。そして割り切る。エネルギーを割くのは後者だけ。そもそも解決できないようなことについて悩んでいる時間がもったいない。
p80 長所だけの人間になろうなんて考える必要はない。そもそも長所だからといって他人に誇るようなものでもないし、短所だからと劣等感にさいなまれる必要もない。
p80 仕事の内容を正確に伝えるために日々の仕事でやってもらいたいことをひとつずつ文章化してみた。この時の自筆の「仕事の流れ」がマニュアルの第一歩だった。口下手であることを認識しているが故の工夫だが。
p81 マニュアルの作成が終わると次に取り組んだのが、日々の商売の「見える化」だった。どの商品のどのサイズ、どの色が売れたのか。そんなことを毎日店を閉じてから自らノートに詳細に書き記していった。
こういう基本をしっかり大事に経営者自らコツコツとやっていったということが一つ。この頃のスタッフは一人か二人だったようです。
p82 カネ儲けは一枚一枚、お札を積むこと。信用の源泉は銀行預金を積み上げること。
p84 父から25歳の時に銀行通帳と印鑑を渡され、経営者となった。この時は山口県宇部市の商店街にふたつの小さな店を持つだけの存在だった。ここから10年ほど暗く長いトンネルの中でもがき続ける日々だった。
p90~101 柳井は経営者としての決意を一枚の紙に記した。・・・柳井の目標を大きく持ち上げてくれたのが・・・本を通じての偉人たちとの対話という静かな時間だった。・・・自宅に戻り食事を終えると、書物を通じて世界の英知と向き合う時間を大切にする。・・・松下幸之助と本田宗一郎。ユニクロの足跡は現実の延長線を越える足し算を描き実行に移す。ハロルド・ジェニーン(『プロフェッショナルマネジャー』)という事物の著書から学び取り、実行に移したこと。米マクドナルド創業者のレイ・クロック(『成功はゴミ箱の中に』)。ピーター・ドラッカー『マネジメント』『現代の経営』『イノベーションと企業家精神』『プロフェッショナルの条件』などは何度も読み返してきた。・・・クロック曰く「勇敢に、誰よりも先に、人と違ったことを」・・・柳井流の読書法は「もし自分だったらどうするか」と考え、筆者と対話するよう点にその妙がある。
p118 失敗を次の成功への気づきに変えてしまえばいい。
p121 まずはひょっとしたら大成功するんはないかと考えることがすごく大事。
p133 経営者のオヤジだけが元気でしきりに売り込んでくる。ところが現場を見ると社員を大切にしていないことがすぐに分かった。若い人たちが暗い顔で働いている。こんなところに未来はない。
p137 消費者はその商品について一番よく知っている人から買いたい。中内さんは小売業の革新者でありイノベーターだった。しかし商品について一番よく知っている人になろうという発想の転換がなかったことが、ダイエー凋落の原因だ。
p139 ゴールを定めていなかった。だから、たいして成長しなかった。
p140 柳井がレイ・クロックの『プロフェッショナルマネジャー』から学んだ二つのこと。
①現実の延長線上にゴールを置いてはいけない
②本を読む時は、初めから終わりへと読む ビジネスの経営はそれとは逆だ 終わりから始めて、そこへ到達するためにできる限りのことをするのだ・・・三行の経営論であり、逆算思考だ。
p155~160 商店街の個人経営店から「企業」へと脱皮するためのおおまかな見取り図。安本(安本隆晴公認会計士。小郡商事が上場企業になるための参謀となった人物)が最初に手がけたのが、組織図の作成だった。組織図とは、経営戦略を機能別に解き明かした説明書である。社長の下に書かれた各部門名の下に、誰が何を担当し、どんな責任を負う売上高や集客数、生産性、商品ロス率などの目標数値を書き記していく。組織を縦割りに分解するだけでなく具体的な機能と責任を明記していく。組織を動かすにはルールが必要。仕事のカタマリごとに誰が何をやるのかを割り当てる必要がある。安本が持ち込んだもう一つの概念が「会計思考」だった。簡単に言えば収益構造とキャッシュフロー構造のふたつを常にモノサシにせよということ。
p224 そもそも新しいことをやると失敗する。でも失敗することは問題じゃない。失敗から何を得るか。失敗の原因を考えて次に失敗しないために何をすればいいのかを考えるのが経営者。だから、失敗しないと始まらない。
もちろん無謀をよしとするのではない。柳井は「失敗しないためにとことん考え抜け」とも話す。最善を尽くしたつもりでも、経営に失敗は避けられない。失敗から何かを学び、より大きく成長するためには、つまずいてもまた這い上がってやるという覚悟が最初からなければ始まらない。
本田宗一郎も『俺の考え』の中でこんな言葉を残している。「研究所なんていうのは、99パーセントが失敗で、それが研究の成果である。人は座ったり寝たりしている分には倒れることはないが、何かをやろうとして立って歩いたり、駆け出したりすれば、石につまずいてひっくり返ったり、並木に頭をぶつけることもある。だが、たとえ頭にコブを作っても、膝小僧をすりむいても、座ったり寝転んだりしている連中よりも少なくとも前進がある」
p228 「どこが去年と違うんですか」「どこが他社と違うんですか」それが尋問のように続く。つまり、売れる理由です。売れる理由を一つずつ積み上げていく。
p241 待てど暮らせどお客は来ない。このままじゃ倒産する。胃がキリキリと痛む。経営者はそれでも考え続ける。そういう経験をしないと絶対に経営者にはなれません。(柳井さんが玉塚元一氏に語った言葉)
これ以降は、ユニクロが海外にも進出しつつ異文化とのコミュニケーションの齟齬や大企業病をいかに克服していったかという件になっていくので割愛しますが、最後に一つだけ。私がセミナーでよくお話をするユニクロの野菜販売の失敗(撤退ラインの事例として紹介しています)に絡んだエピソードを記しておきます。
p363~370 柚木治氏は2002年9月に野菜を扱うSKIPを立ち上げた。「野菜のロールスロイスをカローラの価格で販売します」・・・しかし結果は大失敗だった。2年もしないうちに26億円の赤字を出して撤退に追い込まれた。(柚木氏の奥さんは何度も警告を発しておられたとのこと)・・・その後「僕は失敗していない柚木君より、失敗したことがある柚木君の方が良いと思うな。失敗を生かして10倍返してください」という柳井さんの言葉でGUの立て直しに送り込まれた。柚木には野菜の失敗で得た3つの教訓がある。「顧客を知る努力は永遠に続けなければならない」「新しいことを始める時は、今ある常識を誰よりも勉強しなければならない」「社内外を味方に付けて、その力を使い尽くさなければならない」・・・柚木氏がGUの立て直しを図る歳にも、奥さんから言われた言葉がとてもためになったようですし、店舗スタッフの「ホントは私、GUの服は嫌いなんですよ」という言葉に、改めて顧客のこと、今ある常識を虚心坦懐に学ばなければいけないと思ったそうです。
ということで『ユニクロ』を読んだ直後に私が走った先は、5年ぶりの「GU」でした。
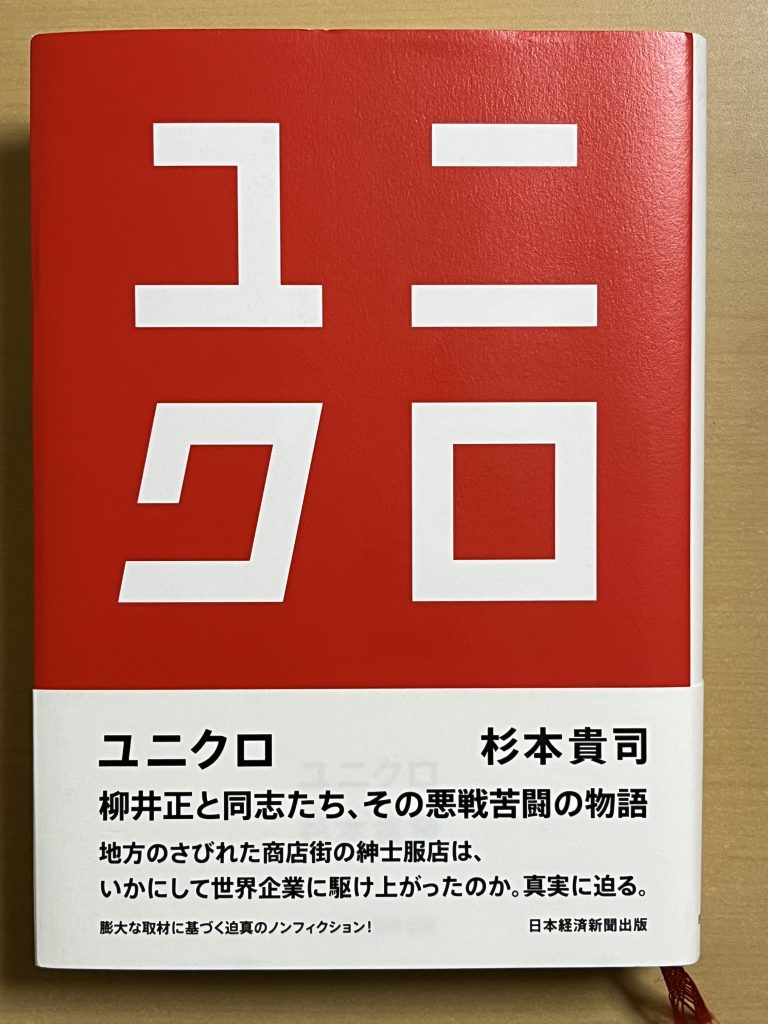

おはようございます。いつの間にか中陳さんの新しい投稿をメール通知する設定にしておりました。連休中に変化があるのかと思って毎日会社でチェックしておりましたが、そのうちこちらがコロナに感染してしまい、一週間の自宅待機を経て復帰したら、葬儀への参列が(明日を含め)4週連続という状態となっています。それは置いときまして、柳井さんに関する記述は面白かったです。自己(会社)は何のために存在するのか、失敗に学ぶ文化など大変参考になりました。私自身は「新しいことを始めるには①アイデアと②タイミングが重要」だと思っています。インターネットやスマホの普及などを見ていてもそう感じます。日産のEV開発やシャープの液晶パネルなどは世界初の技術ではあるのですが、ビジネスとしてはどうか?ということです。半導体にしても設計を中心としたファブレス企業が巨大な利益を得ていることを考えても窺い知れます。話が長くなりましたが、中陳さんのブログを見て私の頭の中にふと浮かんだことをお送りしました。今月6月21日(金)に面談できますことを楽しみにしております。今回の課題(議題)を後ほどメールでお送りいたします。よろしくお願いします。浜田
浜田様
コメントありがとうございます。
コロナにご葬儀にと大変ですね。
連休中はほぼ仕事でしたので、ブログに向かう時間も取れませんでした。申し訳ありません。
『ユニクロ』については、たまたま今日の北日本新聞の書評でも紹介されていました。評者の批判的なコメントにも納得できますし、私もちょっと物足りなさを感じましたが、関心の中心はこの会社の成長過程でしたので、ブログの記事もその辺を書かせていただきました。
「新しいことを始めるには、アイディアとタイミングが大事」というのは、さすが企業をリードしてこられた経営者ならではの慧眼だと思います。タイミングには顧客のマグマのような水面下のニーズの昂ぶりみたいなものをうまく感じ取るセンス(と競合の動向を見極める眼力)が重要ではないかと思います。そういう点では、柳井さんのお友だちでもあるソフトバンクの孫正義さんのADSL事業への参入は非常に良い例ではないかと思います。
長くなりましたのでこの辺で止めます。コメントありがとうございました。またよろしくお願い致します。