日本で出版されたのは2019年2月、ということで既に2年前になりますが、今も読み続けられているベストセラーとのことで、仲間内での課題図書に取り上げました。内容は富士フイルムやアマゾンなどの大企業の成功事例・失敗事例を中心に分析し、理論化したものですが、聞けば中小企業の経営者の方々も読んでおられる由。私たちの事業領域である中小企業の経営者に何か助言できるとすれば、どのような洞察が得られるだろうかと思いながら読み進めました。
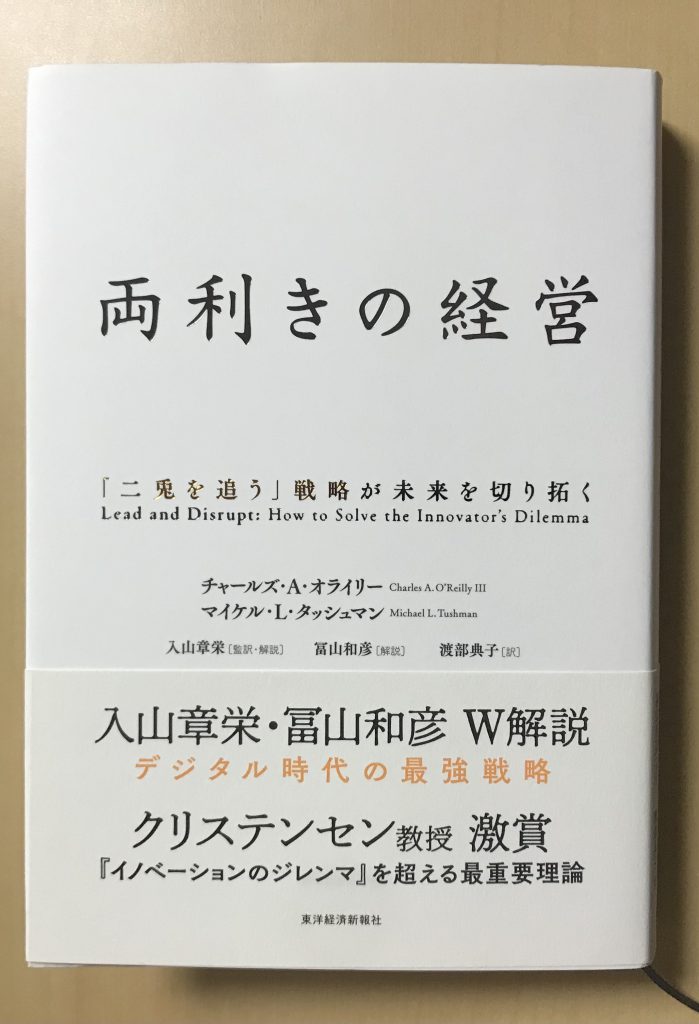
一般に経営資源に乏しい中小企業は事業領域を絞り込み、絞り込んだ領域でナンバーワンとなるよう経営資源を集中することで、大企業に入り込めないニッチで勝負すべし、というようなことを言います。ランチェスターの第一法則がまさにそれで、一点集中主義、局地戦、一騎打ち戦、などと言われています。しかし世の中はどんどん変化しており、顧客も変化し続けていることを考えると、今の顧客に今の組織能力で商品・サービスを多少改善しながら提供しているだけでは、いずれ他社に巻き取られてしまうという危険性がつきものです。どこからどうやって破壊的イノベーションがやってくるか予測することは難しいですが、市場環境の変化を注意深く見、顧客の声に注意深く耳を傾けていれば、ある程度は対応できるはずです。
しかしそれでもある日突然売上が激減するということもあり得ます。それに備えて日頃から、自分たちがわかっていること以外の市場や技術にも目を向けて、テストマーケティング的に「探索」をしていく必要があるのではないか、というのがこの本を読んでの私なりの見え方です。中小企業の場合、お金や人などの経営資源の使い道を決めることができるのは、ほぼ社長だけといっても過言ではないと思います。しかも、誰がその新規事業に取り組むのか、取り組めるのか、については、ほぼ社長だけ、といった中小企業が多いのではないかと思います。社長の肝煎りで後継者が、とか、特別に採用した人が、ということはあると思いますが。
とは言え、使える経営資源は極めて少ないわけで、例えば本体事業までをも毀損するくらいの資金をつぎこむようなことは避けなければなりません。ドラッカーが言うように「すべての失敗は経営者の責任」です。となるとどうするか。ユニクロがかつて野菜販売を行ってうまくいかないと判断して撤退した際には、あらかじめ撤退ラインを決めていたそうです。経常利益の何パーセント、とか、上限いくらまで、という風に決めておくことが大事です。しかし人間、特に叱責を受けることのない立場の人は、自分は間違っていない、もう少しこのままやればなんとかなるんではないか、といった「正常性バイアス」の罠に陥る危険性があります。正常性バイアスの有名な例は第二次世界大戦の時のインパール作戦だと言われています。(『失敗の本質』などに詳しく書かれています)
中小企業の経営者に注意する人はあまりいません。取締役会メンバーも株主も家族・親族であることが多く、ガバナンスが利きにくいと言います。頭でわかっていても、始めた以上やめられないし、経営者としての沽券にかかわる、ということでしょうか。そうした場合、第三者が冷徹な目で「社長、ちょっと行き過ぎていますよ」と言ってお止めすることも必要です。そういう役割として中小企業診断士などの外部専門家と顧問契約をする企業もあるようです。
中小企業の利点は、大企業のように、「戦略的な重要性が高いか低いか」「本業の資産の活用度が高いか低いか」といったような判断基準を用いて、幹部間で合意をして「探索ユニット」に色々なことをやらせるとか、「内部に矛盾をはらんだ探索ユニットと深化ユニットを共存させるために抱負や価値観や結束力のためにトップリーダーがリーダーシップを発揮しなければならない」といった苦労をそれほどしなくても、自分の判断で意思決定できることではないかと思います。
他方で活用できる経営資源がほとんどないため、自分自身が中心になって、本業もやりつつ新しいこともやらなければならないという物理的制約が大きい点が弱点ではあります。論理的な分析や理由づけに時間をかけなくて良い分、また、何が結果的にうまく行くかわからないということもあり、思いつきに近いことでのチャレンジも許容されるかも知れません。思いつきに近い取組みでも効果を早いサイクルで確認していくため、OODAループと言われる試行錯誤の手法や、そのためにMVPと呼ばれる必要最小限の試作品を市場に出して市場の反応を見ながら並行して商品のレベルアップを図っていくといったやり方も必要なのだろうと思います。そのためには、世の中のトレンド、これから世の中が進む方向性、などについて外部専門家の知見に耳を傾けることも必要だと思います。
また、業況の厳しい赤字企業の場合はどうすべきか、といった難題もあります。もし資金を一時的であれ調達できる見込みがあるのであれば、補助金を活用して資金リスクを軽くして新しいことに挑戦するという方法もあります。折しも今、新型コロナウイルスが猛威を振るっている中で、国がものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金を通年で募集していますし、また、この3月には「事業再構築補助金」という新しいメニューも出されるとのことです。いずれも厳しい審査があるため、応募すればお金がもらえるというものではありませんが、厳しい状況にある中小企業も、そういう支援メニューも活用して、自ら変化することにチャレンジしていただきたいですし、そういう経営者の方々を応援していきたいと思っています。
中小企業診断士 中陳和人のホームページはこちら⇒ https://www.nakajinkazuto.com/
