ご縁のご縁のご縁で、ITマスターという役割をいただき、時々お仕事をいただいています。もちろんジェダイの騎士のようなことはできません。小学生から高校生までを対象に、将来の職業としてIT関連の仕事を選んでもらえたら良いなあという厚労省系の施策の一環です。
2017年度から取組が始まり、初めの頃は職業体験イベントでのお披露目が中心でした。本来は小学校高学年向けに作られたカリキュラムということで、担当の職員さんが各小学校などを回り、出張授業を受けてみませんかと提案しておられた甲斐があり、2年目からはあちこちの小学校で出張授業を実施してきました。
いよいよ来年度2020年度からは小学校でプログラミングが授業で必修化となるということもあり、この一年は随分多くの小学校から引き合いがあり、私たち講師陣も大忙しでした。珍しいということからか、テレビ、新聞などマスコミの取材も結構ありました。ありがとうございました。
毎回20~30人の生徒を対象に実施するということで、実機を使うため、操作指導をする必要があります。かつ受講者全員がある程度は触って実感できるようにするという目標があるため、一人の講師で対応することは極めて厳しいものがあります。
おかげさまで私と同じITマスターの登録者が増え、小学校からの引き合いの増加とともに、一回の授業で同時に数人のITマスターが携わって授業を作ることができました。その都度メイン講師も持ち回りでできるようになり、他の講師の語りや進行の仕方など、毎回とても勉強になりました。 自分でもインストラクションプランは作りましたが、講師によってはA3数枚にわたる進行表(すごい!) を作っていた方もおられました。
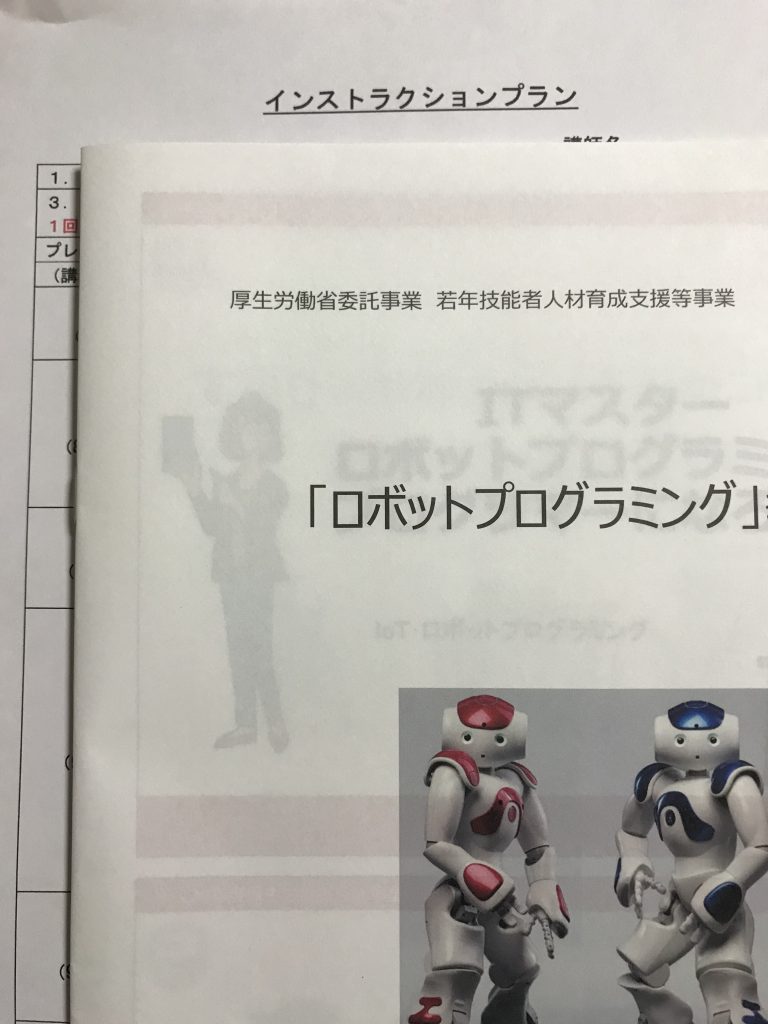
今日が今年度の最終回でした。富山県西部の某小学校で5年生総勢61人が参加し、人数が多いので1、2限目と3、4限目の2回に分けての実施でした。基本的な進め方はカリキュラムに沿って同じやり方なのですが、子どもたちの発想は実にユニークで、毎回楽しく授業を進めさせてもらいました。来年度は正規の授業としてプログラミング(ロボットということではないのでしょうけど)が導入されるため、恐らくこの授業に対するニーズは大きく減るような気がしますが、一般的なプログラミングとロボットを使ったプログラミングは必ずしも同じではないので、案外またニーズが続くかも知れません。
ITマスターとしての役割はまだ他のメニューもありますので、今後も精進が必要なようです。がんばらなくっちゃ。
