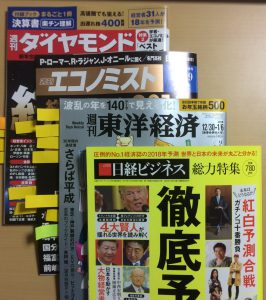
最近は毎年年末に主要経済誌が翌年の予測の特集号を出すのが慣例になってきました。
今回は『日経ビジネス』『東洋経済』『エコノミスト』『ダイヤモンド』の各誌をざっと総ざらえしてみました。
ユーラシアグループのイアン・ブレマーさんと英国エコノミスト誌のビル・エモットさんが複数の雑誌に登場していました。特にブレマーさんは3誌にまで顔を出していました。ということでブレマーさんの象徴的なコメントから記載していきます。
1.日経ビジネスより
ブレマーさん:Gゼロの拡大、ポピュリストの増大と権威の崩壊という潮流はさらに加速。トランプ大統領の弾劾は(中間選挙までは)なく、米国第一主義は続く。
ジョセフ・スティグリッツさん:(中国の今後について)習近平国家主席は以前にはない方法で権限を集中させている。債務主導型の成長を続けてきた。債権問題が深刻化するのを避けつつ成長を維持できるか。
ビル・エモットさん:(英国について)ジェレミー・コービン氏率いる労働党は格差是正を愚直に訴え支持を高めている。2018年労働党政権が誕生するかも。
スコット・ギャロウェイさん:GAFA4社の中ではアマゾンが抜け出す可能性が高い。音声アシスタントが既存企業のブランド資産を壊す。今のトレンドが続けば、平均的なミレニアル世代は死ぬまでの間にエフィスブックとインスタグラムに合計2年半分の時間を費やす計算になる。かつて人間が神に聞いていたことを、私たちがグーグルに聞くようになっているとすれば、それは「神」と言えるだろう。グーグルは「脳」、フェイスブックは「ハート(心)」、アマゾンは「胃袋」、アップルは「局部」(アップルは財力や創造性の象徴であり人間の生殖本能にアピールしているから)。
2.東洋経済より
ビル・エモットさんとリンダ・グラットンさんの対談。
グラットンさん:日本企業は人材育成にかける費用を減らしてきている。これは間違い。
エモットさん:日本企業は高水準の利益を上げており余裕はある。人材育成予算が縮小しているのは、非正規雇用が増えたことの裏返し。こういうやり方で競争力を高めようとするのは問題。
グラットンさん:日本は世界のどこよりも急速に高齢化が進んでいる。日本がこれにどう対処していくかに世界は注目しており、日本はその経験を教えられる。また他国と比べて日本人はロボットやAIに対する信頼が厚く、生産性向上や人生を豊かにしてくれるものとしてロボットやAIがどう役立つかを示すことができる。
2018年はリーマンショックから10年。先進国も新興国も経済は堅調で「ゴルディロックス(適温)経済」が続くと思われるが、信用危機は10年サイクルで到来するとも言われている。油断禁物。
ロシア。財務大臣を務めていたアレクセイ・クドリン氏に注目。首相に指名されるかも。もう一人の注目すべき人物はセルゲイ・ソビャーニン・モスクワ市長・・・だそうです。クドリン氏が提唱する構造改革プランが実現すれば3%成長が期待できるとのこと。
中国経済。習近平氏の2期目は改革促進。
2015年12月の中央経済工作会議で提起された「五大任務」によって経済の構造改革が進められるのではないか
五大任務:①過剰生産能力解消、②不動産在庫削減、③デレバレッジ(債務削減)・資産圧縮、④コスト引き下げ、⑤効率的な供給拡大(略称三去一降一補)
2020年までの「小康社会の全面的完成の決勝期」に挙げられた3つの重点戦略:①重大なリスクの防止・解消、②貧困脱却、③汚染対策(全面的完成とは、2015年に5575万人いた貧困人口を2020年までにゼロにすること)
金融政策はやや引き締め(資産管理業務規制など)でいくため短期的には景気減速も予想されるが、6%台の成長を維持し、2020年所得倍増計画達成に向かっていくであろう。
ライドシェア・カーシェアが浸透。
日本では白タク行為規制によりライドシェアはまだ導入されていないが、個人間のライドシェア(持ち主が使わない間、他人に車を貸す)は人気が出てきた。カーシェアは借りた場所に車を返すラウンドトリップ方式が主流、借りた場所以外の場所にも返せるワンウェイ方式はまだ。
メルカリ。
CASHが出たら即同様のサービスを開始。「メルカリナウ」というサービス。楽天もフリマサービスをメルカリを猛追している。メルカリはモノの売り買いに加え、自転車シェアサービス「メルチャリ」やスキル・知識のマッチングサービス「ティーチャ」などコトのサービスシェアへと拡張を始めている。日本発のフリーマーケットサイトから目が離せない。
ビットコイン。
デンマークの投資銀行サクソバンクは2018年に6万ドルまで上昇するがそれがピークとなり、その後は1000ドルまで急落するであろう。各国政府の規制と国家による独自仮想通貨発行が価格急落の要因になる。
堺屋太一さん。
2020年が過ぎると、大不況になる可能性が高い。膨大なカネを費やす東京オリンピックが終わって、公共事業が止まり、東京都内にまで少子化が及んで空き家だらけになる。2020年代後半には、医者が猛烈に余る。仕事確保のため健康な人を病人扱いしようとする恐れがある。不動産価格は暴落する。江戸時代でいうと天保のころのような雰囲気になる。近い将来の日本でも社会の安定を壊すようなムードが高まるだろう。閉塞感の源である人口減少問題に対して改革の機運が起こる。具体的には移民受け入れを政策的に行うべき。かつての日本は移民受け入れをし、彼らや彼らの子孫は偉大な業績を残したり日本文化の発展に貢献した。日本人は同化力に自信を持つべき、日本文化は決して日本土着の日本人だけで作られたものではない。
3.エコノミストより
嶋中雄二さんの景気循環論。
キチンサイクル、ジュグラーサイクル、クズネッツサイクル、コンドラチェフサイクルの4つの景気循環サイクルすべてが上昇局面になる「ゴールデンサイクル」(嶋中氏命名)という視点で見ると、米国は2017年から2018年までがゴールデンサイクルとなる。2019年はコンドラチェフサイクルを除きあとの3つは下降へ向かう。2018年終わり頃から2019年にかけてインフレが発生する可能性がある。(米国のことです)
水野和夫さんの予言。
ゼロ金利下では近代資本主義は成り立たない。国家は労働分配率を高める努力をせずに、金融緩和のための低金利政策に邁進し、ROE(株主資本利益率)を高める号令を発することに躍起に。この結果、緩和で市中にあふれたマネーが株式に集中し、一部の投資家のみに莫大なリターンをもたらしている。
16世紀の欧州では、オランダのチューリップバブル後、リターンを得た商人が、次にオランダと英国の東インド会社、南海会社を選んだ。その後南米との貿易に期待が過剰に膨らみ、株価が急騰し、ある日はじけた。この南海泡沫事件から見れば、チューリップバブルは序章に過ぎなかった。それに引き寄せて考えるならば、10年前のリーマン・ショックも序章に過ぎないのではないか。2008年のリーマン・ショックは世界に大きな景気後退をもたらしたが、足元ではまた世界中の資産価格が異様に上昇している。高リターンを得た一部の投資家が世界中で再投資をしているからだ。
これから100年は近代資本主義とは違う世界が再構築されていく。今の子供たちの世代が再構築していく。今はその過渡期とも言え、絶えず改善策を見つけては一歩ずつ進んでいくしかない。
中国のIT巨大企業。BAT:検索大手のバイドゥ、EC最大手のアリババ、SNS最大手のテンセント。
4.ダイヤモンドより
地銀は利益が20%減。銀行にとっての脅威はバランスシートの健全性からPLの収益性に移行している。(貸出先の企業の業績低迷=銀行の資産の不良状態がバランスシートの問題、PLの収益性は利益が出ずに企業を維持していけなくなる危険性という点での問題)
 (地銀の本業低迷行の地図はショッキング)
(地銀の本業低迷行の地図はショッキング)
似鳥昭夫氏のコメント。
五輪景気や消費増税の駆け込み需要が終わる2020年以降の5~10年ぐらいは大不況になる。不況はチャンス。不動産価格が下がれば立地が確保しやすくなり、大手企業が採用を控えれば優秀な人材を採用しやすくなる。消費減退の影響で一気に寡占化が進む。
KDDI田中孝司社長のコメント。
われわれはライフデザイン企業に変革する。が、通信事業がコア事業であることになんら変更はない。
IoTに関しては現在消費者向けに力を入れている。家のIoT化を実現する「auホーム」はこれから増えていく。鍵となる端末はカメラである。本当に需要があるのは家電操作などの機能ではなく、家の見守り。
以上、私の勝手なつまみ食い抜粋ですが、2018年またはそれ以降を考えて行くための、自分自身の参考情報として記載しておきたいと思います。
