書店で帯を見て思わず買ってしまいました。
塩野さんの『ローマ人の物語』文庫版の30巻で止まっているのですが、この人のライフワークだったはずの『ローマ人の物語』が結了し、後は悠々自適にエッセイなど書いてお過ごしになってもいいはずなのに、なぜまだ旺盛な著作活動を続けるのか、それもローマよりも古い時代のギリシアにスポットを当てて大部の作品を手がけておられるのか、『ローマ人の物語』の第1巻でギリシアのことを結構なページを使って書いたのになぜまた稿を新たに書いておられるのか、日本のことが気になって仕方がない(と思われる)塩野さんがなぜ今ギリシアの民主制を書くのか、そんなことが一気に頭の中を駆け巡り、即レジに行きました。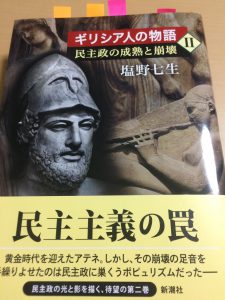
塩野七生節というと失礼かも知れませんが、この人の語り口には相変わらず独特の趣きがありグイグイ引き込まれます。
前半は毎年民主的に選ばれ、30年もの長きにわたりアテネの平和と繁栄を先導した政治家ペリクレスについての記述です。現状をしっかり説明し、自分の考えを伝え、可否判断はきみたちだと明言する。塩野さん曰く「真の意味での政治家であった」。
ペリクレス時代の最晩年に始まったペロポネソス戦役。アテネの首相ペリクレスも相手国スパルタの王アルキダモスも(この二人は友情と信頼で結ばれていたらしい)どちらも戦争になることを望んではいなかった。にもかかわらず27年間もだらだらと、直接の戦いもないままに続いてしまい、最後はアテネの劣化、さらにはギリシア世界の衰亡に至ってしまったということです。
159ページからのペリクレスの開戦1年後の演説は現代ヨーロッパの高校の教科書にも載っている見事な民主的なマニュフェストだと塩野さんは評しています。
「われわれの国アテネの政体は、われわれ自身が創り出したものであって、他国を模倣したものではない。名づけるとすれば、民主制(デモクラツィア)と言えるだろう。国の方向を決めるのは、少数の者ではなく多数であるからだ。・・・(中略)・・・アテネ市民が享受している、言論を始めとして各方面にわたって保証されている自由は、政府の政策に対する反対意見はもとよりのこと、政策担当者個人に対する嫉妬や中傷や羨望が渦巻くことさえも自由というほどの、完成度に達している。・・・(中略)・・・アテネでは外から来る人々に対して門戸を開放している。他国人にも機会を与えることで、われらが国のより以上の繁栄につながると確信しているからだ。」
これほどの賢い人々だったはずのアテネが、ペリクレスの晩年以降、衆愚政治と言われるような状態になってしまいます。
塩野さん曰く「デモクラシー(民主制)のコインの裏面がデマゴジー(衆愚制)なのだ。」
この違いは、ペリクレスがいなくなったらアテネ市民がバカになったわけではなく、リーダーの性質が変わっただけだと書いておられます。
「民主制のリーダー:民衆に自信を持たせることができる人、衆愚制のリーダー:民衆が心の奥底に持っている漠とした将来への不安を、煽るのが実に巧みな人。前者が「誘導する人」ならば後者は「扇動する人」になる。前者は、プラス面に光を当てながらリードしていくタイプだが、後者となると、マイナス面をあばき出すことで不安を煽る。」
そんなこんなの紆余曲折を経た後、ペロポネソス戦役は徐々にアテネの敗色が募り、最後は完膚なきまでに打ちのめされてアテネは衰亡の道を辿っていきます。途中、ペリクレスの甥でペリクレスの後継者的な位置づけになるアルキビアデスという政治家が現れたりしますが、この人はアテネから追放され、敵方のスパルタの指導者になり、次いでペルシアの軍を率い、またアテネに戻るという不屈の人ですが、最後には暗殺されてしまったようです。
歴史にifは禁物とはいうものの、後になって振り返ると、先見の明のある優れたリーダーを、民の選択で潰してしまい、自ら滅びの道を辿ってしまうこともありうる・・・上から法律で道徳感や公益への奉仕を強制するのではなく、一人ひとりが自発的に共助に向かうような心の豊かさがあれば、衆愚などと言われるような状態にならないような気もしますが、不満が募るとついアジる人についていってしまう弱さを持っているのかも知れない、そんなことを塩野さんの本を読むと感じます。
